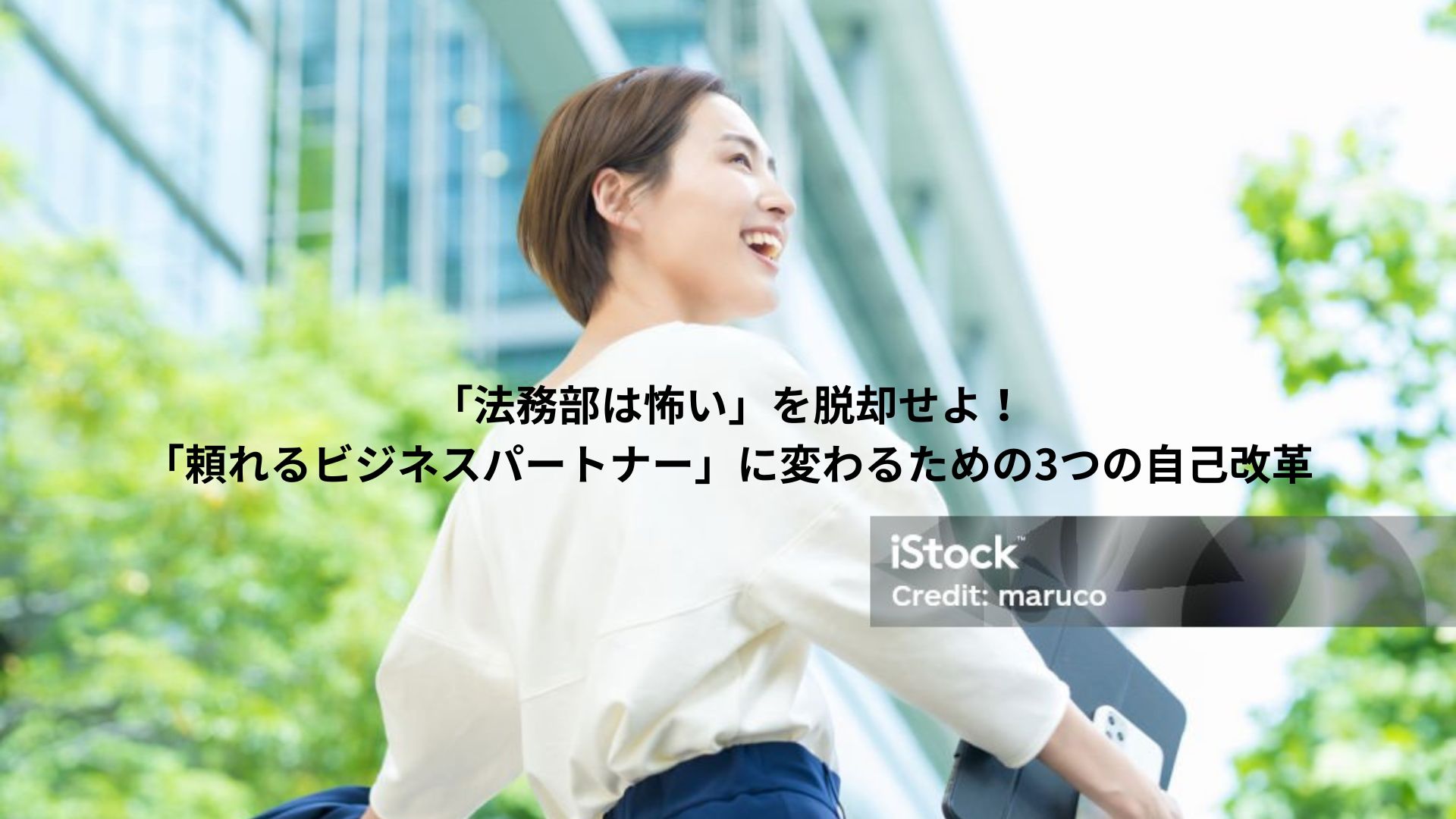※ 本記事には、プロモーションが含まれています。

社内の各組織から「法務部は怖い」または「法務部は偉そう」といった、良くない⁉評判がなされている可能性があります。
これは、法務部による専門的なアプローチが、事業部門との間に深い溝(孤立)と業務の機能不全を生んでいる客観的な証拠です。
法務はリスク管理のプロフェッショナルであるにもかかわらず、そのネガティブなイメージこそが、本来の仕事であるリスク予防を阻害する最大の障壁となっています。
なぜなら、社員が「怖い」と感じれば、問題の芽が小さいうちに相談に来ることはなくなり、法務部は手遅れの「火消し」に追われることになるからです。
法務部門の真の価値は、事業を「止める」ことではなく、「リスクを管理しながら加速させる」ことにあります。
本記事は、この現状を打破し、法務部員としてより高いステージへと進むための、意識と行動を変える具体的なロードマップ、3つの自己改革を提案します。
この記事を読むことで得られる3つのリターン
この現状を脱却し、意識を改め、自らの立ち位置を「邪魔者」から「頼れるビジネスパートナー」へと戦略的に進化させることで、あなたは以下の具体的なリターンを手にすることができます。
- キャリアのステージ向上と市場価値の最大化:
- 単純な契約書のレビューや雛形適用に終始する「受け身」の担当者で終わらず、経営層の視点に立ち、M&Aや新規事業開発における法務戦略をリードする「攻め」の参謀役へと役割を拡大できます。法務人材としての市場価値は劇的に向上し、より挑戦的で報酬の高いポジションへの道が開かれます。
- 自己肯定感の劇的な上昇と組織貢献の実感:
- 「うるさい人」「遅延の原因」ではなく、他部署から「あなたのおかげで、この新しいビジネスが安全に立ち上がった」と感謝される存在に変わります。事業成長への貢献を実感することで、日々の業務に対する内発的なモチベーションと自己肯定感が最大化されます。これは、法務部員の精神的な充足に直結します。
- 効率的なリスク予防体制の確立と業務負荷の軽減:
- 社員が法務に「怖い」と感じなくなれば、彼らはためらいなく、企画段階や交渉初期という最も早いタイミングで相談に来るようになります。これにより手遅れになってから対処する高コストな「火消し」作業が激減し、私たちは本来の使命である、ビジネスを支える強固な「予防法務」の設計と運用に、より深く集中できる理想的な環境を手に入れられます。
- 問題と原因: 「法務部は怖い」というイメージが孤立と機能不全を生む原因を分析
- 最大の障壁: 恐怖心こそがリスク予防を阻害する最大の要因。このイメージ転換が最優先課題
- 解決策: 「頼れるビジネスパートナー」への進化を目指す、3つの核となる自己改革(コミュニケーション改革、現場主義、推進力としての役割再定義)を提示
なぜ私たちは「法務部は怖い」というレッテルを貼られるのか?

私たち法務部が社内の他部署から「怖い」「うざい」「偉そう」と思われてしまうのには、明確な原因があることに注意する必要があります。
その原因は、私たちが意識せず作り上げてきた「コミュニケーションの壁」と「スタンスの壁」にあると考えて良いでしょう。
この負の連鎖を断ち切るためにも、まずはその原因を直視することが大切です。
「理解不能な言語」で思考停止を誘発する壁
私たち法務部員は、法律という専門性の高い言語で思考しています。
しかし、その言語を、事業部門が理解し、行動に移せる「ビジネス言語」に翻訳する努力を怠ると、深刻なコミュニケーション不全が生じます。
「法律オタク」な自己満足の言葉
「これは〇〇法に規定される契約不適合責任に該当するため、条文の趣旨に鑑み、現状の規定ではダメです。」――このような説明は、私たちの専門知識を満たすかもしれませんが、聞いている事業担当者にとっては「だから結局、何をどう変えれば、いつまでにできるんだ?」という疑問しか生みません。
専門用語の羅列は、自己満足であり、相手を萎縮させ、コミュニケーションを停止させる作用があります。
伝わらない説明で生じる「質問の壁」
専門用語を駆使した威圧的な「ダメ出し」は、相手に「この人たちに聞いても時間の無駄だ」「聞くのが怖い」という諦めを生じさせます。
結果として、事業部門は法務部への相談を避け、グレーな部分を隠してプロジェクトを進めるようになり、これが「法務部は怖い」という孤立化を完成させ、最終的に深刻なリスクとして顕在化します。
2. 「リスク回避至上主義」による対立の壁
事業部門は「いかに早く、利益を最大化するか」を追求し、私たちは「いかにリスクを最小化するか」を追求します。
このミッションの違いを調整できず、単なる「全面禁止」に終始すると、両者の間に決定的な対立が生まれます。
事業サイドの熱意を冷ます「ゼロリスク思考」
「リスクがあるから全面禁止」というスタンスは、ビジネスの世界にゼロリスクは存在しないという大前提を無視しています。
リスクを一つでも見つけたら頭ごなしに否定する態度は、事業部門の熱意とスピード感を一瞬で冷まし、法務部門を事業を止めたい「邪魔者」として映らせます。
「法務 対 営業」の不毛な戦い
代替案を出さずに頭ごなしに「ノー」を突きつけ、権威主義的な態度を取ることは、「法務部は偉そうだ」というイメージを生みます。
私たちは、リスクを完全に排除する神ではなく、リスクとリターンを天秤にかける事業の相棒であるべきです。
しかし、そのスタンスが見えないために、不毛な戦いが繰り返されます。
3. 「手続き」にこだわりすぎるスピードの壁
ビジネスの現場はスピードが命です。
商機は一瞬で、競合他社は待ってくれません。
しかし、法務部門のプロセスは時に煩雑で、その遅延がビジネスの成功を妨げる原因となり得ます。
ビジネスの機動力を削ぐ「形式論」
私たちは「正確性」を盾に、必要以上に形式論や手続きにこだわり、スピードを犠牲にしていないでしょうか。
形式が整っていても、ビジネスのタイミングを逸してしまえば、それは法務部門の敗北であり、社内的な評価は地の底に落ちます。
「形式は手段であり、目的ではない」という意識が欠如すると、柔軟性を失ってしまうことになりかねないのです。
決裁スピードが遅延する構造的問題
手続きのフローが不透明であったり、担当者が席を外しているだけでプロセスが完全に停止したりする非効率的な構造は、社内の不満を増幅させます。
「法務のせいで商機を逃した」という不満と、それに伴う「法務部は怖い」という不信感は、スピードの遅さから生まれる最も根深い問題の一つです。
4. 相談者の意図より「契約書」を形式的に重視する傾向

相談に来た事業部門の担当者は、まず「契約が成立するか」「プロジェクトが開始できるか」というビジネスの成功を求めています。
彼らは人間であり、感情と目的を持って動いています。
人ではなく「案件」として扱う冷たさ
私たちが相談者の顔や緊張を見ず、すぐに「持って来た契約書のこの条項が」「法的なリスクが」と、文書と法理の論理のみで冷たく対応すると、彼らは「こちらの気持ちや事業の背景を全く理解してくれない」と感じます。
この無機質な対応が、法務部を冷たい、人間味のない集団として捉えさせ、結果的に「怖い」という印象を強化します。
事業背景のヒアリング不足
事業の目標、競合との差別化ポイント、担当者が抱えるプレッシャーなど、契約書の裏にある文脈を理解しようとしない姿勢は、的確な解決策の提案を不可能にします。
背景を知らなければ、なぜその条項が必要なのか、どのリスクを許容すべきかという、本当に必要な判断を下すことができません。
5. 「ミスを許さない」という完璧主義のプレッシャー
法務の仕事は、ミスの許されない分野であるのは事実です。
しかし、その完璧主義が生む緊張感を、他部署にも無意識のうちに威圧的な態度として押し付けていないでしょうか。
心理的安全性を損なう威圧的な態度
相談者が法務に無知な部分を見せると「なぜこんなことも知らないのか」という態度を取ったり、質問自体を威圧的に否定したりすると、社内に「法務に聞くのは恥ずかしい、失敗が許されない」という心理的な壁が築かれます。
これにより、相談のハードルが異常に高くなります。
早期相談を妨げる「法務部フィルター」
この過度なプレッシャーは、担当者に「法務に聞く前に完璧にしておかなければ」というフィルターをかけさせ、手遅れになるまで相談を遅らせるという、最も危険な状況を作り出します。
完璧主義は、むしろリスクの早期発見を妨げる要因となり得ます。
6. 孤立した部署が生む「何をしているか不明」な閉鎖性
法務部門の日常業務は、経理や人事などの他のバックオフィス部門に比べて、一般社員には見えにくいものです。
この閉鎖性は、不信感の温床となります。
ブラックボックス化した業務と役割
訴訟対応、高度な契約交渉、法改正対応など、法務の重要な業務がブラックボックス化していると、「何をしているのかよく分からない、近寄りがたい部署」という閉鎖的なイメージが生まれます。
見えないからこそ、必要以上に「怖い」と想像されてしまいます。
成果が見えないことによる社内の無関心
結果として、法務部は「何か大きな問題が発生した時にだけ出てくる、恐ろしい存在」というイメージが固定化されます。
私たちの真の予防的貢献(例:年間で〇億円の損害を未然に防いだ)が見えないため、社内での関心や評価も低く留まりがちです。

「法務部は怖い」を脱ぎ捨て、真のビジネスパートナーとなるための3つの自己改革

「怖い」という言葉は、権威を示すかもしれませんが、ビジネスの成長を支援するという真の価値は生みません。
私たちは今すぐ、このイメージを「頼れる」に変えるための、具体的な自己改革に着手する必要があります。
ここでは、私たちの意識と行動を変える3つの核となる自己改革を提案します。
自己改革 1:コミュニケーションとアウトプットを「ビジネス言語」に翻訳する
抽象的な法律論を語るのをやめ、事業部門が理解し、行動に移せるビジネスの言語でコミュニケーションを取ることに集中します。
社内における法律専門家としての知識を、ビジネス戦略上のメリット・デメリットとして再構築するのです。
リスクの定量化:「金額」と「確率」で語る
「訴訟リスクがある」といった抽象的な表現ではなく、「この契約のまま進むと、最悪の場合、売上の10%にあたる損害賠償(約1,000万円)を請求される可能性が50%ある」というように、リスクを金額と確率で定量化して説明します。
これにより、事業部長は感情論ではなく、現実的な経営判断を下すことができます。
リスクはコストであることを明確に示しましょう。
判断材料の提示:「Go/Stop」ではなく「選択肢」を与える
組織の長はリスクを負う判断を下す権限を持っています。
法務部の役割は、意思決定を妨げる「Stop」ボタンを押すことではなく、判断に必要な材料(リスクと回避策)を整然と提示することです。
「選択肢A(低リスク・低リターン)」と「選択肢B(中リスク・高リターン)」を提示し、それぞれの法的・ビジネス的影響を解説します。このスタンスにより、私たちは賢明な意思決定を支援する参謀に変わります。
「Yes, but…」に変える思考回路を定着させる:代替案の自動提示
私たち法務の真の価値は、「いかにリスクを抑えながら、事業を『Go』させるか」を設計することにあります。
「このスキームは法的に問題があります」で終わりにせず、「その代わりに、A案かB案ならば、法的な懸念を90%解消した上で、80%の事業効果を得ることができます」と、必ず代替案をセットで提示します。
これにより、法務部が単なる「規制部署」ではなく「問題解決のプロ」として認識されます。
自己改革 2:オフィスの奥から出て「事業の最前線」に立ち、心理的距離を縮める
法務部が一番情報を得てはいけないタイミングは、問題が発生した後です。
最もコストの低いリスク予防は、事業の企画段階や営業の交渉初期から法務が関与することです。
事前相談の奨励:法務カフェなどカジュアルな窓口
事業部や営業担当者が「法務に相談すると面倒だ」と感じないよう、カジュアルな相談窓口(例: 隔週の法務カフェ、Q&Aセッションなど)を設けます。
形式的な相談書提出を必須とせず、雑談ベースで話を聞くことから始めましょう。
法務部門へのアクセス障壁を物理的・心理的に低く保つことが、早期相談の鍵です。
現場視点の獲得:事業部門の会議への積極参加
事業部門の企画会議や営業戦略会議にオブザーバーとして積極的に参加し、彼らが使う市場用語や業界慣習を積極的に学ぶ姿勢を示します。
これにより、相手は「この法務は自分たちのビジネスのことを理解してくれている」と感じ、「法務部は 怖い」というイメージは自然と払拭されていきます。
彼らの目標と課題を知ることが、的確な法的サポートの第一歩です。
「失敗を許容する文化」:早期相談を促す心理的安全性
法務部の役割は、過去のミスを咎めることではなく、未来のミスを防ぐことです。
相談に対して、「なぜこんな間違いをしたのか」という態度ではなく、「よく気づいてくれた、一緒に解決しよう」というスタンスで臨みます。
法務部が「失敗しても責められない、むしろ歓迎される場所」と認識されることで、担当者は安心して早期に相談に訪れ、真の心理的安全性が生まれます。
自己改革 3:法務部の役割を「推進力」として再定義し、信頼を構築する

契約書レビューを「形式的な確認作業」ではなく、「ビジネスモデルの最終チェックと付加価値創出の機会」と捉え直し、部門横断的な信頼を築くための戦略的な行動を取ります。
相談プロセスに「人間的な共感」の要素を組み込む:感情と目標への理解
法律や契約書を扱う前に、まず相談者の話にしっかりと耳を傾け、彼らが直面している市場の状況や、達成したいビジネスの目標、抱えているプレッシャーに共感を示します。
「大変でしたね」「このプロジェクトは大きなチャンスですね」といった人間的な共感が、法務部を単なる「ルールを執行する機械」から「信頼できる味方」へと変えていきます。
事業部門との定期的な「相互理解セッション」:役割と業務の可視化
法務部の業務内容、現在の優先順位、そして「なぜこの手続きが必要なのか」という理由を事業部門に定期的に伝える場を設けます。
法務の業務をブラックボックス化させず可視化することで、「何をやっているか分からない」という不信感は解消され、部門間の協調体制が生まれます。透明性が信頼を築く土台です。
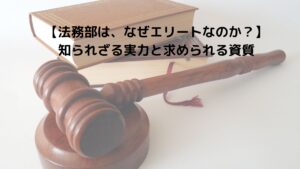
この記事の総括
私たちが目指すべきゴールと、今日から取り組むべき最終的なポイントを再確認しましょう。
この記事のポイントをまとめておきます。
- 真の強さの源泉: 法務部の真の価値は、法律知識の多さや権威性ではなく、社内からの信頼度とビジネス貢献度によって測られます。
- 価値の再定義: 法務部の役割は、リスクを止める「抑止力」(ブレーキ)ではなく、リスクを管理しながら事業を前に進める「推進力」(アクセル)であるべきです。
- イメージの転換: 「怖い」というイメージは、早期相談を遠ざけ、結果的に高コストな「火消し」作業を増やす原因になります。
- 行動の開始: 「怖い門番」という立場を脱却し、事業成長に不可欠な「頼れるビジネスパートナー」への自己改革を、今日からすぐに始めましょう。