※ 本記事には、プロモーションが含まれています。
※ 最終更新日:2025年11月28日

社内で「法務部がうざい」と感じてしまう人は、決して少なくありません。
これは、法務部門が持つ独自の役割と、他部門との関わり方に根本的なズレがあるためです。
企業活動において法務部の存在は欠かせず、法的リスクの回避、コンプライアンスの維持、契約交渉の支援など、多岐にわたる業務を担っています。
しかし現場の営業部門や企画部門から見ると、その慎重な姿勢や詳細な確認作業がスピード感や柔軟性を阻害するものと捉えられることがあります。
ときには、契約の締結直前になって法務部が差し戻しをすることで、ビジネスチャンスを逃したと感じるケースもあります。
また、法務部が現場の業務内容や市場の実情を十分に把握していない場合、机上の理論に基づいた意見ばかりを主張し、他部門との信頼関係を損ねる要因になることもあります。
その結果、「うるさい」「融通がきかない」「足を引っ張る存在」として敬遠されてしまうことがあるのです。
本記事では、こうした「うざい」と感じられる背景を多面的に分析したうえで、法務部と他部門の健全な関係構築のために取るべき具体的な対策を提示します。
企業全体のパフォーマンスと信頼性を高めるためにも、法務部のあり方を今一度見直す機会にしていただければ幸いです。
企業全体のパフォーマンスと信頼性を高めるためにも、法務部のあり方を今一度見直す機会にしていただければ幸いです。
・なぜ法務部が「うざい」と感じられてしまうのか、その根本的な原因を解説
・営業部や他部門との摩擦が生じる典型的なパターンを紹介
・法務部が抱えがちな課題やスキル不足の実態に迫る
・「法務部いらない論」が台頭する背景にある業界トレンド
・他社の先進的な法務部の取り組み事例を分析
・法務部が信頼されるために今できる具体的な対策を提案
法務部が社内で「うざい」と思われる理由
- 営業部との摩擦が絶えない理由とは?
- 契約交渉のスピード感の違い
- 「口うるさい存在」として敬遠される背景
- 細かすぎるチェック体制
- 現場感覚との乖離が「理解されない」原因に
- ルール先行型の姿勢
- 法務部に必要なスキルが不足しているケース
- 一人法務・少人数法務の限界
- 「法務部いらない論」が出てくる背景とは?
営業部との摩擦が絶えない理由とは?
営業部がスピード重視で契約を進めたい一方で、法務部はリスク管理を最優先に動くため、対立が生まれやすい構図にあります。
営業部としては、顧客との合意内容を迅速に契約書に反映させて早期にクロージングしたい意図がありますが、法務部はその契約内容に潜むリスクや不明確な表現、将来のトラブルの種となり得るポイントを見逃さないよう、慎重に確認を行います。
このように、スピードとリスク回避という相反する価値観の間で衝突が起きやすく、結果として契約の進行が滞ることになります。
さらに、営業部は顧客との関係性を重視するあまり、多少のリスクを許容してでも話をまとめたいと考える傾向にありますが、法務部は組織としてのリスクマネジメントを重視する立場から、どうしても制約や条件を付けざるを得ません。
また、両者の間に十分なコミュニケーションが取られていない場合、営業部は法務部の判断基準を理解できず、「融通が利かない」「現場を知らない」といったネガティブな印象を持つことが少なくありません。
逆に法務部側も、営業の事情や顧客の期待を知らないまま判断を下してしまうと、社内で孤立してしまう恐れがあります。
さらに、契約書におけるリスク分析や条項修正の工程がブラックボックス化している場合、営業部からすると“何を見ているのか”“なぜ時間がかかるのか”が不明瞭であり、不満や不信感を募らせる原因にもなります。
こうしたすれ違いを解消するには、相互理解と目的共有が不可欠です。
契約交渉のスピード感の違い
法務部の慎重さが、営業部から見ると“ブレーキ役”に映るのです。
営業部は、1日でも早く契約を締結し、売上に直結する成果を出すことがミッションであるため、スピード感を強く意識しています。
一方で、法務部は契約書のリスクチェックを怠るわけにはいかず、慎重に条文を精査する必要があります。
特に重要取引や新規ビジネスにおいては、少しの表現ミスや曖昧な条文が将来大きな法的トラブルに発展するリスクもあるため、法務部は可能な限り明確かつリスクのない表現を模索します。
このような法務のプロセスは正当であり必要なものですが、営業部の立場からすると「なぜそんなに時間がかかるのか」「その修正は本当に必要か?」と疑問に思う場面が多く、感情的なフラストレーションが生じがちです。
また、法務部が社内でその慎重さや遅れの背景を丁寧に説明しない場合、営業部との認識のズレがさらに拡大してしまいます。
相互理解と説明責任を果たさなければ、「法務はただのストッパーだ」というレッテルが貼られてしまう恐れがあります。
「口うるさい存在」として敬遠される背景
細かい文言修正や法律的な指摘が繰り返されることで、「面倒くさい」「うるさい」といった印象が広がってしまいます。
例えば、句読点の位置や表現の言い回し、助詞の使い方に至るまで細かく修正を求められることで、他部門からすると「些末な部分にこだわりすぎではないか」と感じることが多々あります。
また、契約書だけでなく、社内規程や取引先との通知文などに対しても法務部が口を出すことにより、関係部署の業務が滞ることがあります。
実務上は許容される範囲であるにもかかわらず、過剰な表現修正や法的見解の強調が続くと、「またか」という反応を引き出しやすくなり、結果として「うるさくてやりにくい存在」と認識されてしまうのです。
さらに、法務部が一方的に指摘を行うだけで、改善案や代替表現を提示しない場合には、ただ否定しているだけのように受け取られ、現場からの反発を招く原因にもなります。
指摘の意図や必要性を説明し、相手の業務負担を減らす工夫を行わなければ、社内での信頼や協力は得にくくなります。
このような状況を改善するには、法務部が「指摘する部署」ではなく「サポートするパートナー」としての意識を持つことが重要です。
また、社内では法務部に対し、取り扱う業務の性質などにかんがみて、ある種のエリート感を覚えてしまうことも考えられないではありません。
この点については、別記事で取り上げていますので、併せてご覧ください。
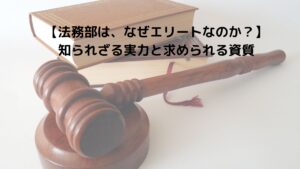
細かすぎるチェック体制
形式や言い回しへのこだわりが、時に過剰と受け取られることもあります。たとえば、同じ意味を持つ言葉でも「適切」と「妥当」のどちらを使うかといった細部にこだわりすぎるあまり、現場としては「本質とは無関係なことで時間を取られている」との不満を持つことがあります。
また、文書全体のトーンや敬語表現など、実務上の支障がない部分にも修正が入ることで、担当者にとっては重箱の隅をつつかれるような感覚に陥りがちです。
そのような指摘が繰り返されると、法務部とのやり取り自体が負担となり、「チェックに出すのが憂鬱」と感じさせる原因になります。
さらに、法務部の中には、社内基準や用語統一の観点から厳格なスタイルガイドを運用しているケースもあり、それに則らない文書は全面的な修正を求められることもあります。
もちろん、品質保持の観点では重要ですが、業務の目的や優先順位を考慮しない運用は、形式主義と受け取られかねません。
こうした状況を改善するには、法務部がチェックの「目的」を明確にし、「なぜその修正が必要なのか」を丁寧に説明する姿勢が求められます。
加えて、リスクが低い箇所については柔軟に対応するなど、現場とのバランス感覚を持った判断が信頼を築く鍵となります。
つまり、“うざいと言われる法務”は、個人の性格や能力ではなく、組織構造やコミュニケーション設計の問題で生まれるケースが多いのです。だからこそ、改善可能なポイントを整理し、戦略的に対応することが重要です。
現場感覚との乖離が「理解されない」原因に
法務部がビジネスモデルや現場の実情を十分に理解していないと、実現不可能な指摘をしてしまうことがあります。
たとえば、商品開発部門や営業現場が日々直面している市場の変化や顧客ニーズに即したスピーディーな対応を求めているにもかかわらず、法務部が理論的なリスクのみに注目し、実務とのギャップを理解しないまま指摘を行うと、現場からの信頼を損ねることになります。
また、法務部が現場を一切訪れず、会議にも顔を出さないまま文書だけで判断する場合、「現場を知らないのに口を出してくる」という批判を受けがちです。
実際には、現場の担当者が顧客との関係構築や納期との戦いのなかで苦心して作り上げた提案を、法務部が一方的に否定すると、感情的な摩擦が生じるのは当然です。
このような問題を解決するためには、法務部も現場に出向き、業務フローや意思決定の背景、業界固有の事情などを学ぶ姿勢が求められます。
現場の実情を正しく理解したうえでの法的指摘であれば、現場も納得しやすくなり、受け入れられやすくなるのです。
ルール先行型の姿勢
法律を重視するあまり、柔軟な対応に欠けることが不信感につながります。
例えば「会社としてリスクを回避すべき」という観点のみで物事を判断し、相手部門の事情や顧客の要望を一切考慮しない姿勢は、単なる杓子定規な部門として映ってしまいます。
ルールを守ることは当然重要ですが、それをどう実務に応用するかという“翻訳力”や“現実解”を提示できなければ、法務部は社内で孤立してしまいかねません。
法務部に必要なスキルが不足しているケース
法律知識だけでなく、ビジネスの理解、交渉力、コミュニケーション力が求められます。それらが欠如していると、社内連携がうまくいきません。
具体的には、法務部員が法律には詳しくても、実際のビジネスモデルや業務プロセスに関する理解が浅い場合、現場のニーズに即したアドバイスができず、結果として「使えない」と評価されることがあります。
たとえば、マーケティング戦略や営業現場の判断スピードを理解していない法務担当が、リスクだけを見て「この内容は不可です」と断言することがあります。
しかし、リスクを低減するための代替案や、一定の条件付きで実行可能な方法を示すといった対応が取れなければ、社内からの信頼は得られません。
また、契約交渉の場面では、相手企業との折衝において交渉力が不可欠です。細かな法的知識があっても、相手の立場や状況を汲み取る能力がなければ、スムーズな合意形成にはつながりません。
同様に、コミュニケーション力も重要であり、複数の部署と調整する場面では、単なる法律用語の解説にとどまらず、分かりやすくかつ共感的に説明できる力が必要とされます。
このようなスキルの欠如は、法務部が他部門との橋渡し役として機能しづらくなり、結果として「壁を作る存在」と見なされる原因になります。
現代の法務部員には、単に法律を知っているだけでなく、実務と現場に即した多角的なスキルが強く求められています。
一人法務・少人数法務の限界
法務部が少人数体制の場合、確認やレビューが追いつかず、遅延が生じやすくなります。
契約書のドラフト確認やリーガルチェックに要する時間が長くなり、現場のスケジュールに間に合わないケースも出てきます。
こうした状況が続くと、他部門からは「法務に出すと時間がかかる」「急ぎの案件には向かない」といった評価が下され、業務のボトルネックとして認識されてしまいます。
さらに、一人法務や少人数体制では、属人化のリスクも大きくなります。担当者が休暇を取ったり、退職した場合に業務が完全に停止してしまうリスクをはらんでおり、組織全体としての対応力や継続性にも不安が残ります。
知見の共有や業務プロセスの標準化が進んでいないと、担当者以外には対応できない状況が生まれ、結果として全体の生産性が落ちてしまうのです。
また、法務業務には法改正や判例動向の把握、社内啓発など継続的な取り組みが求められますが、人手が足りないとこれらの「攻めの法務」に時間を割くことができず、「守りに徹するだけの部門」になってしまいがちです。
こうした法務部は、戦略的パートナーとしての役割を果たすことが難しくなり、経営層や他部門からの期待にも応えきれなくなります。
このような問題を打開するには、業務の効率化やリーガルテックの導入、外部専門家との連携といった施策に加え、中長期的な視点での人員計画と育成体制の構築が欠かせません。
「法務部いらない論」が出てくる背景とは?
テンプレート契約の普及やリーガルテックの台頭により、法務の存在意義が見えにくくなり、軽視されるケースも増えています。
多くの企業では、契約書の標準化や業務フローの整備が進み、従来であれば法務部が担っていた契約レビュー業務が、営業部門や総務部門で完結するケースも出てきています。
また、AI契約審査ツールやクラウド型のリーガルマネジメントシステムの導入により、契約書の自動生成やリスクアラート、管理業務が劇的に効率化され、法務部の人的リソースへの依存度が下がってきている現状もあります。
このような流れの中で、「法務部がなくても業務は回るのでは?」という声が現場から上がるのも不思議ではありません。
さらに、法務部が付加価値のある提案や戦略的な判断を提供できていない場合、その存在は単なる事務的チェック機能にとどまってしまい、「コストセンター」として扱われるようになります。
これが「いらない」とまで言われる一因となっているのです。
一方で、こうしたテクノロジーの進展や業務変革の流れは、法務部の役割を縮小させるものではなく、むしろ“進化”させる機会とも言えます。単純な契約チェック業務をツールに任せることで、法務部はより高度なリスクマネジメントや戦略法務に注力する余地が広がります。
重要なのは、法務部自体が変化を受け入れ、能動的に新たな価値を提供していく姿勢を持つことです。
法務部が社内で「うざい」と思われることへの対策
- 法務部自身の業務スタイルを見直す
- 過剰なリスク回避思考からの脱却
- 他社の法務部の取組みを学ぶ
- 成功している法務部の特徴
- スキルアップと法務人材の質的向上を図る
- 外部ネットワークの活用(経営法友会など)
- 人事異動による適材適所の見直し
- 法務部門の機能再編という選択肢
- 総括|法務部が社内で「うざい」と思われる理由と対策
法務部自身の業務スタイルを見直す
法務部が現場に寄り添い、相手の目的を理解する姿勢を持つことで、信頼関係を構築しやすくなります。
単に契約書の修正やリスクの指摘をするだけではなく、「どのようにすれば実現可能か」「代替手段はあるか」といった提案型のアプローチが求められます。
たとえば、営業部や企画部が「この条件で契約をまとめたい」と提案してきた場合、従来の法務部であれば「このままではリスクが高い」と一刀両断してしまうこともありました。
しかし、これからの法務部は「このリスクを抑えるためにこういう条文を加えることで実現可能です」といった、現実的な調整力を発揮すべきです。
また、業務の進め方そのものも見直す必要があります。たとえば、各部門が法務に相談しやすい仕組み(事前相談シートや簡易チェック体制の導入など)を整備することで、業務が滞ることなくスムーズに進む環境を整えることができます。
過剰なリスク回避思考からの脱却
「絶対にリスクゼロでなければNG」という姿勢から、現実的な対応へとシフトすることが必要です。
法務部が「リスクを完全に排除しなければ承認できない」という立場を貫きすぎると、かえってビジネスチャンスを逃すことになります。
もちろん、重大な法令違反や明確な不正に対しては厳格な姿勢が求められますが、グレーゾーンや許容範囲の判断には、柔軟な対応が必要です。
リスクを“管理”するという観点を重視し、「どの程度のリスクなら受容可能か」「代替手段はあるか」を明確にすることで、現場との折衝が円滑になります。
さらに、法務部自身が定期的に自らの対応方針を振り返る機会を設け、過去に否定した案件のフィードバックを収集・分析することで、判断の妥当性や業務の改善点を見直す姿勢も重要です。
他社の法務部の取組みを学ぶ
最強法務部と称される企業の取組事例から、自社の改善点を洗い出すことが可能です。
たとえば、上場企業の中には法務部が経営戦略に深く関与し、M&Aや国際契約の現場で積極的に意見を述べる体制を築いているところもあります。
これらの企業では、法務部が単なるサポート機能ではなく、ビジネスの意思決定における重要なプレーヤーとして位置づけられています。
さらに、企業によってはAIを活用した契約審査の自動化や、他部署とのリアルタイムなやり取りを可能にする法務ポータルの導入といった、テクノロジーを活用した効率化の取り組みが進んでいます。
こうした先進的な取り組みを知ることで、自社の課題や改善点が浮き彫りになり、組織としての法務体制の再構築につながる可能性があります。
成功している法務部の特徴
ビジネスとの一体感、柔軟な判断力、他部門との高い連携力が共通点です。
加えて、経営層との密なコミュニケーション、現場の課題感に即したアドバイス、継続的なスキルアップの姿勢も成功法務部の要素といえます。
つまり、単なる「法の番人」ではなく、「価値を創造する法務部」こそが、社内外で信頼される存在となっているのです。
スキルアップと法務人材の質的向上を図る
契約実務の専門性だけでなく、論理的思考力やヒアリング力、ITリテラシーの向上も求められています。
さらに、近年ではビジネスに対する深い理解と、経営層や現場部門と円滑にコミュニケーションを取れる力がより一層重視されています。
たとえば、単に契約条項のリスクを指摘するだけでなく、そのリスクが実際の業務や取引にどのように影響するのかを具体的に説明できるスキルが不可欠です。
そのためには、各部門のビジネスモデルや業務フローを理解し、それに応じた法的対応を考える力が求められます。
また、法改正や社会情勢の変化に柔軟に対応するためには、日々の情報収集能力と、継続的な学習への取り組みが欠かせません。
eラーニングや外部セミナー、書籍などを活用し、業務に直結するスキルを随時ブラッシュアップしていくことが、法務人材の競争力を高める鍵となります。
さらに、プレゼンテーション能力やファシリテーションスキルも重要になってきています。
複雑な法的リスクや契約条件を分かりやすく伝えることで、他部門との合意形成をスムーズに進めることができ、法務部の存在価値が自然と高まっていきます。
つまり、法務部にとってのスキルアップとは、単なる法律知識の深化だけでなく、ビジネスの現場とつながる総合的なスキルの底上げであり、これが部門全体の信頼性と影響力を高める基盤となるのです。
外部ネットワークの活用(経営法友会など)
法務部員が孤立せずに他社の成功事例や課題を共有することで、視野が広がり、業務改善に活かすことができます。
特に、業界ごとに異なる商習慣や法的課題への対処方法を知ることができるのは、社内に閉じこもっていては得られない大きな価値です。
経営法友会、企業法務協会、あるいは弁護士会主催の研究会などの外部コミュニティに参加することで、同じような悩みを持つ他社の法務担当者と情報交換ができ、実践的な解決策や新しいアプローチを得る機会になります。
また、こうした場では法改正や最新の判例動向に関する講演が行われることも多く、知識のアップデートにも非常に役立ちます。
さらに、他社とのネットワークを通じて、業界横断的なベストプラクティスやトレンドを学ぶことができれば、自社の業務プロセスの見直しにもつながり、部門全体のレベルアップが期待できます。
外部との接点を持つことは、法務部が社内で孤立するのを防ぎ、戦略的な視点を養ううえでも非常に重要です。
人事異動による適材適所の見直し
法務への適性がない人が配置されている場合、異動によりメンバー構成を最適化することが効果的です。
たとえば、法律の解釈や論理的な構成を苦手とする人、リスク判断に極端に慎重すぎるあるいは逆に楽観的すぎる人材が法務部に配置されていると、他部門との連携に支障を来すだけでなく、法的な観点からの判断にも偏りが生じる可能性があります。
そのような場合には、当該職員の適性や志向を再評価し、他の部署──たとえば人事、総務、営業支援など──への異動を検討することが望ましいといえます。
また、法務部への新たな配属についても、単に「空いているから」といった消極的な理由ではなく、法務業務への関心や素養がある人材を選ぶことが、組織全体の生産性や調和に資することとなります。
さらに、定期的な適性診断やジョブローテーションを通じて、人材の最適配置を行うことも、部門の健全化には有効です。
法務部の仕事は高度な専門性が要求される一方で、他部門とのバランス感覚や柔軟性も求められるため、適材適所がなされていないと、部門内外の摩擦がより深刻化するおそれがあります。
その意味で、人事戦略と連動した法務体制の見直しは、長期的な観点からも非常に重要な施策と言えるでしょう。
法務部門の機能再編という選択肢
一部の業務を他部門に移管したり、法務をコンプライアンス部門と統合することで、より効率的な組織運営が可能になります。
たとえば、契約書の初期ドラフト作成や定型的なレビュー業務は、営業支援部門や総務部門が担うことで、法務部はより複雑かつ戦略的な案件にリソースを集中できるようになります。
また、近年ではガバナンス・リスク・コンプライアンス(GRC)を一体的に扱う組織体制が注目されており、法務部門をコンプライアンス部門や内部監査部門と統合し、「リスク管理本部」といった形に再編する企業も増えています。
このような再編により、重複していた業務の整理や情報共有の円滑化が進み、意思決定のスピードも向上する可能性があります。
さらに、法務機能を子会社やグループ全体で統一する「シェアードサービス化」や、外部の法律事務所やリーガルテック企業へのアウトソース化といった形態も有効です。
これにより、全体のコストを抑えつつ、高品質なリーガルサービスを確保することができます。
機能再編には一定のコストや体制変更が伴いますが、中長期的には組織全体の柔軟性と生産性を高め、法務部の負担軽減と専門性の発揮を両立させる選択肢となるでしょう。
法務部が社内で信頼されるために、まずできること
社内での立場や評価を大きく変えようとすると、制度改革や組織再編など時間のかかる方法を考えがちです。しかし、日々のコミュニケーションや業務姿勢の工夫だけでも、周囲の認識は大きく変わります。
たとえば、
- 法務チェックの観点を事前に共有する ・営業や企画会議に積極的に参加する
- 「ダメです」ではなく「こうすれば可能です」と返す ・相手部門のKPIや事情を理解する
といった小さな積み重ねは、長期的に大きな信頼につながります。
とはいえ、会社の文化、意思決定構造、経営層の法務理解度などは、個人の努力だけでは変えられないことがあります。そこで無理に踏ん張り続けると、心身をすり減らしてしまうこともあります。
その場合は、「自分の専門性が正当に評価される環境」に目を向けてみることも選択肢の一つです。
法務ポジションは、表に出ない“非公開求人”で採用が進むことが多く、社内にいるだけでは情報が手に入らないケースがほとんどです。
リクルートエージェントなら、法務経験者向けの求人紹介や年収相場の確認、キャリアの棚卸しを無料で相談できます。
「今すぐ転職する予定はない」という段階でも問題ありません。まずは選択肢を知ることが、将来のリスクヘッジになります。
それでも評価されないなら、環境を変えることは合理的
法務が軽視される企業文化は、担当者の能力や努力とは無関係に形成されます。
例えば、短期売上を最優先する企業、現場主導で意思決定が行われる企業、法務が経営会議に参加しない企業などでは、法務がビジネスパートナーではなく“事後処理係”になりがちです。
こうした環境に長く身を置くことは、キャリア形成の機会損失につながります。
自分の成長と市場価値を守るために、環境選択は立派な戦略です。
総括|法務部が社内で「うざい」と思われる理由と対策
「法務部がうざい」と感じられる背景には、コミュニケーションやスキルのミスマッチ、組織体制の問題が複雑に絡み合っていることがわかります。
特に、法務部と他部門との間にある役割認識のずれや情報共有不足が、摩擦や誤解の温床となっているケースは少なくありません。
これを放置すれば、法務部の孤立を深めるだけでなく、企業全体のリスク対応力や意思決定のスピードにも悪影響を及ぼします。
その一方で、法務部は適切な改革と連携によって、単なる「社内のチェック機関」から「信頼されるビジネスパートナー」へと変わる可能性を秘めています。
スキルアップや業務スタイルの見直し、外部ネットワークの活用などを通じて、より柔軟で戦略的な法務体制を構築することが重要です。
本記事では、現場からの視点と法務部の課題の両面から、「うざい」と見られてしまう原因とその対策を整理しました。
まずは自社の現状を振り返り、小さな改善から着手してみることが、変化の第一歩となるでしょう。
企業全体で法務部の役割と価値を再定義し、より風通しの良い組織運営を目指していくことが、これからの法務部に求められる姿勢です。
もし、「このまま今の会社にいていいのか?」と少しでも感じているなら、まずは市場を知るところから始めてみてください。
法務キャリアの転職支援実績が豊富な【リクルートエージェント】なら、非公開求人の紹介、年収交渉、キャリア相談まで無料で利用できます。
情報収集だけでもOKなので、未来の選択肢を確保する意味でも、早めの行動がおすすめです。
ぜひ本記事を参考に、今後の法務部のあり方や社内における役割について、前向きに再考していただければ幸いです。
・登録費用は無料!
・情報収集だけでもOK
・法務経験者向けの求人多数‼

