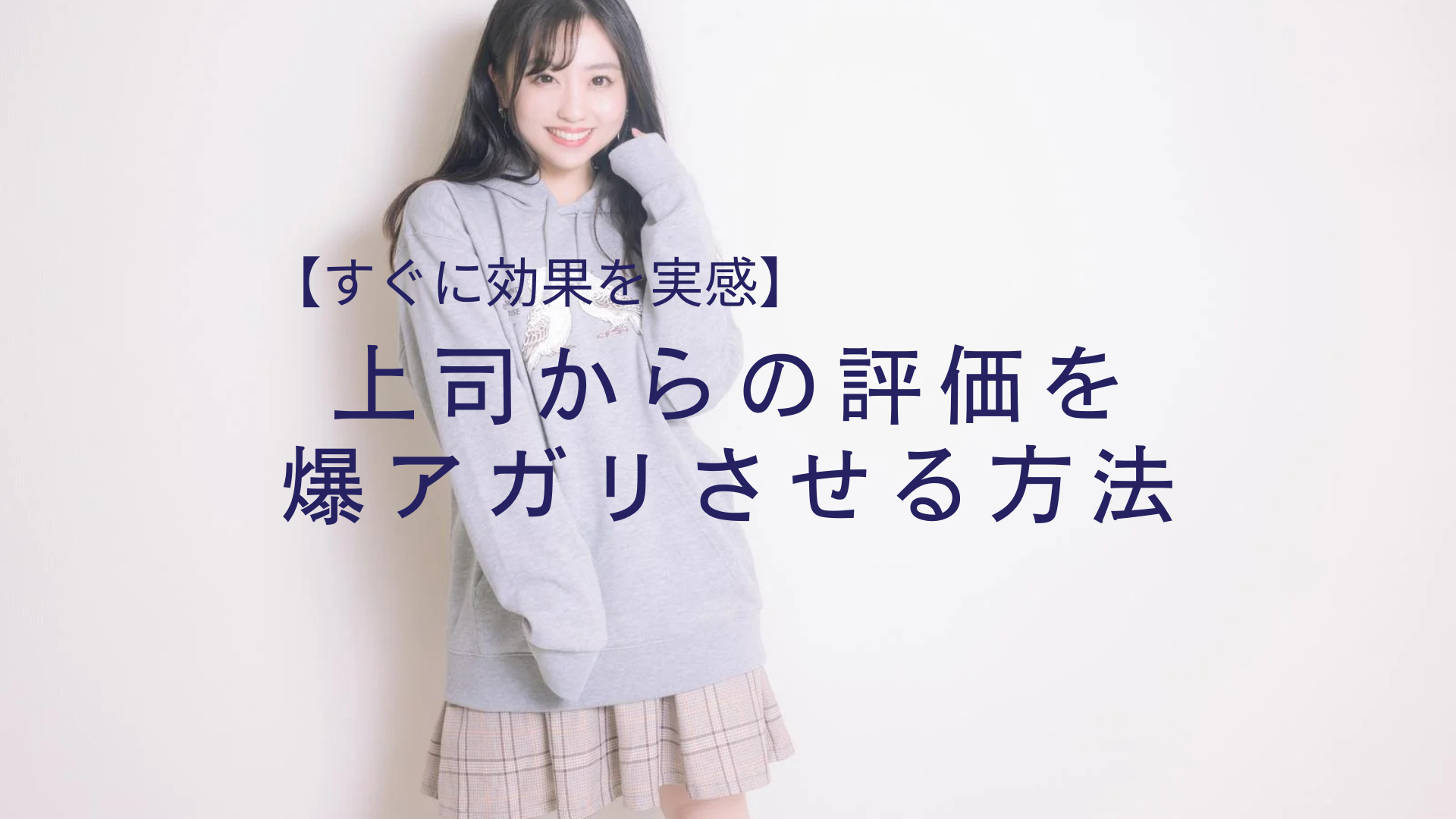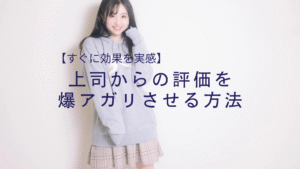はじめに
職場の上司からの評価って気になりますよね。
組織である以上、社員の業績や行動等に対する評価がなされ、それがボーナスや昇給に反映されているはずです。
時期が来ると、上司との面接が行われ、業績の振り返り等が行われます。
社員本人は自分に対する評価、すなわち自己評価を行い、上司は評価者としての評価を行います。
直属の上司は最終的な評価者とは限らず、部内での調整が入ることはもちろんありますし、他組織との調整ということも場合によってはあることでしょう。
そうした一連の過程を経て、あなたの評価が上司からフィードバックされることになります。
その間、あなたはどのような気持ちだったでしょうか。
「今回は結構頑張ったから前回より1レベル上の評価をもらえるのではないか」とか、「あのときのプレゼンがうまくいったのは自分の活躍があればこそのはずだから、今回は一番上の評価をもらって当然だろう」などと思っていたのではないでしょうか。
それで、実際のフィードバックの結果は、いかがでしたか?
上司から淡々とした口調で予想もしない低評価を告げられ、「えっ⁉」と思ったことはなかったでしょうか。
この記事では、法務部門で仕事をする社員のうち、上司から自分が希望するような評価結果を得ることができていない人を対象にして、その原因を探ると共に、これまでの評価が一転して高評価に転換するための具体的な手法を解説します。
参照ページ

| この記事で分かること |
| 自分が上司から十分な評価を得ることができていない理由が分かる上司の評価基準が分かる「聴覚タイプ」と「視覚タイプ」の意味を理解できるとともに、それぞれのタイプにより報告・説明の仕方が異なることが分かり、実行に移すことができるようになります。 |
良い評価を得ることができないのには理由がある
この記事を読んでくださっている皆さんは、会社における自分の評価に対して、必ずしも満足することができない部分があるのではないかと想像します。
その原因・理由は何だと思いますか。
上司は、部下に対する評価をする際に、機嫌が悪くて「たまたま」あなたの評価を低くつけたというわけではないのです。
まず、大前提として、上司は配下の社員全員に良い評価をつけることができるわけではありません。
評価とは、限られた数を取り合う、いわば椅子取りゲームであることを最初に理解しておく必要があります。
多くの競争相手がいる中で、どうやって生き残るかが課題になるわけです。
あなたがどうしてそのゲームに勝ち残ることができていないのか、検証していくことにしましょう。
あいさつをしていない⁉
仕事内容については、一定の評価をされているけれども、それ以前の段階、すなわち社会人として身に着けておくべき基本的な部分に課題を抱えていて、それが仕事に対する評価にマイナス効果を与えてしまっているということが考えられます。
例えば、あいさつなどです。
あなたは、会社に出勤した際、上司や同僚等に対して「おはようございます」というあいさつをしていますか?
あいさつは当たり前と思われるかもしれませんが、仕事に没頭するあまり、あいさつもせずに業務を始めているということがないでしょうか。
また、同僚や後輩などが頼んだ仕事を終えたときに「ありがとう」の一言を添えることができていますか?
仕事ができる、できないに関係なく、「ありがとう」や「申し訳ありません」といった一言は、仕事で適切な人間関係を構築していくうえで必要ですし、重要なことなのです。
もちろん、職場にはさまざまな人が集まっており、考え方も区々です。
しかし、自分の行動一つ一つが、周りにどのような影響を与えるか想像することができないとすると周囲からの信頼を得ることは難しい面が出て来ます。
そのことがいつの間にか評価に影響を与えてしまうということは、実はよく見られることなのです。
このような姿勢の場合、仕事の内容自体は良いけれども、社会人としての振舞いができていないとして、厳しい評価につながる場合があります。
つまり、あいさつをすること自体が評価において積極的な加点事由となるわけではないものの、他の社員と(例えば)同点の状態にあり、いずれか1人だけに良い評価をつけることができるという状況にある場合、上司は、日頃のあいさつが必ずしも十分ではない人に加点しようとは思わないことが多いことを気に留めておく必要があります。
心当たりのある人は、今からでも全くかまわないので、しっかりとあいさつをするようにしましょう。
あなたが想像する以上に「あの社員は良くなっているね」「成長が感じられるね」というように上司同士で話題になることが少なくないのです。そうなれば好転していくものです。
時間にルーズ⁉
あなたの評価が芳しくない、次の要因について検討してみましょう。
周囲に対する配慮と同様に、いくら仕事ができても勤務時間などにルーズであっては評価されにくいでしょう。
あなたの周囲を見回してみて、社内のミーティングの開始時間に必ずと言ってよいほど遅れて来る人はいないでしょうか。
しかも、遅れてきても悪びれることもなく、平然と着席したりしていませんか?
こういう人には大事な仕事を任せることが難しいと上司は考えることが多いのです。それは、「肝心な場面でも時間に遅れて来るのではないか」という警戒心が起きるからです。
上司は、こういう事柄について往々にして保守的というか、安全第一に考えます。
こうした社員に対して重要な仕事を任せることに対する警戒心が生じるのです。
重要な仕事を任せることができない以上、その社員の仕事は重要性の劣る案件が多く、その結果、他の社員に比して高い評価を受けにくくなるというわけです。
実際上、遅刻が多かったり昼休憩から帰ってくるのが遅かったりと、基本的なことができていないようでは、良い評価を得ることは難しいといえます。
心当たりのある人は、今からでも決して遅くありません。時間厳守を意識して仕事に臨んでみてください。上司をはじめ、周囲の人たちのあなたに対する見方が変わるのは、そう遠くないことを実感することでしょう。
好きな仕事しかしない
仕事をするうえで、好きな業務と嫌いな業務があるかもしれません。
私にも分かります。楽しい仕事もあれば、楽しくない仕事もあります。
どちらかというと、楽しくない仕事の方が多いかもしれません。特に社内外を問わず、人に謝らないといけない仕事は楽しいとは言えないですし、業務として対応するにしても辛い思いをすることも少なくないですよね。
しかし、そのこと自体は、程度の差はあるものの、誰もが同じであるということを押さえておきたいものです。
自分の好きな業務ばかりを選び、嫌いな業務を意識的に避けて、同僚や部下にさせるようでは、周囲の信頼を得ることは難しいでしょう。
上司が直接的にその姿を見ていないとしても、部下や周囲の同僚等から「〇〇さんは自分が好む仕事しかやらず、他の仕事は後輩に振っているみたいだよ」といった話がなされることも少なくないのが実情です。
同僚や部下が好きな業務であれば、助け合って仕事するのもよいでしょう。
しかし、多くの人が嫌がるような業務でも、誰かがしなければ会社はまわりません。
そのような業務を常に引き受ける必要はないかもしれませんが、引き受けた方が、仕事が円滑に進むという場合は引き受けるようにするとよいでしょう。
そうした仕事をすることを通じ、頼りになる社員であるとの印象を与えることにつながります。
ただし、その際にも恩着せがましくするのは避ける方がよいです。むしろ、「この程度の仕事は、すぐに対応できますよ」と気持ちよく引き受けたとしたら、その姿を周囲の人たちはどのように感じるか、想像してみると良いでしょう。
「これからは面倒な仕事は、すべてアイツに頼もう」などと思うでしょうか。
いいえ、そんなことは決してありません。
上司や同僚をはじめ、周囲の人たちの目には「あの社員は、嫌な仕事から逃げずに積極的に取り組んでくれますね」というように映るとともに、「今後、昇格や昇進の可能性についてもよく見てあげることにしよう」という雰囲気が漂うものなのです。
求められていないことをする
あなたは、上司や同僚から求められていることを理解して仕事しているでしょうか。
上司から見て、部下が優先順位が低い仕事や、やる必要性が劣る仕事から取り組んでいた場合、たとえその仕事を完璧にこなしたとしても、それはあなたの評価につながりにくいでしょう。
本人は「完璧にできた」「何一つミスがない」と思っているかもしれませんが、今必要ないと周囲が認識している仕事であれば、ただの自己満足になってしまいます。
上司に報告していない
あなたは上司に対して、自らが対応した業務の進捗や結果、さらには効果等について、しっかりと報告しているでしょうか。
もしかして、あなたは「部下の仕事の進捗等については、部下である自分が説明等するまでもなく、上司が自ら管理するべきものであるから、あえて部下が上司に対してあらためて説明する必要はない」などと考えていたりしませんか?
あなたが上記のように考えているのだとすれば、それは高評価にはつながらない思考方法であると言わざるを得ないでしょう。
部下が自ら対応した仕事の内容や各々の過程における進捗や課題などを上司に伝えていなければ、上司には、あなたのその案件に対する働きぶりを十分に理解することができません。
その結果、あなたの成果を十分に理解してもらうまでには至らず、評価につながらない恐れがあります。
報告・連絡・相談は仕事をするうえで重要なことです。「仕事をして終わり」というのではなく、自分が成し遂げた結果を上司に報告し、認識してもらうところまでが仕事なのです。
最後の最後までやり抜く気持ちを意識しておくと良いでしょう。
中途半端に関わっている
仕事内容によっては、ある程度の期間にわたって関わらなければならないこともありますが、ポイントのみ手伝う場合は、周囲の人に感謝されることはあっても、自身の成果としては残りにくくなります。
あなたが行った仕事であることや、チームで行っても中心人物として関わったことをアピールできると、評価につながりやすくなるでしょう。
参照ページ
優秀なのに職場から評価されない人の特徴と原因。正当に評価されるためには
上司からの評価を爆アガりさせる秘術
この記事をここまで読んでくださった方々の中には次のように思っている人がいることでしょう。
「自分は上司に対し、毎回しっかりと報告しているよ。それでも他のメンバーと比べて高い評価をしてもらえないから悩んでいるのに・・・」
つまり、あなたとしては、既に上司に対して適宜適切に業務に関する報告・連絡・相談を行ってきているにもかかわらず、ご自身の評価が自己評価を乖離している状況にあるというわけですね。
実は、そのような状況にある人は、上司について重要な視点を見落としている可能性が高いのです。
以降では、この点について解説していきます。
あなたの上司は、どのようなタイプなのかを分析する
ここでは、あなたの評価を行う上司がどのようなタイプの人なのかをハッキリとさせておく必要があります。
ここで問題にする「タイプ」とは、その上司が陽気な人とか、そうでないとか、優しいとか怒りっぽいというようなことではありません。
皆さんの上司は、皆さんから業務に関する報告等を受ける際、部下の「話を聞いて理解するタイプ」でしょうか、それとも「資料を読んで理解するタイプ」でしょうか。
実は、ここが非常に重要なことなので、詳しく説明していきます。
話を聞いて理解するタイプ(聴覚タイプ)
このタイプの上司は、業務上の案件について、部下や社内関連組織の社員からの説明を聞くことによって、その内容を理解します。
もちろん、部下等が用意した案件説明資料を読むこともするのですが、理解のための基本的な比重を「説明を聞いて理解する」ことに置いているのです。
このタイプを聴覚タイプと呼ぶことにします。
聴覚タイプの上司は、自身が意識的に「説明を聞いて理解」しようとしているわけではありません。自然とそうしているのです。いわば癖のようなものであると理解してください。
あなたの上司が聴覚タイプである場合、部下である貴方は、上司に対する報告・説明を迅速に行うことが必要です。
聴覚タイプの上司は、部下からの報告・説明を今か今かと待っていると考えてよいのです。
それにもかかわらず、貴方が「まずは上司に説明するための資料を作成しよう」としていると、上司は内心「何をモタモタしているのだ」と思ってしまい、貴方に対する評価を下げてしまう要因になってしまうでしょう。
部下としては、「上司に対して報告・説明をする以上、前もってしっかりとした資料を作成しておかないと」と考えることがあるかもしれません。
しかし、話を聞いて理解することに重点を置く、聴覚タイプ上司の場合は、資料準備を前提とする対応は良くありません。
まず、いち早く報告・説明をすることを意識して行動するべきです。
そして、報告・説明を行うにあたっては、結論を最初に言うことが非常に重要です。
個々の過程は、上司から聞かれた場合に応えれば十分です。何よりもまず最初に結論を言うことを意識しておいてください。
1回の報告・説明ですべてを終わらせるのではなく、複数回の報告・説明を行っていくことを意識すると良いでしょう。
そうすれば、聴覚タイプの上司は、「迅速に行動してくれているし、絶えず情報をアップデートしてくれている」として評価してくれることにつながります。
資料を読んで理解するタイプ(視覚タイプ)
次は、部下からの話を聞いて内容を理解するというのではなく、(部下が作成した)資料を読むことにより内容を理解するという上司もいます。
このタイプの上司を視覚タイプと呼ぶことにします。
視覚タイプの上司は、部下の説明よりも目の前にある資料の方に集中します。
上司本人がメモを取りながら部下からの話を聞くことも多いでしょう。視覚タイプの上司にとって、紙や画面上に書かれたものを読む方が情報が入りやすいと感じているのです。
よって、視覚タイプの上司に対する報告や説明の際には、上司にインプットする必要のある事項は、すべて説明資料の中に記載しておく必要があります。
また、視覚タイプの上司の場合には、資料の内容や構成、個々の文章表現に至るまで上司なりの「好み」があることが多いといえます。
配色豊かな図表やグラフを挿入しておくことも効果的ですので、日ごろから上司の好みを探っておくと良いでしょう。
部下であるあなたが視覚タイプであるならば、自分の目で見て理解しやすいように情報を示すことでしょう。
しかし、上司が聴覚タイプである場合、ひとことで話せば済む内容なのに、なぜ図表を作ったり、いちいち説明資料を新たに作成して時間を無駄にしてしまうのだろうと思われてしまう可能性があります。
もちろん、その逆もあります。
部下であるあなたが上司と同じタイプであるならば、上司との関係は良好であるはずです。
言い換えれば成功を手にしたも同然といえるでしょう。るる
上司にとって良いと思ってもらえる方法で、情報を提示することができるはずです。しかし、タイプが異なる場合には、上司に「素晴らしい」と思ってもらえる報告・説明方法を学ぶ必要があります。
視覚タイプの部下が聴覚タイプの上司に報告・説明する場合
あなたが視覚タイプで、聴覚タイプの上司に対して報告・説明をする場合、あなたの報告・説明方法に上司は辟易していて、「それで?結論は何?」とか、「どういうことなのか、口頭で説明してください」「この膨大な資料を全部読んでいる時間は、ありません」などと思っているかもしれません。
こういうタイプの上司が最も喜ぶのは、簡潔に書かれた資料が用意され、口頭で詳しく説明することです。
資料は念のためにとっておくだけなので、要点を手短にまとめたものを用意しておくと良いでしょう。
連絡メモやメールを書くことよりも、口頭で状況を用意することを意識しておくことが重要です。
肝に銘じておくべきことは、部下であるあなたにとってやりやすい方法ではなく、上司が最も良いと思う方法で報告・説明をしましょう。
そうすることによって、上司は、あなたと波長が合うし、仲良く仕事ができそうだという印象を上司に与えることができます。
そのことは上司が「自分は部下から必要な支援を受けている」と思ってもらう上でうってつけの方法なのです。
聴覚タイプの部下が視覚タイプの上司に報告・説明する場合
部下であるあなたが聴覚タイプで、視覚タイプの上司に報告・説明する場合に、上司が最も喜ぶのは図表やグラフを用いて要点を説明した資料であることを理解しておくべきです。
よって、視覚的な効果をもたらす資料を用意することを日ごろから心がけましょう。
口頭では要点だけを簡潔にまとめることです。部下であるあなたが口頭で話した内容を上司が記憶しているなどとは、微塵も期待しないことが肝要です。
報告・説明の対象となる事案等について、その概要や要点を即座に参照することができるよう、資料の中に図表やグラフを盛り込みましょう。
重要な事項を理解してもらおうと思って、上司に対し、あれこれと口頭で説明したとしても右から左に抜けて終わりになってしまうかもしれないことを心得ておいてください。
口頭説明よりもメールやSlack等によることの方が良いでしょう。
また、この上司にとって部下であるあなたがメモを取る姿に感心することも忘れないようにしてください。あなたがミーティング等でメモを取ることを苦手としている場合であっても、意識してメモを取ることになれる必要があります。
あなたがメモを取らない場合、上司は「私の話を聞いていない」と思ってしまう可能性があるからです。
こうした違いを理解しておくと、最大の効果を生む資料を準備することができるようになります。チーム内で話をしたり、説明するときにも、より効果的に行うことができるはずです。
同じチーム内で聴覚タイプの社員と視覚タイプの社員がいるはずですが、いずれのタイプの社員も感心させる方法を知っていたならば、効果的かつ魅力的に情報を提示する可能性が高まります。
自分が好む方法しか知らない場合には、聞き手の半分はつまらないはつまらない
思いをさせてしまうかもしれません。
社外の講師のセミナーにおいて、講師がホワイトボードに書いたり、セミナー資料に記載されている事項と同じことを話していることに気づいた経験はありませんか?
その講師は、両方のタイプの受講生に効果的に話を伝えようとしていたのです。
この方法は、同僚に対しても用いることができます。何かを教えても、ちっとも覚えてもらえないメンバーがいないでしょうか。
次回は紙やメール等に書いて伝えてみてください。その人は視覚タイプなのかもしれません。あるいは、紙に書いた情報を渡しても読んだためしがないような場合には、その人は聴覚タイプである可能性があります。
メンバー全員がどのタイプなのかを探っておくことで、コミュニケーションが高まることでしょう。
あなたの周囲にいる人たちは、あなたが相手にとって最も譲歩を理解したり覚えたりしやすい方法に合わせようと気を配っていることを、高く評価してくれるでしょう。
自分にとってやりやすい方法で情報を提示するか、それとも相手が好む方法を採用しているか、その差は、あくびをされてしまうか、それとも「素晴らしい」と称賛されるかの分かれ道になることを理解しておいてください。
まとめ
この記事では、現時点において上司から高い評価を受けることが十分にできていない社員を対象として、その原因を探るとともに、上司に対して報告・説明をするうえで理解しておくべき事項として、上司が聴覚タイプか視覚タイプなのかを見極め、それぞれのタイプに応じた対応法歩を説明しました。
この記事にて説明した方法は、今すぐに実行可能な方法です。
タイプ別の対応法を実行して、他の社員に差をつけるチャンスです。たとえ、他の社員から出遅れていたとしても、追いつき、追い越すことが可能になります。
ぜひ、上司から高評価を得て、昇格・昇進を勝ち取ってください。