※ 本記事には、プロモーションが含まれています。
はじめに
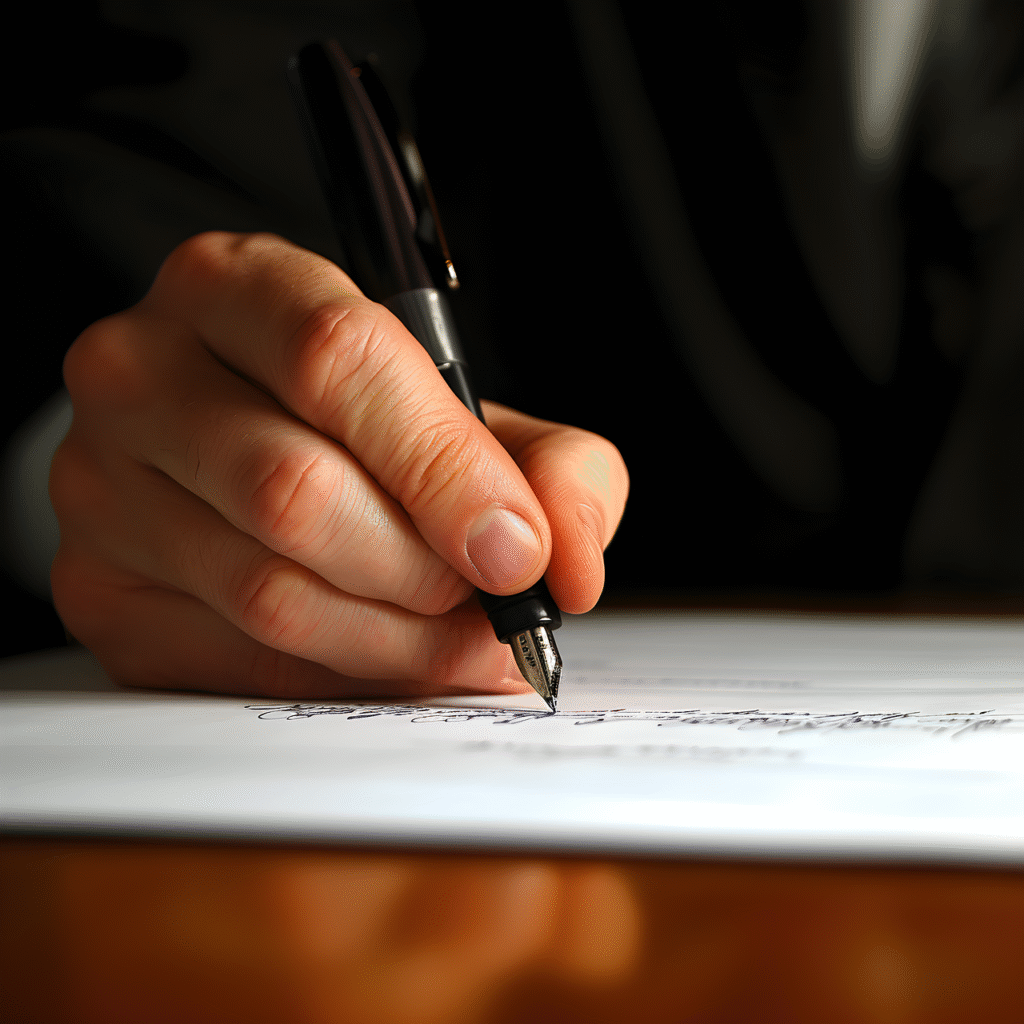
企業の法務部に所属している皆さんにとって、「行政書士試験」は単なる資格取得にとどまらず、自身の法務知識を客観的に証明し、スキルアップとキャリア形成の大きな一歩となる国家資格です。
日々の契約書作成、法的リスクの分析、社内規程の整備など、多岐にわたる実務経験は、行政書士の試験科目や業務内容との親和性が非常に高く、合格後にはその知識をダイレクトに活かすことができます。
また、行政書士は独立開業が可能な数少ない士業の一つであり、社内法務からキャリアを転じて自らの事務所を構える道も開かれています。
副業や定年後の再就職としても有望であり、ライフステージに応じた柔軟な働き方ができるのも大きな魅力です。
本記事では、行政書士とはどのような職業なのか、試験の制度や難易度、資格取得後の働き方や求人状況まで、特に法務部員の皆さんが知っておくべきポイントを中心に、わかりやすく丁寧に解説します。
この記事を通じて、自分の可能性をさらに高め、今後のキャリア形成に前向きな一歩を踏み出していただければ幸いです。
なお、比較的取得しやすい資格として個人情報保護士を挙げることもできます。
これについては別記事でご紹介していますので、併せてご覧ください。

・行政書士という資格について、その業務内容や資格試験について概説
・弁護士等の関連資格との違いの他、行政書士の年収等にも言及
・試験勉強の効果的な方法等についても説明している
行政書士とは

業務内容
行政書士は、行政機関への提出書類の作成やその手続き代理、相談業務を担う国家資格者です。
具体的には、法人設立時の定款作成や変更手続き、各種許認可申請、農地転用や自動車登録、外国人の在留資格申請など、非常に多岐にわたる業務を行います。
また、行政手続に関する専門家として、個人や企業からの依頼を受け、書類の作成にとどまらず、相談対応やコンサルティング業務も担当することがあります。
建設業、運送業、飲食業など業種ごとに必要な許認可が異なるため、業界知識や関連法令にも精通している必要があります。
さらに、相続・遺言に関する業務や、内容証明郵便の作成、契約書の作成補助など、暮らしに密接した法務支援も担っており、地域社会に根差した法務サービスを提供する存在でもあります。
行政書士は、行政と市民・企業の間をつなぐ架け橋として、法的な視点から実務的な支援を行う重要な役割を担っているのです。
行政書士法は何を定めているか
行政書士法(昭和26年法律第4号)は、行政書士の業務範囲、資格要件、登録制度、懲戒制度などを明文化して定めています。
具体的には、第1条の2において行政書士の業務として「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」が明記されており、行政手続における専門家としての立場が明確に示されています。
さらに、行政書士となるためには、国家試験に合格したうえで、日本行政書士会連合会への登録が義務付けられており、登録後は各都道府県の行政書士会に所属する必要があります。
これにより、一定のモラルと倫理観を備えた専門家集団としての組織運営が可能となっています。
また、行政書士法には懲戒処分に関する規定も設けられており、業務に関して不正行為や職業倫理違反があった場合には、戒告、業務停止、登録抹消といった処分が行われることがあります。
これにより、資格の公共性と信頼性を担保する制度的枠組みが構築されています。
このように、行政書士法は単なる制度的基盤ではなく、国民と行政の信頼関係を支える法制度の一翼を担う重要な法律であるといえるでしょう。
弁護士や司法書士との違いは?
弁護士は、民事・刑事問わず裁判業務や交渉、法律相談など、紛争処理に関する全般的な業務を行える唯一の資格です。
行政書士が扱う書類作成業務に加え、訴訟代理や調停、和解交渉といった高難度の法律事務に対応可能であり、業務範囲が広いのが特徴です。
そのため、法的紛争の現場での対応力においては、弁護士が最も強い存在といえるでしょう。
一方、司法書士は主に不動産登記、商業登記といった登記関連業務を専門としており、簡易裁判所での訴訟代理も限定的に認められています。
遺産分割協議書の作成や成年後見業務にも対応しており、相続・財産管理の現場で重要な役割を果たします。
これに対して行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続代理に特化しており、主に行政と市民・企業の橋渡し役として機能します。
許認可業務を中心に、特定の分野に特化して活動することで、深い専門性を発揮することが可能です。
つまり、弁護士・司法書士・行政書士はいずれも法律系の国家資格ですが、それぞれが担う役割と強みは明確に異なります。
法務部員が行政書士を取得することで、これまで社内で対応していた行政手続関連業務の質が格段に高まり、法務部としての付加価値がより一層高まるのです。
行政書士の年収

独立、開業する場合
開業当初は収入が不安定な場合もありますが、営業活動や業務の質を高めることで徐々に顧客を獲得し、安定した収入を築いていくことが可能です。
特に法人設立支援や、建設業許可申請、外国人ビザ業務など需要の高い分野に特化することで、顧客単価を高めることができ、年収500万〜700万円程度を目指すことができます。
また、オンラインによる業務展開やクラウド申請の活用により、全国のクライアントとつながることができる時代になっており、地方にいながら首都圏の仕事を受注するケースも増えています。
行政書士専用の業務管理システムやAIツールを導入すれば、業務効率が向上し、より多くの案件をこなすことができるようになります。
さらに、セミナー講師、行政書士法人の設立、書籍出版など、多様な収益源を組み合わせることで、収入の安定化と向上が見込めます。
ニッチな分野を専門にし、差別化されたサービスを展開できれば、独立開業から数年で年収1,000万円超を達成する行政書士も少なくありません。
司法書士と行政書士は、どちらが儲かるか
司法書士は、特に不動産登記や商業登記といった業務において1件あたりの報酬が比較的高く、安定したニーズもあることから、平均年収では行政書士より高い傾向にあります。
とくに不動産取引の多い都市部では継続的な依頼が見込めるため、安定収入を実現しやすいのが特徴です。
一方で、行政書士は業務の幅が非常に広く、専門分野によっては司法書士以上の高収入を得ることも十分に可能です。
たとえば、外国人の在留資格関連、建設業許可、補助金申請、法人設立支援といった業務に精通し、複数の法人顧客と継続的な契約を結べば、1件あたりの単価は低くても件数の多さで収益を確保できます。
また、行政手続のデジタル化が進むなか、オンライン申請代行やコンサルティングなど新たな収益モデルも生まれており、これを活かせば他士業との差別化が可能になります。
行政書士としての成功は、営業力や専門性、さらにはマーケティング戦略に大きく左右されますが、戦略的に取り組むことで年収1,000万円以上も現実的です。
士業間の連携や法人化により業務を拡大していけば、年収2,000万円を超えるケースもあります。
つまり、司法書士の方が平均的には高収入であるものの、行政書士も十分に「儲かる」職業であるといえるでしょう。
年収1,000万円は可能か
可能です。
特に法人設立、外国人関連業務、補助金申請などに特化し、法人顧客を中心に営業活動を展開していけば、年収1,000万円を超える行政書士も少なくありません。
ただし、そのためには高い専門性だけでなく、営業力や顧客対応能力、迅速かつ的確な業務処理力が求められます。
たとえば、補助金申請業務では、常に最新の制度改正や募集要項を把握し、申請者の実情に合わせた適切な書類作成ができるかどうかが鍵を握ります。
また、外国人ビザ業務などでは、法務省・入管庁の運用実態にも通じていることが求められ、信頼できる行政書士としての地位を築くことが必要です。
さらに、継続的な取引を望む法人顧客に対しては、定期的な法改正情報の提供や、経営に役立つセミナーの開催などを通じて信頼関係を構築する工夫も不可欠です。
単発の案件ではなく、リピート・紹介による受注を増やすことで、安定的かつ高収益な事業運営が可能となります。
また、SNSやホームページ、動画などを活用したマーケティングを展開し、自身の専門性や実績を広く発信していくことも、今や行政書士として生計を立てていくうえで重要な要素となっています。
これらの努力と工夫を積み重ねた結果として、年収1,000万円を超える行政書士が多数存在しているのです。
女性の行政書士の活躍可能性
家庭と両立しながら働ける点が行政書士の魅力の一つです。
時間や場所にとらわれず、自分のライフスタイルに合わせた働き方ができるため、特に子育て中の女性や、出産・育児を機にキャリアを一時中断した方々にとって、再出発の選択肢として非常に有望です。
実際に、自宅で開業し、地元の小規模事業者や個人からの依頼に対応している女性行政書士も数多く存在します。
また、女性ならではの共感力や丁寧なコミュニケーションスキルは、依頼者からの信頼を得るうえで大きな強みとなります。
特に相続や遺言、外国人支援業務など、きめ細やかな対応が求められる分野では、その強みが顕著に発揮されます。
さらに、女性士業としての視点を活かし、SNSやブログを通じて情報発信を行うことで、女性顧客の支持を得やすくなる傾向も見られます。
最近では女性行政書士のネットワークや勉強会も活発化しており、情報交換や相互支援を通じてスキルアップや業務拡大を図ることも可能です。
このように、行政書士という職業は、性別を問わず平等に活躍のチャンスがある国家資格であり、女性にとっても大きな可能性を秘めたキャリア選択のひとつであるといえるでしょう。
行政書士試験
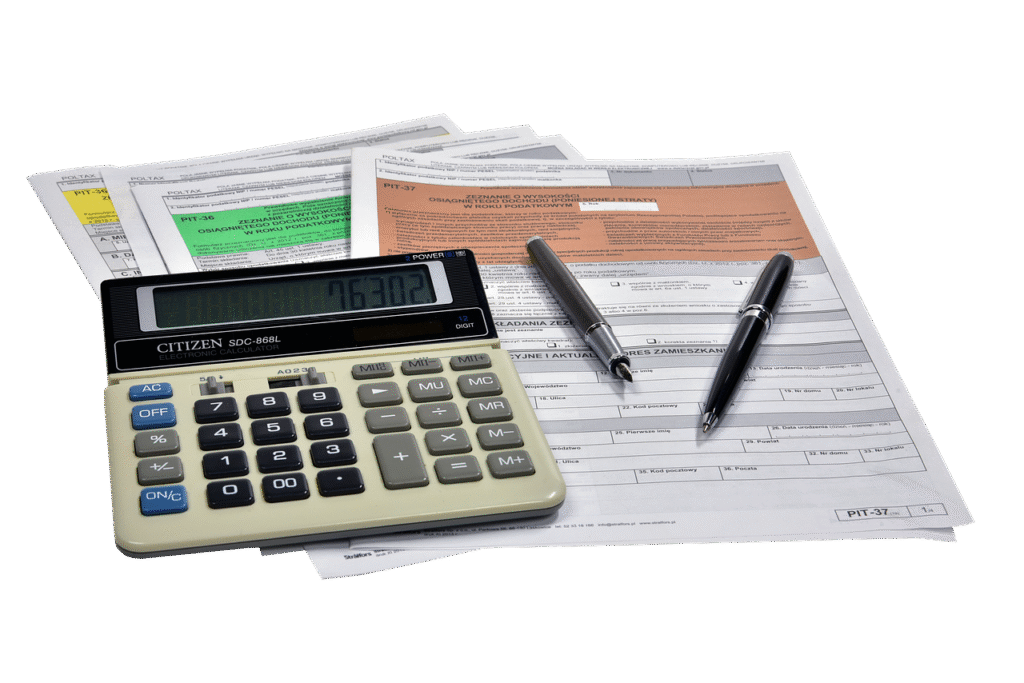
受験資格
年齢・学歴・国籍不問で、誰でも受験可能です。
これは、多くの国家資格と比較しても非常に門戸が広く開かれており、社会人、主婦、学生など、幅広い層が受験の対象となります。
法務部員としての実務経験を有する方にとっては、すでに業務で扱っている契約法や行政法に関する知識が試験内容と重なるため、大きなアドバンテージとなります。
また、法律初学者であっても、市販テキストや通信講座、スマートフォン対応の学習アプリなどが充実しており、独学でも十分に対策が可能です。
さらに、受験資格に実務経験や学歴制限が一切ないため、キャリアチェンジや副業として行政書士を目指すことも現実的です。
法律に関心があり、手に職をつけたいという強い動機があれば、誰でも挑戦できるのがこの資格の大きな魅力の一つです。
試験日程
例年、11月の第2日曜日に全国で実施されます。申込期間は7月頃です。
参照ページ
難易度(合格率)
合格率は概ね10%前後で推移しており、国家資格の中でも中堅クラスの難易度です。
これは受験者全体のうち9割が不合格になるということであり、試験に対してしっかりとした学習戦略を立てることが求められます。
特に、試験はマークシート形式の択一式問題に加え、文章力と法的思考力が問われる記述式問題が含まれており、これらの対策が合格のカギを握ります。
知識の暗記だけではなく、条文の趣旨や実務への応用力も問われるため、深い理解と実践的なトレーニングが不可欠です。
また、合格基準は「法令等科目:満点の50%以上かつ記述式で一定点数以上」「一般知識等:40%以上」など細かく設定されており、特定の分野だけに集中するのではなく、バランスよく得点することも求められます。
このように、合格率10%前後という数字以上に、試験の構造や要求水準を理解し、それに合った準備をしないと、合格は難しい試験といえるでしょう。
宅建や社労士と比較した難易度は?
宅建(宅地建物取引士)と比べると、行政書士試験の方が科目数や法令知識の深さの点で難易度は高めとされています。
宅建試験は不動産に特化した内容であり、出題範囲も比較的限定的であるのに対し、行政書士試験は憲法・行政法・民法・商法など幅広い法律知識が求められます。
また、社労士(社会保険労務士)試験と比較すると、試験形式や試験範囲の広さにおいて類似点はありますが、行政書士は記述式問題が出題される点で、単なる暗記だけでは太刀打ちできず、論理的思考力や文章表現力も問われる点が特徴です。
特に行政法の分野においては詳細な知識が必要で、法律条文の趣旨を理解したうえで運用に応じた応用力も求められます。
そのため、宅建に合格した方でも行政書士試験に挑戦する際は、試験のボリュームと形式の違いに注意し、より体系的な学習計画を立てることが必要です。
一方で、社労士に合格している方は法令科目の基礎がある程度身についているため、行政書士試験においても有利に働くことがあります。
総じて、行政書士試験は宅建より難しく、社労士と同等かやや上回る難易度といえるでしょう。
独学でも合格できるか
独学でも合格は十分に可能ですが、学習効率やモチベーションの維持という観点から、通信講座やオンライン学習ツールの併用を検討することが望ましいです。
行政書士試験は、法令科目・一般知識・記述式問題など出題範囲が広く、独学ではどうしても自己流になりがちで、重要ポイントを見逃してしまうリスクがあります。
特に法務経験者であれば、行政法や民法といった主要科目において一定の理解があるため、過去問演習を軸にしたアウトプット中心の学習で高得点を狙うことが可能です。
一方で、初学者や法律のバックグラウンドがない方にとっては、インプットの質が合否を左右するため、体系的に整理された教材や講義が強い味方になります。
また、独学者が陥りがちな問題として、勉強時間の確保とペース管理があります。
仕事や家庭と両立しながら学習を継続するには、スケジュール管理や習慣化の工夫が不可欠です。
最近ではスマホで学べるアプリやYouTube講義も充実しており、通勤時間やスキマ時間の活用が独学合格のカギとなります。
結論として、独学でも行政書士試験に合格することは十分に現実的ですが、自分の生活スタイルや学習習慣に応じて、通信講座や学習支援ツールを活用することで、より確実に、効率よく合格を目指すことができるでしょう。
オフィスでの業務を終えた後に資格取得に向けて勉強をしようとしても、なかなか思いどおりに進めることができないことが多いですよね。
いたずらに日数ばかりが経過してしまい、焦りにつながり、十分に知識が定着せず、過去問等の問題演習もうまくいかないということが良く起こります。
そうした事態を避けるためには、受験指導機関によるカリキュラム化された講座を利用するというのも良い方法です。
資格取得に直結した講義やテキストが完備されていることも重要ですが、ペースメーカーとしての役割は非常に重要です。
ペースメーカーとしての役割とは、半ば強制的に勉強をするよう仕向けてくれるということです。
「いきなり難関資格に挑戦するのは不安がある」
そんな皆さんにおかれましては、LEC東京リーガルマインドの講座を受講してみてはいかがでしょうか。
LECは司法試験をはじめ、法律関係の難関資格について高い合格実績を誇る受験指導機関です。
このため、行政書士試験合格に向けて短期間で効率的な学習法を教授してくれます。
ご興味があれば資料請求してみると良いでしょう。
合格までに要する勉強時間や期間は?
目安としては600〜800時間程度とされていますが、学習スタイルや法律知識の有無により個人差があります。
法学部出身者や実務経験がある方は比較的早期に基礎を固められるため、半年以内の短期合格も可能です。
一方、法律初学者の場合は、法律用語や論理構成に慣れるまで時間がかかるため、1年〜1年半程度の計画でじっくり取り組むことが推奨されます。
特に民法や行政法は出題数も多く、理解に時間がかかる分野ですので、計画的に復習と演習を繰り返すことが大切です。
また、一般知識対策や記述式問題の対策も忘れてはならず、これらに割く時間を含めると、トータルでは900時間前後かかるケースもあります。
社会人や主婦など、限られた時間の中で勉強する場合は、平日1〜2時間、休日3〜4時間のペースを維持することで、半年〜1年の学習期間で合格ラインに到達することが可能です。
大切なのは、単なる学習時間の長さではなく、どれだけ集中して効率的に学習できるかです。
早い段階でのスケジュール作成と定期的な進捗確認が、合格への近道となるでしょう。
大学で法学部出身者でないと合格は困難か?
法学部出身でなくても、行政書士試験に合格することは十分に可能です。
実際、合格者の中には経済学部、文学部、教育学部、さらには理系学部出身者も多く見られます。
法律の学習が初めての方でも、市販のテキストや通信講座を活用することで体系的に基礎から学ぶことができます。
特に、初学者向けに作られた教材や講義では、法律用語の定義から丁寧に解説されており、講師による実務的な補足や図解を交えた講義も多く、法律を専門的に学んだことがない方でも理解しやすい工夫が施されています。
さらに、繰り返し学習により知識を定着させるための問題演習や復習機能も充実しており、継続的な努力さえあれば誰でも合格に近づける環境が整っています。
また、法学部出身であっても、行政書士試験特有の記述式問題や一般知識対策には個別の対策が必要であり、単なる法学の知識だけでは対応しきれない部分もあります。
そのため、学部出身にかかわらず、試験対策としての「実践的な勉強」が何よりも重要です。
結論として、法学部出身であるかどうかは合否に直接的な影響を与えるものではなく、必要なのは理解力と継続力、そして合格まで学び続ける意思です。
主婦が独学で合格する可能性は?
十分に可能です。家庭や育児と両立しながら勉強を進めている主婦の方は多く、行政書士試験は時間や場所に縛られず学習が可能な点で非常に適しています。
スキマ時間を活用した学習計画を立てることで、日々の家事や子育ての合間でも無理なく勉強を進められます。
最近では、スマホやタブレットで手軽に学べるオンライン講座や過去問アプリも多数登場しており、隙間時間の活用をさらに効率的にしています。
また、家事をしながら耳で聞ける音声講座や、動画での解説講義なども充実しており、インプットとアウトプットの両方を日常生活の中で組み込むことが可能です。
さらに、主婦ならではの継続力や計画性は、試験勉強において非常に有利に働きます。
日々のスケジュール管理や目標設定が得意な方は、独学でも自律的に勉強を進めやすく、合格に向けて着実にステップを踏むことができるでしょう。
SNSやブログで情報共有を行う「ママ行政書士」コミュニティも存在し、仲間と励まし合いながら勉強を続けることもできます。
このように、主婦の方でも行政書士試験に挑戦し、独学で合格を目指すことは十分に現実的です。
効果的な勉強方法
行政書士試験の効果的な勉強方法として、過去問中心のアウトプット学習と記述式対策の早期着手が非常に重要です。
まずは、インプット学習として基本書や講義動画を利用し、法令ごとの全体像をつかむことから始めましょう。
その際、条文の趣旨や判例との関係も合わせて確認すると、理解が深まります。
次に、アウトプット学習では過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や問われやすい論点が見えてきます。
出題形式に慣れ、どのような問われ方をされるのかを把握することが、得点力アップに直結します。
間違えた問題にはチェックを入れ、復習の際に重点的に見直すと効果的です。
さらに、記述式問題の対策は早めに取り組むのがポイントです。
記述では正確な法的知識と論理的な文章構成が求められ、実践的な訓練が必要不可欠です。
模範解答を真似るだけでなく、自分なりの表現で解答を組み立てる訓練を行いましょう。
また、学習サイクルとしては「インプット→問題演習→復習→再確認」というループを意識して繰り返すことで、知識が定着しやすくなります。
自分の弱点を分析し、時間配分や勉強スタイルを工夫することで、限られた時間の中でも着実に実力を伸ばすことができます。
加えて、勉強の進捗状況を記録したり、SNSで学習記録を公開したりすることで、モチベーションの維持にもつながります。
計画的かつ戦略的な学習姿勢が、行政書士試験合格への鍵となるのです。
おすすめのテキストは?
「うかる!行政書士」シリーズ(伊藤塾監修)や、「合格革命シリーズ」などが評価されています。
いずれも最新の法改正に対応しており、試験に必要な基本的知識から応用力を養う内容がバランスよく構成されています。
「うかる!行政書士」シリーズは、図解やイラストを多用し、法律初学者にも分かりやすい丁寧な解説が特徴で、インプット重視の学習に適しています。
特に、行政法・民法などの主要科目については各章ごとに確認テストが設けられており、理解度を確認しながら読み進めることができます。
一方、「合格革命シリーズ」は、出題頻度に応じた重要度ランクや、本試験を想定した問題演習が豊富で、アウトプット中心の学習スタイルに向いています。過去問の出題傾向や試験委員の趣向なども分析されており、受験生にとって効率的な学習が可能です。
この他にも「みんなが欲しかった!行政書士の教科書(TAC出版)」や「伊藤塾試験対策問題集」なども定評があり、目的や学習スタイルに応じて使い分けることをおすすめします。
重要なのは、自分の理解しやすい書き方のテキストを選ぶことです。
可能であれば書店で中身を確認した上で選定し、長期間付き合える一冊を見つけると良いでしょう。
おすすめの過去問アプリや講座は?/ユーキャン
ユーキャンの行政書士講座は映像とテキストのバランスがよく、初心者にもわかりやすい構成です。
学習の進捗管理や弱点分析機能が搭載されており、初学者でも安心して取り組めるのが魅力です。
映像講義は短時間で要点を押さえており、繰り返し視聴することで理解を深められる設計になっています。
テキストはフルカラーで図解が多く、法律知識に慣れていない方でも直感的に学習できる工夫がなされています。
また、質問対応機能も充実しており、学習中に出てきた疑問を講師にオンラインで質問できるため、独学でありながらもサポート体制が整っています。
添削課題も定期的に提出することで実践力を養うことができ、記述式対策としても非常に有効です。
アプリでは「行政書士 過去問道場」が人気で、スマートフォンで気軽に過去問演習が可能です。
年度別、科目別、出題頻度順など、さまざまな条件で絞り込めるため、自分の理解度に応じて効率的に学習ができます。
通勤時間や家事の合間などのスキマ時間を活用したい方には最適なツールであり、独学者にも高く支持されています。
合格後の求人状況
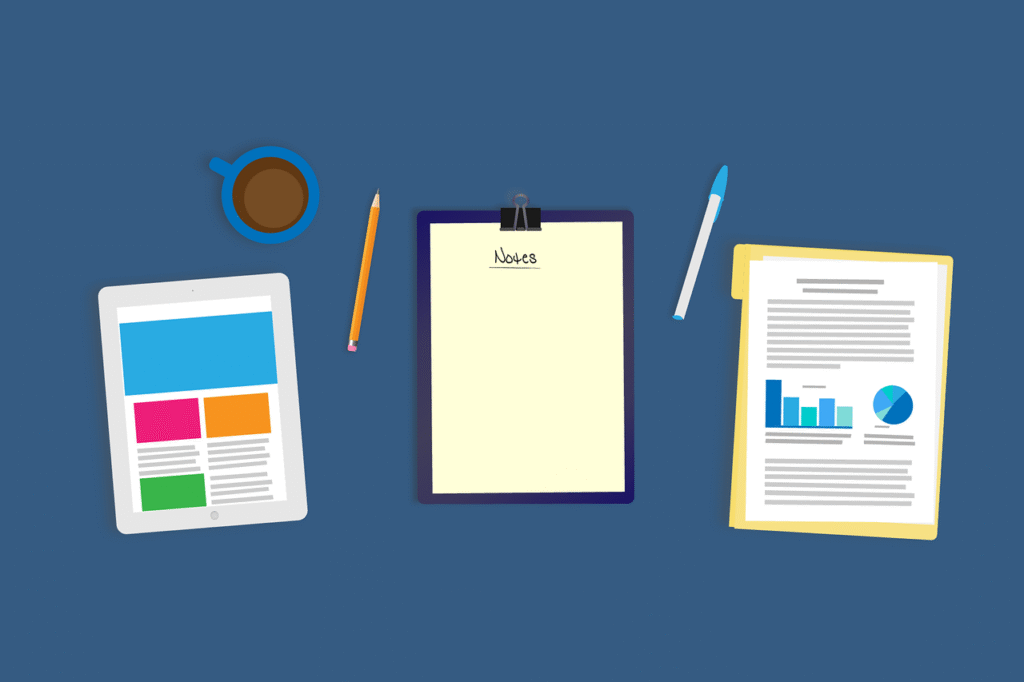
地域別求人状況(東京、神奈川、愛知、大阪、福岡)
都市部では行政書士法人や士業連携事務所での求人が豊富にあります。
特に東京・大阪は求人件数も多く、行政書士の需要が高まっています。
これらの都市では、企業法務や国際業務、外国人対応など、専門性の高い分野へのニーズが顕著であり、即戦力となる行政書士が求められています。
東京では大手の行政書士法人や、弁護士・税理士との合同事務所が多く、幅広い案件を扱う環境に身を置くことができ、実務経験を積みながらスキルを磨くには最適な地域です。
神奈川・愛知・大阪でも、建設業や運送業など地域産業と連携した業務が多く、安定した依頼が見込める環境が整っています。
福岡においても、外国人労働者の増加やスタートアップ支援の高まりから行政書士の役割が注目されており、在留資格申請業務や法人設立支援の求人が増加傾向にあります。
地方都市でも、行政書士会の支援制度や創業支援事業により、新規開業者や未経験者でも活動しやすい基盤が整ってきています。
今後はDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や電子申請の普及により、リモート業務や副業としての行政書士活動も可能性が広がっており、居住地に縛られない新しい働き方も期待されています。
未経験者の求人状況(30代、40代、50代)
年齢に関係なく、未経験からの就職・転職も十分に可能です。
行政書士は幅広い年代に門戸が開かれている国家資格であり、30代・40代・50代のいわゆるミドル層でも、資格取得後に新たなキャリアを築くことが可能です。
特に近年では、人生100年時代を見据えた「第二のキャリア」として行政書士を目指す人が増加しており、社会経験豊富な中高年層に対するニーズも高まりを見せています。
実務未経験者歓迎の求人も多く、行政書士法人や中小規模の事務所では、入社後に基礎から業務を習得できる研修制度を設けているケースも増加しています。
なかには、定年退職後に行政書士資格を活かして再就職を果たした例や、家業を手伝いながら独立を目指す40代・50代のケースも見られます。
また、年齢を重ねた人ならではの信頼感や対応力、社会的信用は、行政書士業務において強みとなる要素です。
特に、企業顧客を対象としたコンサルティング業務や、高齢者向けの相続・遺言支援などでは、年齢と経験がかえってプラスに働きます。
このように、30代から50代の方が未経験で行政書士に転身することは、現代では決して珍しくありません。
志さえあれば、年齢に関係なく活躍できる職業であると言えるでしょう。
まとめ
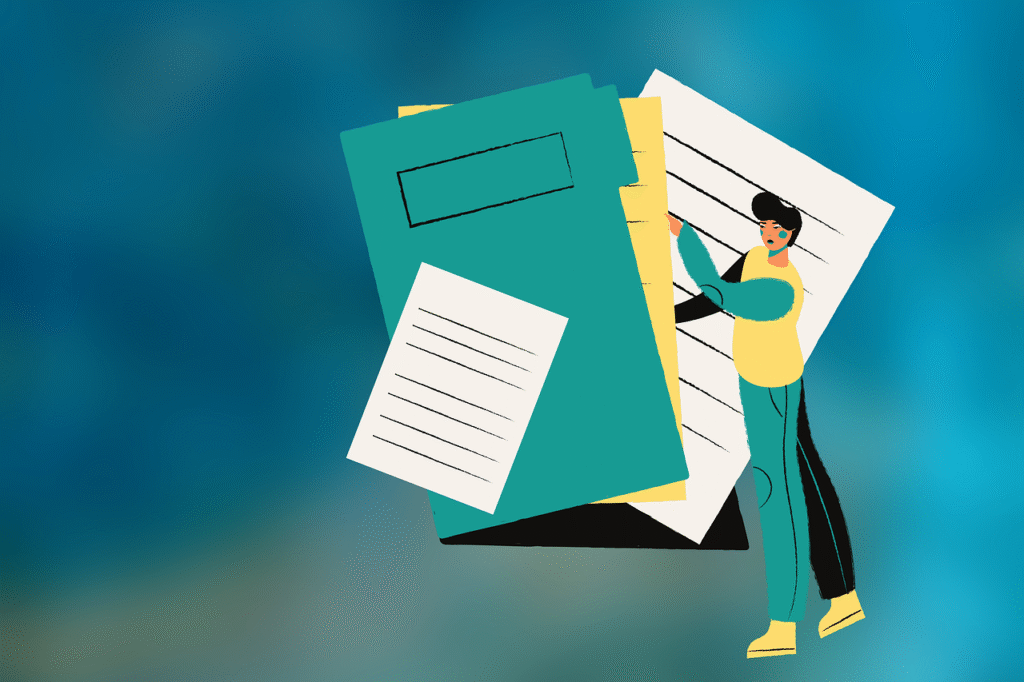
行政書士は、法務部員の実務経験を活かしてさらなる飛躍が目指せる国家資格です。
契約書作成やコンプライアンス対応など、企業内での実務経験を活かしてスムーズに試験内容に取り組めることから、現役の法務担当者にとって極めて親和性の高い資格といえます。
試験自体は決して簡単ではなく、継続的な学習と戦略的な対策が求められますが、合格することで得られる専門知識と信用は非常に大きな価値を持ちます。
行政書士としての資格を取得すれば、副業としての活動や将来的な独立開業といった新たなキャリアの可能性も開かれ、企業に勤めながらでも着実にキャリアアップが図れる手段となるでしょう。
また、行政書士は地域社会に根差して活躍する機会も多く、幅広い年代や背景を持つ人々と関わりながら社会貢献ができるやりがいある仕事です。
性別や年齢を問わず、多くの人が挑戦し成果を上げていることからも、その懐の広さがうかがえます。
将来の選択肢を広げ、自分自身のスキルと可能性をさらに高めたいと考える方にとって、行政書士試験はまさに挑戦する価値のある国家資格です。
今この瞬間こそ、あなたの新しい一歩を踏み出す絶好のタイミングなのです。

