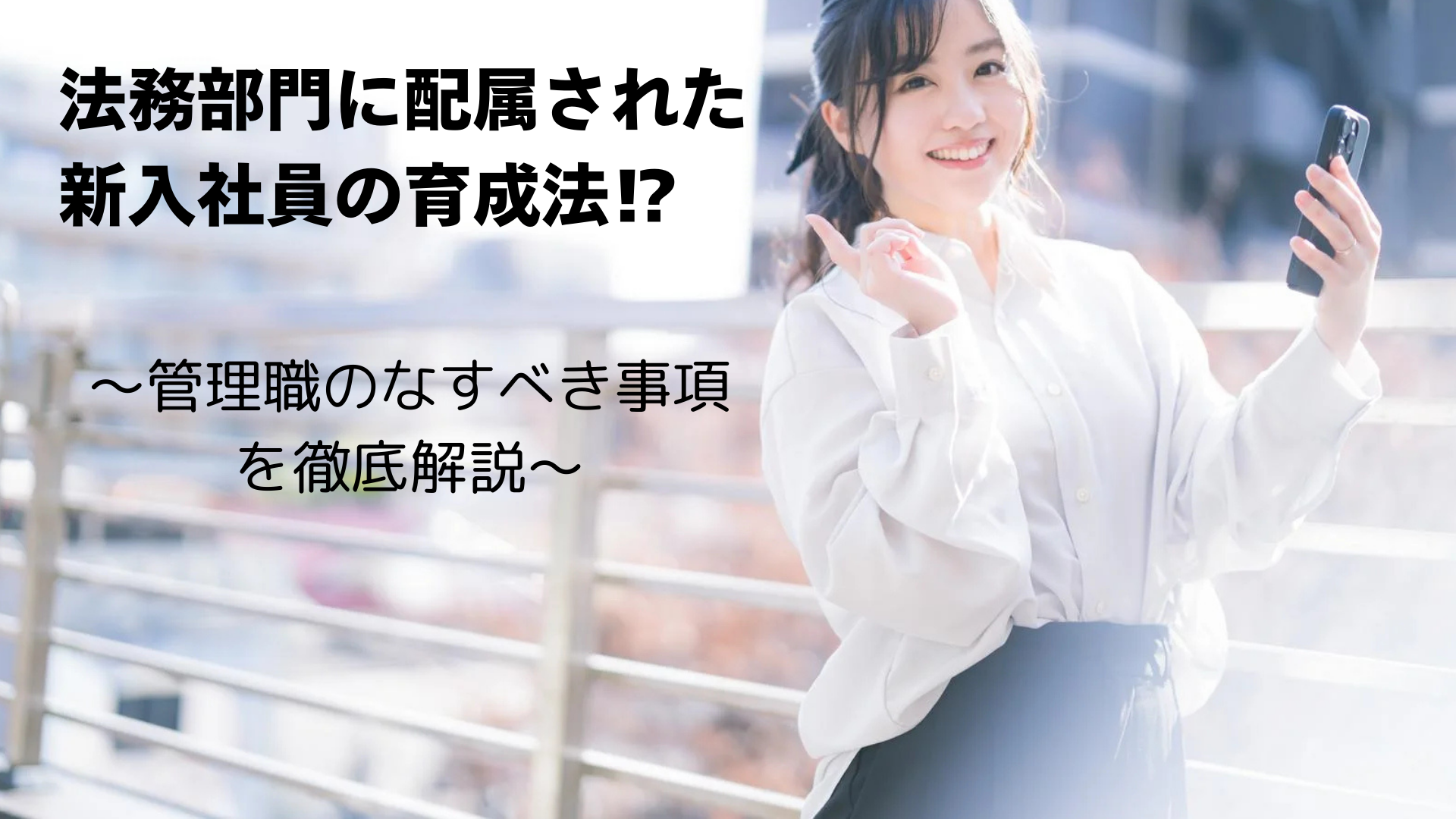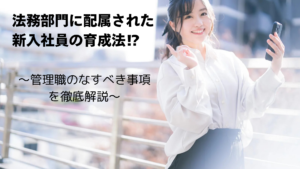はじめに
近年、新卒社員についても、いわゆるスペシャリスト採用として特定の組織に配属することを意識した採用をする会社が少なくありません。
以前の日本企業は、入社して以降、3年~5年程度を1つの区切りとして様々な部署での仕事を経験していく、いわばゼネラリストが通常の姿でした。
多くの部署、時には出向を経験しつつ、社内外の人脈を形成していくことを通じて、業務の幅を広げていったのです。
現在もその形態をとる企業は多くあります。
しかし、その一方で、そうした育成法では、スペシャリストは育ちにくい環境にあることも事実でした。
せっかく仕事を身に着けて一本立ちし、さらに成長し、活躍してもらおうとした矢先に、畑違いの部署に異動するということも珍しいことではありませんでした。
異動元および異動先の部署では、新たにゼロから人材を育成していく必要が生じてしまうため、効率的ではありませんし、社員本人としても自分が希望する人事異動であるのであればともかく、現在の仕事を継続し、さらに発展させたいと希望したいたにもかかわらず、別方面の業務に従事するとなると、モチベーションの維持・向上という点でも課題を含むものでした。
特に法務スタッフの場合、会社の経営に重要な影響を与える事項を取り扱うことが多いことから、社員の育成には相応の時間を要することは避けられません。
営業部門等の業務を経験してから法務部門に異動してくる社員の存在も組織としては頼もしいことは勿論ですが、法務のように会社に入る以前の学生時代からの蓄積がある程度重要性を帯びる職種の場合には、その蓄積が錆びる前に法務の世界に入ることの方が伸びしろを活かすことができるように思われるのです。
取り扱う法令の範囲も広いですし、制度改正にも対処していくことが当然必要になります。
このため、法務人材をスペシャリスト採用に取り入れ、新卒の採用の段階から社員本人の希望を考慮しつつ、法務配属する適正アリと認められる人材を確保していく会社が見られるようになっています。
社内的にはスペシャリスト採用として新卒社員の採用をしていくのは、企業によりその手続過程は区々であるとしても、相応の高さのハードルをクリアする必要があります。
「どうして法務が?」とか「それだったらウチの部署もそうするべきでは?」といった疑問ないし批判が出てくるからです。
このため、人事部門もいわば特別扱いをする必要性について説明を求めてくる場合が多く、人事部門との交渉役は気苦労が絶えないのです。
そのような苦労を経て、ようやく法務部門に新入社員が配属されることになったとします。
せっかく獲得するに至った貴重な人材であり、その指導に責任を負う立場の管理職には、かなりのプレッシャーがかかるでしょう。
その管理職がすでに法務人材の育成に経験があり、その方法を熟知している人であればともかく、経験値がそれほど高くない場合には、「どうするのが一番良いのだろうか。失敗するわけにはいかないし」と悩む場面があるかもしれません。
そこで、この記事では、法務部門に新入社員が配属された場合に、その新入社員の指導・育成を行うにあたっての留意点を解説していきます。
| この記事で分かること |
| 新入社員の指導、教育の仕方が分かる特に法務部門に配属された新入社員を育てる場合に気を付けておくべき事項を知ることができる上司に新人教育の成果を認めてもらう効果的な戦略を理解できる |
新入社員の指導・教育に関する一般論
法務部門に配属された新入社員の指導教育の方法という、各論に入る前に、いまどきの新入社員はどのような特徴があるのか、ということと、新入社員教育に関する一般的な手法を概観しておくことにします。
その方が、法務部門の新入社員の指導法の特殊性を理解しやすいからです。
「イマドキの新入社員」の特徴
いわゆる「Z世代」と称される新入社員には、以下のような特徴を持つ人が多いので、これを概観していくことにします。
ひとりで抱え込む
近年の新入社員に非常に多い特徴が、上司や先輩への遠慮、評価への不安から、「報連相」報告・連絡・相談をためらい、自分一人で問題を抱え込んでしまう傾向です。
その背景には上司・先輩のネガティブな反応に対する恐れがあるのです。
- 「こんな簡単なことを質問したら、怒られるんじゃないか?」
- 「こんな相談をしたら、仕事ができないやつだと思われるんじゃないか?」
- 「質問ばかりしていたら、評価が下がってしまうのでは?」
新入社員が報連相をしなければ、勝手な判断によってミスを繰り返したり、解決できない問題が放置されたりして仕事が進まなくなってしまいます。
また、新人の成長機会も失われます。
指示待ちで主体性が低い
指示待ちとは、1つのタスクが終わるたびに、「次は何をしたら良いでしょうか?」と尋ねてくることです。
新入社員の場合は、自分で次の業務を判断する知識などがないためにやむを得ない部分もありますが、報連相と同様に上司・先輩に過度に遠慮してしまう、また、正解がわからないと動けないといった傾向・特徴もあります。
間違いや失敗を過度に恐れる
悪い意味で、“万能感”が高いまま社会人になってしまった状態です。
万能感が高すぎた場合、新たな仕事・挑戦をするときに「絶対に間違えられない」という自らのプレッシャーに押しつぶされてしまいます。
また、逆に失敗するかもしれない仕事から遠ざかる傾向ともなります。誤った万能感の高さは、間違いを起こさせない学校教育などによる影響が考えられます。
万能感以外にも、前述した上司や先輩からのネガティブ評価を恐れる、正解があることへの慣れといったものも間違いや失敗を恐れる背景になっています。
また、子供のころからSNSに慣れ親しんでいる今の新人は、有名人や企業が何か起こした際の炎上や叩かれ方も目の当たりにしてきています。
こうした経験も失敗を過度に怖がる要因となっているでしょう。
明確な「正解」を求める
いまどき新入社員は、生まれたときからインターネットやSNSがあったZ世代です。
昔から言われる学校教育や学歴主義の弊害という部分もありますし、子どもの頃からインターネット検索に慣れていると、「検索すれば簡単に正解が見つかる」と思い込むようになってしまいます。
しかし、ビジネスにおける意思決定は正解が曖昧であることが多くあります。
正解を求める、正解がないと動けないという特徴は、ビジネスにおいては妨げとなることも多いでしょう。
承認欲求が強い
SNS文化のなかで育った新入社員は、自分が何か投稿するたびに「いいね!」で承認されることに慣れています。
そのため、承認されることが当たり前であり、承認欲求の強い新入社員は、上司や先輩に承認を強く求めます。
一方で、承認されなければ不満になり、モチベーションやエンゲージメントが低下してしまう傾向にあります。
新入社員のうちは、仕事を完全に覚えていないので、間違いや失敗は起こして当然ともいえます。
また、新入社員に限らず、人は間違いや失敗を通して成長していくものです。
その意味で、間違いや失敗を恐れすぎる姿勢は成長の妨げとなるものです。
参照ページ
新入社員の特徴に合った指導方法を解説!成長を促すポイントとは?
新入社員に対する指導・育成で最初にするべきこと
この記事を読んでくださっている法務部門で仕事をする先輩社員や管理職の皆さんに振り返っていただきたいことがあります。
「あなたは自分が今の会社へ入社した頃のことを覚えておられるでしょうか?」
会社に入って仕事をすることの不安や「職場にはどんな人がいるのだろう?」「自分と合わない人がいたらどうしよう」と思ったことはなかったでしょうか。
未知の仕事に対する期待と同時に不安が募る。
新入社員の正直な気持ちは、ここにあります。
職場の先輩や上司として、新入社員に対してまず最初にするべきことは、そうした新入社員の期待に応え、不安を解消ないし軽減していくための支援であることなのです。
新入社員の気持ちを知る
職場で頻繁にみられる失敗例は、配属された新入社員に対し、いきなり業務を詰め込もうとすることです。
「会社は大学のサークルではない。会社は仕事をするところなのだから、やるべき業務の話をすることは当然だ」と考える人が多いことでしょう。
ですが、ちょっと待ってください。
新入社員は、会社に対する期待や希望を持って入社する一方で、大きな不安を抱えている場合がほとんどです。
そのような不安のある状態の中で、細かい業務の話をされてもほとんど吸収できないでしょう。
それどころか、かえって人材を壊してしまう結果にもつながりかねないことを理解してほしいところです。
新入社員が抱える不安とはどのようなものか、あなたが入社した時のことを思い出しながら一緒に確認していくことがよいでしょう。
「そんな悠長なことをしていては新入社員が仕事を覚えられない」と思っていませんか?
会社の厳しい採用手続きを経て入社してきた人財なのですから、彼らが抱える不安が解消ないし軽減される見通しがついたならば、仕事を覚えることも早くなるでしょう。
下手に年齢を重ねた人間よりも吸収能力は早いはずです。
ですから過度な不安・心配は無用であるように思うのです。
人間関係の不安
新しい会社に入社した新入社員が、まず不安を感じるのは会社の同僚や上司との人間関係にあると考えてまず間違いありません。
特に上司との人間関係については、学校の先輩などとは違い距離感がつかめなかったり、どのように接していいかわからなかったり、といった不安が多いものです。
また、後述いたしますが、入社して一番最初の上司というのは後々の社会生活に大きな影響を与えるほど重要な存在なのです。
新入社員にとって、「いい関係を築くことができるか」「しっかりとフォローをしてもらえるか」など、不安はどんどん募る一方です。
同僚に関しても「これから一緒に働いていく仲間として上手くやっていけるか」と思う反面「自分よりも先に出世したらどうしよう」といったライバル心などが芽生えるケースもあり、上手く付き合っているかどうかで悩む人も多いのです。
仕事に対する不安
なぜこの会社を選んだのか」と聞かれた場合に、大半の新入社員は「やりたい仕事ができるから」「やりがいがあると感じたから」と答えるものです。
彼らは、仕事に対して希望や願望を持って入社してきたものの、実際に働きだしてみると「思っていたのと違う」「やりたい仕事じゃなかった」と感じる場面が多くあります。
さらに、新入社員にもかかわらず「経験を積むため」「失敗をしておくと良い」などの理由から、いきなり大きな仕事を任せられるケースもあります。
「自分が任された!やったー!」と思う人もいますが、「いきなりこんな大仕事無理!」と思う人がほとんどで、期待されたことに対する嬉しさよりも、失敗した場合における不安の方が大きくなってしまう場合が少なくないのも事実です。
プライベートに対する不安
新入社員が不安を感じるのは会社における人間関係や仕事に関することばかりではありません。
会社に入るとこれまでとは生活環境がガラリと変わってしまいます。
一人暮らしや会社の寮生活などの開始、家族や友人、恋人とも離ればなれになるなど、環境の変化による不安を抱える人も少なくありません。
プライベートの環境が変わることによって精神的な不安を感じると、仕事に関しても「上手くいかない」「疲れがたまりやすい」「集中できない」といった影響が出てきてしまいます。
プライベートの不安は仕事の不安にも繋がりやすいため、注意が必要な要素なのです。
参照ページ
新入社員への指導方法のコツとは?大切なのは新人の気持ちを知ること!
新入社員に対する指導・育成のポイント
Z世代の新入社員を指導・育成し、職場の戦力としてしっかりと成長させるためには、次に掲げるポイントを押さえた指導や教育を行うと良いでしょう。
新入社員の価値観に理解を示す
まず、上司や先輩がいまどき新入社員の価値観を頭ごなしに拒まず、理解して受け入れることが大切です。
新入社員を指導する最大の目的は、新人の価値観を矯正することではなく、仕事を早く覚えてもらい活躍できるようにすることです。
いまの新入社員は、上司や先輩、会社の価値観を一方的に押し付けると強く反発する傾向が強くなっています。
したがって、先述のような新入社員あるあるを理解したうえで、彼(彼女)らに合ったアプローチ方法を模索することが大切です。
もちろん、活躍してもらううえで新人に身に付けてもらうべき考え方や言動もあります。
それらも一方的に「価値観」として押し付けるのではなく、何のために、なぜその考え方や言動が必要かを理性的に説明することが大切です。
承認の機会を増やす
いまどき新入社員は、前述の通り、承認欲求が高い傾向があります。
そのため、SNSでの「いいね!」と同じ感覚で、上司・先輩からの承認や褒め言葉によってモチベーションが上がりやすい特徴があります。
褒めることが少ない、たとえば、「仕事は見て覚えろ」「男は黙って……」といった昭和的な組織風土の組織では、いまどき新入社員の成長・定着を促すなら、ポジティブなフィードバックを増やすなどの変革が必要でしょう。
ただし、承認する、褒めるというのは、仕事の基準を下げるということではありません。
結果が出ていないのに仕事の水準を褒める、合格基準に達していないのにOKしてしまう必要はまったくありません。
姿勢やプロセス、成長に着目して、「取り組みへの姿勢」「努力」「以前からの成長」などの過程を承認する、ポジティブにフィードバックしてあげることが大切です。
なお、承認は外的報酬(外発的動機づけ)です。
外的報酬に慣れすぎると、同じレベルの報酬では満足できなくなり、不満が生じやすくなります。
新入社員に対する承認は大切ですが、「上司からの承認」に依存してしまわないように、仕事への興味・面白さ・ワクワク感のような内発的動機づけを促す仕組みづくりも必要です。
自ら思考する機会を増やす
前述の通り、ビジネスの意思決定は、明確な答えや正解はないことが大半です。
そのため、「正解」を探そうとする癖が身に付くと、いつまでも答えを出せず、手が止まってしまいがちです。
いまの時代、正解が外部環境の変化にともなって変わっていくことも多々あります。
こうした状況で大切なのは、自分で課題などを見て仮説を立てながら妥当解を出し、さらなる考えや上司などへの相談を通して、解決への精度を高めていくことです。
また、妥当解を素早く試して結果を踏まえて修正していくことも重要です。
新入社員の仕事や意思決定については、上司や先輩社員は正解を知っているケースも多いでしょう。
ただ、「正解を教えられる」ことに慣れ過ぎないように、教えすぎないことも大切です。
新入社員に「仮説思考」「考える習慣」「やってみること」を身に付けさせるために、すべての答えを教えてしまうのではなく、あえて答えを教えず考える習慣を持たせることを意識しましょう。
スケジュールに「空き」を作る
新入社員研修やOJTなどで、上司が新入社員のスケジュールを目一杯に詰めていた場合、与えられたタスクをこなすことが仕事になってしまい、タスクがなくなったときに指示待ち新人になってしまいがちです。
先ほどの「答えを考えさせる」に通じますが、この問題を解消するには、スケジュールに空白部分をあえて設けて、自分でスケジュールを決めて進めてほしいプロジェクトやタスクなどを指示しておく方法がおすすめです。
すると、プロジェクトのスケジュールを考えたり時間管理したり不明点の相談を積極的に行なったりと、主体的な行動を増加させることができます。
研修やOJT期間が終われば、自分のスケジュールを自分でコントロールして成果をあげることが求められます。
こうした仕事の取り組み方を新入社員のうちから身に付けさせるとよいでしょう。
目的・理由をハッキリと伝える
いまどき新入社員だけに限ることではなく、すべてのメンバーの指示・指導に関係することですが、特にいまどき新入社員の指導をするうえでは大切です。
いまどき新入社員は学校教育で「キャリア教育」を必修で受け、また、社会的にもLGBTQなどのジェンダーをはじめとして多様な価値観が認められる風潮の中で育ってきました。
その中で、多様な価値観を受け入れる許容度が広く、また、自分自身の価値観が認められることも自然だと思っています。
一方で、いまどき新入社員が嫌うのは、(自分が古臭いと感じる)価値観を一方的に押し付けられることです。
もちろん新入社員の個性や主体性は素晴らしいものですが、未熟な新入社員に成長して成果をあげてもらうためには、ビジネスにおける価値観や自社の常識を受け入れて吸収していってもらう必要があることは言うまでもありません。
しかし、指導する際に「これはこういうものだから……」「仕事だから……」「うちの会社ではこう決まっているから……」と目的や理由も言わずに一方的にこちらの価値観や当たり前を押し付けると反発が生まれます。
したがって、何かを指導する、実行してもらう必要がある際には、客観的に目的や理由を明確に伝える、新入社員が得られるものをきちんと伝えるといったステップが大切です。
参照ページ
新入社員の特徴に合った指導方法を解説!成長を促すポイントとは?
法務部門に配属された新入社員の指導・育成法
上述の新入社員に対する指導・育成法に関する一般論を踏まえて、今度は法務部門に配属された新入社員を戦力化していく方法を見ていくことにします。
本人の能力(現在値)を知る
法務部門に配属される新入社員は、学生時代、法学部や法科大学院等で勉強をした経験を持つ人材であるはずです。
もっとも、その習熟度には個人差があり、その差が業務をしていくうえで明確に表れてきます。
新入社員が配属されて間もない時期においては、まず最初にやるべきことは、「この新入社員は何を、どこまですることができるのか」「何を任せることができるのか」を把握することです。
もちろん、その時点においてのことです。つまり現在値、現在の能力を把握するのです。
社会人経験、とりわけ法務部門の業務を数年経験した先輩の眼から見ると、新入社員の能力の現在値は頼りなく見えることでしょう。
人事部等を説得し、スペシャリスト採用をした以上、「すぐに活躍できる即戦力のはず」と思っているのかもしれません。
確かに上司・先輩としては、そういう気持ちになることも理解できないわけではありませんが、あくまで新入社員であることに変わりはありません。
スペシャリストとしての採用は、入社後の「伸びシロ」に着眼したものであると受け止めておくべきです。
実際に新入社員に接し、人によっては「オレが新入社員の頃の方が遥かに上だな」と思う人もいることでしょう。
ですが、多くの場合、そうした自身に対する過去の評価は甘くなりがちです。
あなたが先輩社員として社会人として、その会社で、法務部門で立派に仕事をすることができているのは、駆け出しの頃、当時の上司や先輩があなたの欠点よりも長所を見つけ、それを伸ばそうとして育成に取り組んでもらったからであることに気づいていただきたいのです。
長所を探す
配属された新入社員の現在の能力の程度が分かったら、その次は、本人の長所を見つけたいところです。
ここでいう「長所」とは、どこの誰にも負けないというような突出したものでなくてよいのです。
本人の良いところ、法務の仕事をしていく上で伸ばしてあげると良いと思われる特徴を把握します。
その特徴は人によって区々ですが、例えば、「文章を書く能力に優れている」とか「言葉で説明することが上手である」というものが考えられます。
また、「ちょっとやそっとのことでは音を上げない」というものでもよいです。
新入社員が未熟なのは当然です。
それなのに上司や先輩たちから欠点の指摘ばかりされてはやる気を失ってしまいます。以後の成長が鈍化することにつながりかねません。
人財を壊す権利は、誰にもないのです。
本人の長所を伸ばしていく指導を心がけてください。
長所を伸ばしていくことができたならば、本人自ら欠点の克服にも意欲を見せるものです。
いきなり契約書ひな形等を渡さない
会社によっては法務部門において自社が締結する契約類型に応じた各種の契約書のフォームを多数用意していることでしょう。
多くの上司や先輩が新入社員に対し、「これは当社の契約書ひな形だよ。これを使うと契約案件の処理が効率的にできるよ。条項の意味が良く理解できない場合には、契約書ひな形の逐条解説がココにあるから、これを見るといいよ」等と言ってこれらを示してあげる風景をたびたび目にします。
ですが、新入社員が民法の理解について怪しいレベルにある場合、こうしたひな形や逐条解説は育成面でマイナス効果が目立つことに注意が必要です。
上司や先輩としては、少しでも早く一本立ちして欲しい、即戦力として活躍してほしいという一心からの助言なのですが、これは本人の成長を鈍化させてしまうことになります。
そればかりか、仕事に対して上司や先輩、さらには会社が「いつも答えを用意しているはずであり、その正解を教えてもらって当然」と考えるようになってしまう、いわば依存体質が形成されてしまうのです。
最初はストレッチから
上司・先輩が留意しておくべきことは、新入社員の戦力化を焦らないことです。
配属直後の指導方法を誤ってしまうと、想定していた成長曲線を描くことができなくなります。
スポーツの世界でもそうです。
例えば、プロ野球界において新人投手の投球フォームをコーチが修正指導したところ、球威も制球力も落ちてしまい、数年後には球界を去るに至るケースが見られます。
法務部門に配属された新入社員も同じです。
いきなり上司や先輩の方法論を与えて、その通りに仕事をさせることは待ってください。
この時期にやるべきことは、法務で仕事をしていく上での身体の動きを身に着けることです。
(会社や業界のことの理解や社会人としての振舞方等を除けば)契約案件でいえば、当事者間の権利義務関係をしっかりと理解することです。
身近に先輩がいる状態であれば、一緒に検討させてもらうと良いでしょう。
先輩にも自身が駆け出しの頃に戻って、結論を急ぐのではなく、ともに取り組んでもらえる環境を作ってもらえたならばなお良いです。
また、会社・業界によっては、業法に関する知識を吸収する必要もあるでしょう。
業法は総じて難解ですが、じっくりと取り組むことによって視界が拓けてくるはずです。
新入社員の時期でしか取り組むことのできない事項でもあるのです。
こうしたストレッチを積んでいくことにより、上述のようなひな形や逐条解説の意味(会社がそのようなスタンスを取っていることの政策的な意味)を理解することができるようになるでしょう。
まとめ
この記事では、法務部門に配属された新入社員に対する指導・育成の方法について解説しました。
特にスペシャリスト採用を実現した場合、受け入れ側である法務部門の上司や先輩としては、戦力化を急ぐ傾向にありますが、あくまでも新入社員であることを重視し、じっくりと育てる方針を固めておくべきです。
本人の特徴・長所が何なのかを観察していき、その長所を伸ばしていくことを考えてください。
欠点が目に付くはずですが、マナー等の問題を除けば、欠点の指摘ばかりが続くと本人がそれを気にするあまり、肝心の業務の内容に注力することに支障を来す場面も出てくることに注意していた台と考えています。