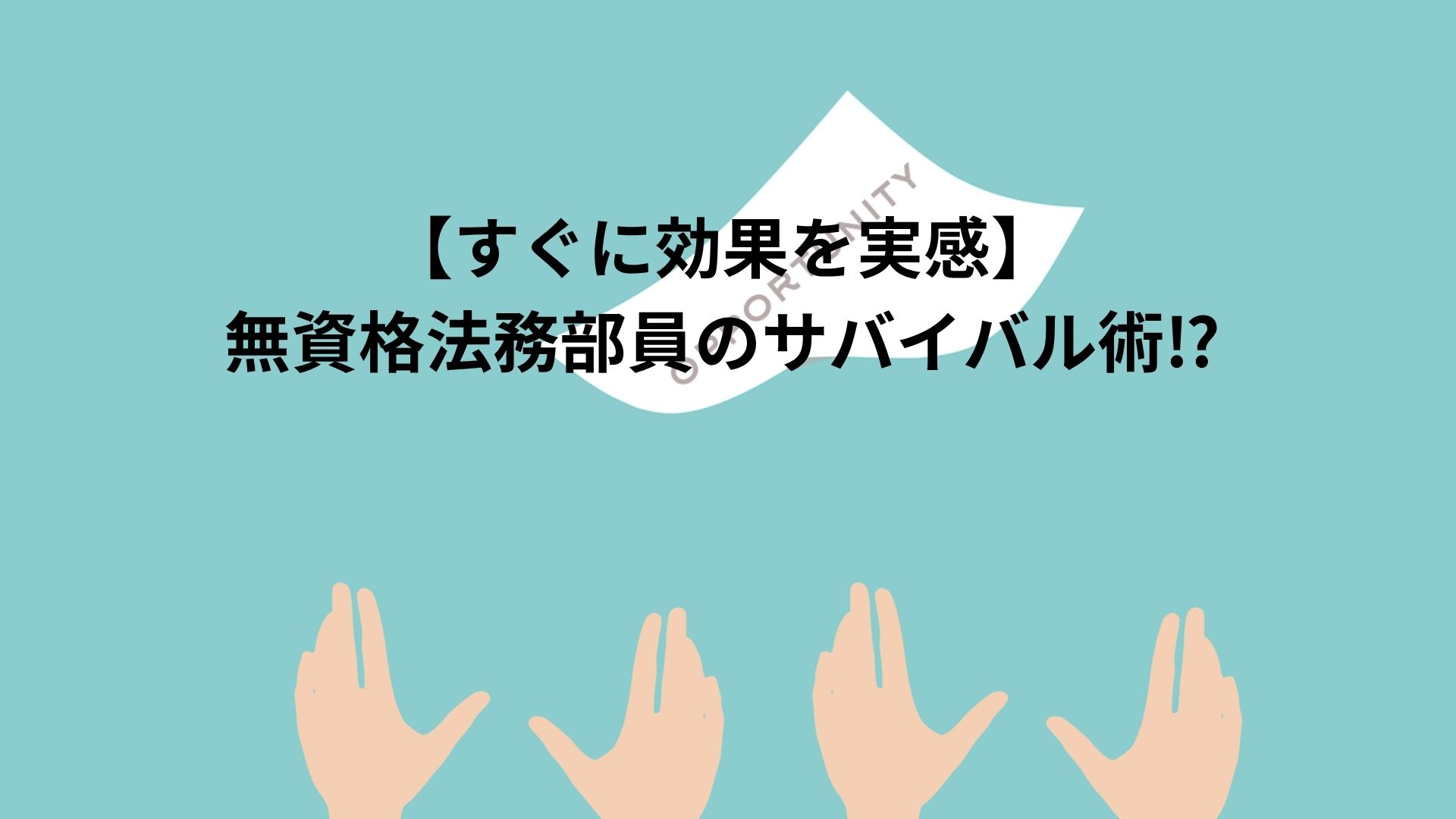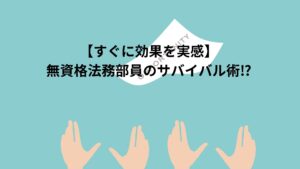※ 本記事には、プロモーションが含まれています。
1.はじめに

法務部に所属していながら「資格を持っていない」ことに不安を抱いていませんか?
弁護士や司法書士といった法律系の国家資格を持たずに、企業の法務部で働いているというケースは決して珍しいことではありません。
しかし、無資格であることに引け目を感じたり、自信を失ったりする必要は全くありません。
実際、多くの企業で活躍している法務部員の中には、実務経験と知識によって信頼を勝ち取っている無資格者も数多く存在しています。
とはいえ、現代の企業法務は複雑化・高度化しており、常にスキルアップや知識のアップデートが求められています。
無資格のままであることにリスクを感じるなら、スキルの棚卸しや今後のキャリアを見直す良いタイミングかもしれません。
本記事では、無資格で法務部に在籍している方が今すぐ実践できるサバイバル術を中心に、将来的に資格を取得することの意義やその道筋についても詳しくご紹介します。
ご自身のキャリアに対する不安を解消し、今後の方向性を明確にするためのヒントを得ていただければ幸いです。
無資格であることはマイナスではなく、工夫と努力次第で十分に武器に変えられる――そんな視点で、この記事を読み進めてみてください。
・法務の仕事の中には、弁護士等の資格がないとできない事項もあるが、多くの場合は特定の資格を持たなくても可能
・資格は邪魔になるものではなく、また、法務という性質上、法制度の改正等に応じ、知識を新たなものにしていく必要はあるため、勉強を続けるという姿勢を示すために資格取得に向けて取り組むことはキャリアアップの上では重要である
・試験に慣れていない人に向けて、比較的取り組みやすい資格を紹介するので、取り組んでみることを勧める
2.法務部の業務は資格がないとできないか
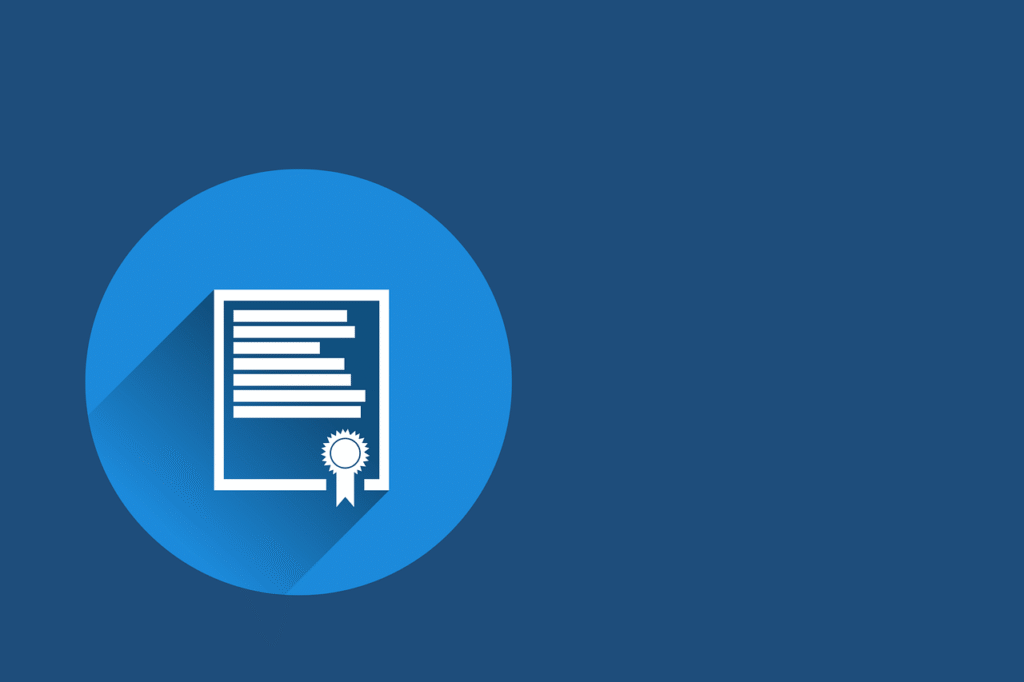
訴訟代理人になるのであれば、弁護士資格が必要
企業の法務部員として、自社の訴訟案件について訴訟代理人として当該訴訟に対応するためには、弁護士資格が必要です(弁護士法第72条)。
ただし、例外的なケースも存在します。
たとえば、簡易裁判所における訴訟では、企業内であっても「特定の条件を満たした使用人」が、裁判所の許可を得て代理人となることが認められています。
これを「使用人による訴訟代理(許可代理)」といい、実務上では一定の実績があればその許可を得ることができます。
許可代理は小規模訴訟や調停、債権回収などの場面で利用されることが多く、実務に携わる無資格者にとって、実力を発揮できる貴重な機会となることもあります。
しかしながら、あくまでこれは限定的な措置であり、全面的に訴訟活動を行うためには、弁護士資格の取得が前提となります。
そのため、企業法務としてより高度な法的対応力や交渉力を持ちたいと考えるのであれば、将来的に弁護士資格を視野に入れることも選択肢のひとつと言えるでしょう。
何のために資格が必要なのか
資格は「能力の証明」であると同時に、「独占業務へのアクセス」を得るためのパスポートでもあります。
例えば、弁護士資格を持っていれば、法律相談の実施、訴訟代理、契約書の作成・レビュー、さらには社内法務部門での法的意思決定への関与など、多岐にわたる業務に正式に携わることができ、その業務範囲の広さは法務部門の中で極めて大きな影響力を持つ要素となります。
これにより、社内外からの信用度や責任範囲も自ずと高まるため、キャリアの幅を大きく広げることが可能となります。
さらに、資格は対外的な評価基準にもなります。
例えば転職市場において、資格の有無は応募者の能力を短時間で見極める指標となり、履歴書上の強力な武器になります。
内部的にも昇進や職位の検討において、一定の資格保有が条件となっている企業もあるため、キャリアアップの要素として重要です。
ただし、資格がすべてというわけではありません。
資格を持っていない法務部員であっても、豊富な実務経験や専門性の高い知識、業務遂行能力によって社内外からの厚い信頼を築いている人は数多くいます。
資格の有無はあくまで手段のひとつであり、実務の中で自らの実力を証明し続けることが、真の信頼につながることも忘れてはなりません。
法曹等の資格がなくてもできる仕事は多い
企業の法務業務には、契約書の作成・レビュー、コンプライアンス対応、社内研修の実施、規程管理、知的財産管理など、多岐にわたる業務があります。
これらの業務は、必ずしも資格を保有していなければ実施できないものではありません。
実務経験や法律知識、論理的思考能力、社内コミュニケーションの巧拙といった要素が大きな影響を与えます。
たとえば、契約書のレビューにおいては、条文の意味を的確に把握し、リスクの有無を判断する力が求められますが、これは日々の業務を通じて養うことが可能です。
コンプライアンス関連では、業法や社内規程に対する深い理解と、社内教育や啓発活動を推進する能力が問われます。
これも、現場での経験や社内制度への理解を深めることで実践できる分野です。
また、知的財産の管理や出願対応、労務管理との連携を含む契約交渉支援、M&Aに伴う法的デューデリジェンスの準備なども、資格がなければ担当できないというわけではありません。
実際、これらの業務の多くは、法務部内で無資格の担当者が中心的な役割を果たしているケースも多く見られます。
さらに、社内研修の企画・実施や、法令改正の社内通知作成、リスク管理体制の整備といった”社内の法務インフラ”に関わる業務は、むしろ現場をよく知る無資格の実務者がリードするほうが効果的なこともあります。
このように、法曹資格がなくても、企業法務においては幅広く貢献できる余地があることを忘れてはなりません。
このことは、なにも法務部に限った事柄ではありません。
例えば、企業の財務・経理部の社員が皆、公認会計士や税理士等の資格保有者であるかというと、そういうことは稀です。
財務・経理部の業務も法務部と同様に、有資格者であることにより業務の幅が広がることはあることに疑いの余地はないものの、資格がなくてもその分野の専門的な見地から能力を発揮することのできる領域は十分にあるのです。
3.仕事をしながら資格を取得することは可能
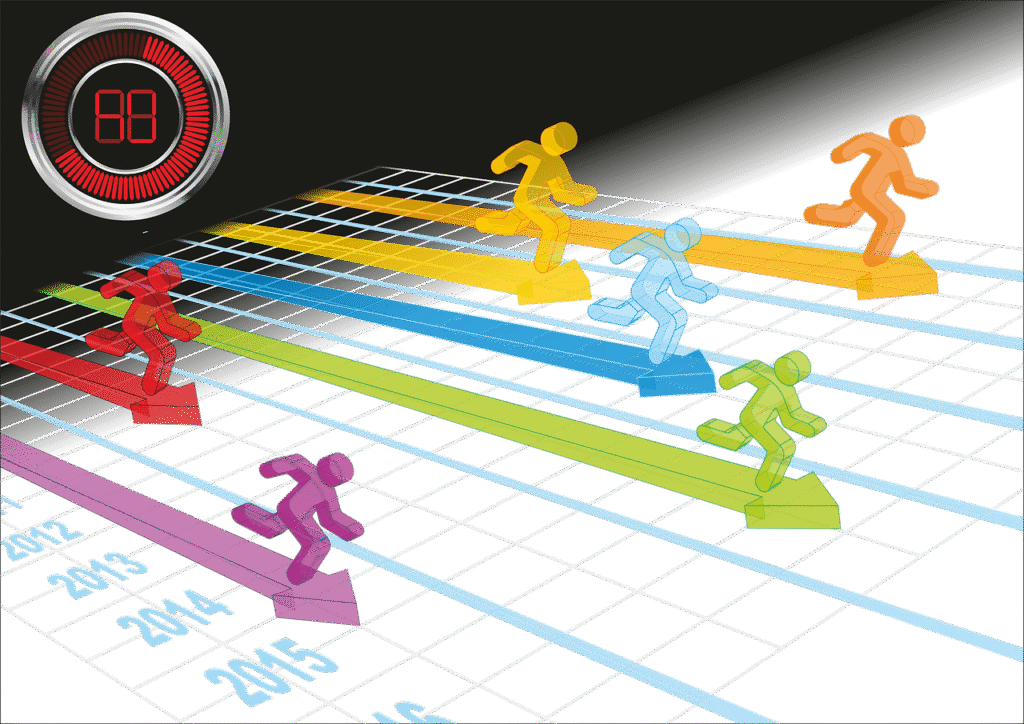
無資格であることを悩むのであれば、資格をめざせ
上述のように、たとえ、法務部において、法律関係の資格を有しない社員であったとしても、その能力を発揮することのできる業務は少なくありません。
しかし、それは法務部員は資格取得を目指す必要がないことを意味するものではないことを明確にしておきます。
この記事を読んでくださっている読者は、何らかの形で自らに誇ることのできる資格を十分に保有しているわけではなく、その点を気にかけているのであろうと想像します。
「無資格」という肩書にコンプレックスを感じているのであれば、まずはその気持ちに正面から向き合い、行動で乗り越えることが大切です。
資格がないという事実は変えられなくても、それをどう受け止め、どう未来へ活かすかは自分次第です。
資格取得はその最もわかりやすい打開策の一つです。資格を取ろうと決意すること自体が、すでに第一歩を踏み出した証でもあります。
特に法務部員としてキャリアを積んでいくうえで、一定の資格を持つことは、業務範囲の拡大にとどまらず、自分の法的判断力や知識の裏付けとして強力な武器になります。
たとえば、法務相談を受けた際に、社内の他部署からの信頼度が高まり、意見の説得力が増します。
また、社外の取引先や顧問弁護士と対等に議論するためにも、一定の資格があれば大きな安心材料になります。
さらに、企業によっては、役職や給与テーブルに資格要件を設けている場合もあり、資格の有無がダイレクトに評価や昇進に結びつくケースも珍しくありません。
そのため、中長期的なキャリア設計を描く際には、どのタイミングでどの資格に挑戦するのかという戦略的視点も必要です。
もちろん、働きながら資格の勉強をするのは簡単なことではありません。
家庭との両立や業務の繁忙期など、物理的・精神的な障壁は多々あります。
しかし、近年では通信講座やオンラインセミナー、AIを活用した学習アプリなど、学習スタイルは柔軟になってきており、社会人でも継続しやすい環境が整っています。
まずは1日30分でもよいので、勉強の習慣をつけることから始めてみましょう。
毎日の積み重ねが、やがて大きな成果へとつながります。
スケジュール管理アプリを活用したり、同じ資格を目指す仲間と励まし合ったりすることで、継続のモチベーションを保つ工夫も大切です。
通勤時間やランチ後の隙間時間など、日々のちょっとした時間を勉強に充てるだけでも、確実に前進している実感を得られます。
今こそ、自分の可能性を信じて新しい一歩を踏み出しましょう。
資格取得は「無資格」という状態から脱却するための手段であると同時に、法務パーソンとしての自信を高め、社内外で信頼される存在へと成長するための最良のステップでもあります。
目指すべき資格一覧
ビジネス実務法務検定(2級以上)
法務部門に必要な基礎知識から応用までを体系的に学ぶことができる検定であり、法律知識の幅と深さを証明できます。
企業内での業務に直結しやすく、受験者数も多いため実務者にとって人気のある資格です。
宅地建物取引士(宅建士)
不動産取引に関する法的知識を中心とした資格で、企業法務では特に不動産関連契約や担保設定、資産管理業務に関わる場面で役立ちます。
金融業界や建設業界の法務部門でも高く評価されています。
行政書士
許認可申請書類の作成や、法的文書の作成に強い資格です。
企業が官公庁とのやり取りを行う場面で力を発揮でき、独立も視野に入れられる実用的な資格です。
司法書士
登記関連業務、商業登記、裁判所提出書類作成など専門性の高い業務を担える資格です。
企業の子会社管理や商業登記に関する業務でその知識が求められることが多く、法務専門職としての地位向上にもつながります。
個人情報保護士
個人情報保護法や情報セキュリティに関する実務的知識を有していることを証明できる資格で、近年ニーズが高まっています。
特に個人情報を多く扱う業界や、内部統制・コンプライアンス部門との連携が必要な場合に有用です。
個人情報保護士は、比較的取得のしやすい資格です。
これについては別記事を用意していますので、ご興味をお持ちの方は併せてご覧ください。

知的財産管理技能士
特許、商標、著作権などの知的財産の保護と活用に関する知識が身につく国家資格です。
製造業やIT企業、エンタメ関連企業の法務部では重宝されるスキルの証明になります。
コンプライアンスオフィサー認定資格(CCO)
法令遵守体制の構築・運用に関する能力を認定する資格で、内部統制や企業倫理の観点から重要性が増しています。特に企業のCSRやガバナンス強化を進めるうえで有用です。
簿記検定(日商2級以上)
経理や財務の知識があることを示す資格で、法務と財務の連携が求められる契約やM&Aの場面で活用できます。
法務部員としての総合力を高める資格のひとつです。
これらはすべて、企業法務での実務に直結し、自身の専門性や付加価値を高めることができる資格です。
現在の業務内容や今後のキャリアビジョンに応じて、最適な資格を選び、段階的にステップアップを目指しましょう。
取得しやすい試験から取り組み、試験に向けてカンを養うのも一考
いきなり難関資格を目指すのではなく、まずは比較的合格しやすい資格(例:ビジネス実務法務検定2級、個人情報保護士)からスタートするのも一手です。
これらの試験は、出題範囲が明確で、独学でも対策が立てやすく、市販のテキストや過去問も豊富に出回っているため、働きながらでも学習が継続しやすい点が魅力です。
このような「比較的やさしい資格」に挑戦することには、いくつかの利点があります。
まず、法律の用語や出題形式に慣れることで、試験に向けた学習感覚を養うことができます。
また、合格体験を得ることで自己効力感が高まり、次のステップに挑戦するモチベーションが強化されます。
特に社会人の場合、達成感の積み重ねは継続学習の原動力になります。
小さな成功を積み重ねていくことが、結果的に大きな自信につながるのです。
さらに、こうした資格の多くは実務に直結しており、たとえ試験勉強の範囲であっても、業務中に活かせる知識が自然と身につきます。
たとえば、ビジネス実務法務検定2級では契約法や会社法、知的財産法などが出題されるため、法務文書を読む際の理解度が向上します。
個人情報保護士試験では、個人情報の取り扱いに関する実務的なリスクマネジメント力も強化されます。
これらの知識は、実務上の判断や書類作成、他部署との連携の場面などで即戦力として発揮されることが多く、業務効率化にもつながります。
また、比較的取得しやすい資格であっても、履歴書や社内申告書に記載できる実績として有効であり、自己PR材料としても説得力があります。
企業によってはこうした資格取得を人事評価に反映させる制度を設けている場合もあり、昇進・異動・キャリアチェンジの際に有利に働くこともあります。
副次的効果として、資格取得をきっかけに社内外の人脈が広がったり、学習グループを通じて横のつながりが強化されたりと、思わぬプラスの影響が出ることも期待できます。
このように、学習のリズムや「カン」を養うという観点からも、まずは難易度の低い資格から始めてみることは有効です。
試験勉強は決して一過性の努力ではなく、法務職としての思考力や法的感覚を磨くためのトレーニングと捉えるべきでしょう。
将来的により難易度の高い資格に挑戦する際の土台にもなりますし、まず一歩を踏み出すことで得られる成長の実感は、何にも代えがたい財産となるはずです。
4.法務部内で無資格でい続ける場合のサバイバル術

基本は、複数の顔を持つことがおススメ
一つの役割にとどまらず、多様な能力を持つ「ハイブリッド人材」を目指すことで、無資格でも重宝される存在になれます。
特定分野の専門性に特化するのではなく、法務知識はもちろん、業務改善スキル、ITリテラシー、プレゼンテーション能力、データ分析など、周辺スキルを柔軟に身につけることが重要です。
たとえば、契約レビュー業務に加えて、Excelやスプレッドシートを使って契約書管理の効率化を図る、あるいは社内向けの簡易マニュアルやFAQを作成して情報共有の中心的役割を担うなど、+αの価値を発揮できるポジションを築くことが理想です。
また、他部署との橋渡し役として機能することで、調整力や社内政治力を発揮できるのも「複数の顔を持つ」メリットのひとつです。
法務に限らず、業務改善や新規プロジェクトの立ち上げなどでも声がかかるような存在になることが、長く評価され続ける鍵となります。
こうした多面的な能力を備えることは、法務部門全体の柔軟性を高めることにもつながり、自身のポジション確保にとっても極めて有効です。
結果として、「無資格者であること」自体が問題とされないほどの信頼と実績を社内に築くことができるでしょう。
有資格者では務まらない、他に代えがたい存在を目指す
法務部には、資格者がやりたがらない業務や、業務量の多さから後回しにされがちな作業、または定型的であるがゆえに軽視されやすい重要な仕事が多く存在します。
たとえば、法令改正に応じた社内規程の修正案作成や、部署間調整に関する細かな文書の調整作業、反社チェックや個人情報同意書の管理業務、法務相談の初期ヒアリング対応など、資格の有無とは関係なく、正確さと丁寧さ、継続的な関与が求められる領域です。
こうした業務に主体的に取り組むことで、「あの人がいないと困る」と言われる存在になれます。
有資格者が手をつけにくい仕事にこそ、実務力と人間力を兼ね備えた無資格者が輝ける余地が広がっています。
また、自らマニュアルを整備したり、業務プロセスを見直して属人化を防ぐ取り組みを主導することで、業務の質的向上にも貢献できます。
さらに、定型業務だけにとどまらず、「現場の声」を拾って制度運用に活かす橋渡し役になることも、代替のきかない価値を生み出します。
法務部内外から相談を受けやすい環境を築くことは、組織全体の法務体制の底上げにもつながります。
このように、資格の有無に左右されない分野で深く関与し続けることが、「他に代えがたい人材」としての地位を確立するうえで極めて重要です。
具体例1:自分の能力を最大限に使って上司を立派に見せる
上司の意向や業務スタイルを理解し、資料作成や段取りなどを通じて「影の立役者」となることで強い信頼を得られます。
たとえば、上司がどのようなプレゼンスタイルを好むか、資料の構成は箇条書きがよいのかストーリーテリングが効果的なのか、といった細かな好みに配慮しながら資料を作成するだけでも、非常に頼もしい存在として評価されます。
また、上司が外部との折衝や社内説明の場でスムーズに話を進められるよう、法的な背景や想定される質問に対する答えを事前に用意するなど、サポート力を発揮する場面は数多くあります。
さらに、上司が抱える法務案件の優先順位を整理し、タスク管理ツールなどを使って進行状況を見える化する工夫も有効です。
このように「自分の存在によって上司が成果を上げられる」状態を作ることは、結果的にチーム全体のパフォーマンス向上にも貢献します。
上司にとって「手放したくない人材」となることで、自身の評価や信頼性も自然と高まっていくのです。
具体例2:AI活用を通じ、社内説明資料の作成に優れる
ChatGPT等の生成AIを駆使し、わかりやすく法的リスクを説明する資料を作れる人材は重宝されます。
特に近年では、複雑な法令や契約条項を非専門部署にも理解してもらう必要が高まっており、図解やサマリー、Q&A形式などで伝えるスキルは大きな強みになります。
AIツールを使えば、文書の要約や対話形式でのポイント整理が効率よくでき、従来数時間かかっていた資料作成作業が飛躍的に短縮されます。
例えば、新たな法律が施行された際に、自動要約機能や法改正の背景をわかりやすく噛み砕いて説明する文案をAIとともに作成すれば、上司や他部門からの信頼を勝ち取ることができるでしょう。
また、社内ポータルやプレゼン資料、社内セミナー用スライドなどの整備においても、AIの活用によりデザイン性と情報伝達力を兼ね備えたアウトプットを迅速に提供することができます。
さらに、AIに頼るだけでなく、自らの判断で正確な情報を取捨選択し、編集する力も磨かれるため、資料作成力そのものの底上げにもつながります。
このように、生成AIを駆使しながら法務資料の質とスピードを両立できるスキルは、無資格であっても専門職としての存在感を大いに発揮するうえで有効な武器となります。
具体例3:社内研修講師として教授法が評判
法務知識を分かりやすく伝えるスキルは、資格よりも重要な場合があります。
単に知識を持っているだけでなく、それをどのように噛み砕き、相手の理解度に応じて伝えられるかが重要です。
そのため、社内研修の講師として教える立場に立つことは、自らの知識の定着にもつながるうえ、周囲に知識を広められる存在として高く評価されます。
たとえば、契約法や個人情報保護、コンプライアンス、知的財産といった複雑なテーマでも、実務の背景や実例を交えながらわかりやすく解説できる講師は貴重な存在です。
PowerPoint資料を工夫し、双方向の質疑応答やクイズ形式を取り入れることで受講者の満足度を高めることもできます。
また、研修内容がそのまま社内ナレッジとして定着することで、社内全体の法務リテラシーの向上にも寄与します。
講師としての信頼が高まると、他部署からも法務への関心や相談が増え、組織全体のコンプライアンス体制の強化にもつながるでしょう。
このように、研修講師として活躍することは、自分自身のスキル向上だけでなく、組織全体に好影響を及ぼす可能性を秘めています。
具体例4:社内の弁護士がやりたがらない仕事(例:簡易裁判所の許可代理)の実績がある
許可代理人の制度を活用して、小規模訴訟の現場を任される経験は、現場感覚と実務スキルの向上に直結します。
簡易裁判所での代理業務は、証拠の整理や主張の構成、裁判所とのやり取りといった実践的な能力が問われるため、座学では得られないスキルを数多く習得するチャンスです。
また、社内の弁護士が時間的・業務的な理由で手を出しにくい領域に果敢に取り組む姿勢は、周囲からの信頼を勝ち取る要因にもなります。
訴訟案件の記録整理や関係部門との連携、裁判資料の提出準備など、地道ながら重要なプロセスを率先して担うことで、法務部の屋台骨を支える存在として評価されることもあります。
こうした取り組みは、自らのキャリアにおいても「訴訟対応の経験あり」という明確なアピールポイントになります。
実際、許可代理の実績を積み重ねたことがきっかけで、法務キャリアをさらに広げた無資格者も多く存在しています。
自らの専門領域を作り、他の法務部員とは一線を画した強みを持つことは、無資格者にとって極めて有効な戦略といえるでしょう。
具体例5:周囲の法務部員の精神的支柱として信頼を集める
人間的な包容力やチーム内の潤滑油となるような存在は、どの組織にも不可欠です。
特に法務部のように緊張感のある業務が多く、対立や調整が頻繁に発生する職場においては、精神的な安心感を提供できる人物の存在は非常に貴重です。
たとえば、周囲が忙殺されている時にさりげなくサポートしたり、失敗を責めるのではなく前向きにリカバリー策を提案できる姿勢が、信頼と共感を生みます。職場での会話のきっかけを作ったり、雑談の中からチームの変化を察知して必要なフォローを行ったりするような柔らかい対応も、チーム全体の空気を整えるうえで大きな役割を果たします。
また、後輩の相談役として法務業務の進め方や悩みごとに耳を傾けられる存在は、実務能力以上に「頼れる先輩」としての価値を発揮します。
資格やポジションに関係なく、職場に安心と活力をもたらす存在は、組織にとってなくてはならない存在です。
こうした内面的な魅力と信頼を積み重ねることが、結果的に資格者以上の影響力を持つことも少なくありません。
5.まとめ

無資格で法務部にいることは、決して恥ずかしいことではありません。
法律資格を持っていないという理由で自分を過小評価する必要はなく、むしろ「自分だからこそできること」に着目して、その価値を社内外に発信していくことが大切です。
法務部の仕事には、知識だけでなく、コミュニケーション力、対応力、調整力といった総合的なスキルが求められます。資格の有無は、その中の一要素に過ぎません。
資格取得に挑戦するという道は、知識の裏付けを持ちたい、もっと自信を持って発言したい、あるいは将来的に専門職として独立したいという強い意志の表れです。
それに向けて一歩ずつ努力を重ねること自体が、確かな自己成長につながります。
資格勉強の過程で得られる法的思考力や文書理解力は、実務にも大いに活かせるはずです。
一方で、資格がなくても法務部で確固たる地位を築く方法は多く存在します。
周囲との信頼関係を築き、実務で役立つ成果を出し続けること、またチームにとって欠かせない潤滑油のような存在であることも、非常に重要な要素です。
自らの強みを見極め、それを最大限に活かすことが、結果として組織にとって不可欠な人材となる道でもあります。
資格の有無に縛られるのではなく、「自分ならではの価値は何か」を問い続け、法務パーソンとして誇りを持って働けるよう、自分自身をアップデートし続けていきましょう。
あなたの努力と工夫次第で、どんなキャリアも切り拓いていけるはずです。