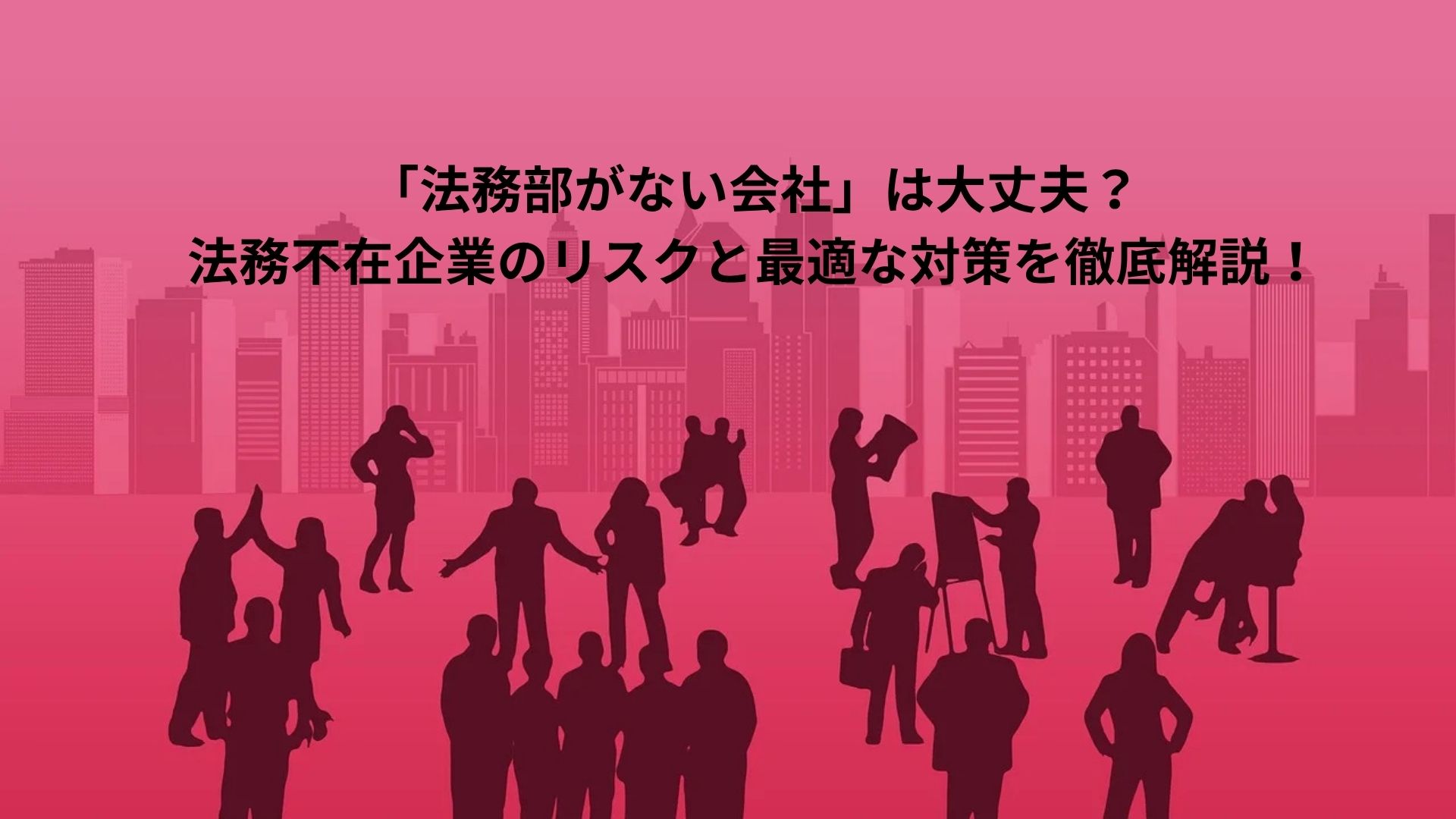※ 本記事には、プロモーションが含まれています。
企業の法的対応力が問われる現代において、「法務部がない会社は問題なのでは?」と不安に思う経営者や担当者も少なくありません。
しかし、法務「部」という名前の部署がなければ即リスク、という単純な話ではありません。
法務部とは別の組織、たとえば総務部や経営企画部の中に、法務「室」「課」「担当」といった名称で機能を担っている企業も多く存在します。
また、企業の業種や規模、取引の複雑性によって、必要な法務体制のあり方は千差万別です。
本記事では、法務部のという組織の有無にとらわれるのではなく、「自社にとって必要な法務機能をどう整えるか?」という視点で、法務不在企業の実情・課題・対策について徹底的に解説していきます。
- 企業の法務対応力が求められる現代、法務部がない会社のリスクを懸念する経営者も多い。
- 法務部がなくても、法務機能を他の部署(総務や経営企画部など)で担っている企業も多く存在する。
- 企業の業種や規模により、必要な法務体制は異なるため、法務部がなくても問題ないケースもある。
- 法務部の有無にこだわらず、「自社にとって必要な法務機能」を整えることが重要。
- 必要なのは、法務部がなくても法務機能を効果的に管理し、リスクを適切に予防する体制の確立。
法務部がない会社でも法務機能は果たせる!その実態と対応方法とは
- なぜ法務「部」がない会社が存在するのか?
- 法務「室」「課」「担当」など、名称は違っても役割は果たせる
- 法務機能を総務部や経営企画部で担うケースとは
- 社内での役割分担と明確な責任体制がポイント
- 中小企業が法務専任部署を持たない現実とその背景
- 法務クラウドやリーガルテックサービスの活用例
- 会社の実情に応じた柔軟な法務体制こそが重要
なぜ法務「部」がない会社が存在するのか?
法務部が独立した部署として存在しない会社は、実は決して珍しいことではありません。
特に、日本の中小企業や立ち上げ間もないスタートアップ企業においては、限られた人材と予算という制約があります。このため、経営資源を最も効率的に配分する観点から、法務部門の設置が劣後する傾向があることは否定できません。
このような企業では、多くの場合、総務、人事、経営企画といった既存の管理部門が法務機能を担う、すなわち兼務する体制がとられます。
この選択は、決して法務を軽視しているわけではなく、むしろ合理的な経営判断の結果であることがほとんどです。
例えば、急成長中のベンチャー企業であっても、IPO(新規株式公開)を控えた段階でも、社員数が50名未満といった比較的小規模な組織では、法務部の専門部署の設置は見送られることがあります。
その代わり、代表者自身やCOO(最高執行責任者)が主要な契約の最終確認を行うなど、経営陣が直接法務リスクの管理に携わるケースも少なくありません。
これは、経営トップが法務の重要性を認識し、自ら責任を負うという強い意志の表れとも言えます。
また、特定の業種やビジネスモデルによっては、法務部の必要性が低いと判断されることもあります。
例えば、BtoB(企業間取引)サービスを展開する企業であっても、提供するサービスが定型的で、取引先との関係が安定しており、かつ法的トラブルのリスクが限定的であると判断される場合、社内に専任の法務職を置く必要性は低いと判断されることもあります。
もちろん、この判断には細心の注意が必要ですが、ビジネスの実情に即した効率的な体制構築の一環として理解できます。
法務「室」「課」「担当」など、名称は違っても役割は果たせる
企業において法務機能が果たすべき役割は、法的リスクの管理、予防、そして発生した問題への対応に集約されます。
これらの役割は、必ずしも「法務部」という名称の部署によってのみ遂行されるものではありません。
実際には、法務「室」や「課」、あるいは単独の「担当」として法務業務を専門的に運用している企業も数多く存在します。
これらの組織は、一般的に法務部と比較して規模が小さく、人員も1〜2名体制であることが多いですが、その役割は多岐にわたります。
具体的には、契約審査、社内規程の整備、係争・訴訟対応、コンプライアンス教育の実施、知的財産管理、M&Aにおける法務デューデリジェンスの支援など、企業活動に必要な法務機能を十分果たしているケースがほとんどです。
重要なのは、その組織の名称や規模ではなく、「その組織が企業の法的リスクを効果的に管理し、予防し、そして問題発生時に適切に対応する能力を備えているかどうか」という点です。
つまり、実効性のある機能が確保されているかが最も重視されるべきポイントなのです。
法務機能を総務部や経営企画部で担うケースとは
特に中小企業や地方に拠点を置く企業では、独立した法務部を設ける代わりに、総務部や経営企画部が法務機能を兼務しているケースが非常に多く見られます。
総務部は、企業の基盤を支える部門として、多岐にわたる業務を担っています。
その中でも法務関連業務としては、以下のような役割を担うことが一般的です。
契約管理
企業が締結する様々な契約書(売買契約、業務委託契約、秘密保持契約など)の保管、更新管理、そして基本的な内容の確認や修正案の作成を担います。
印章管理
契約書や重要書類に使用する社印や代表者印の管理、押印の承認プロセスなどを担当し、文書の正当性を担保します。
社内規程の管理
就業規則、情報セキュリティ規程、コンプライアンス規程など、企業の内部統制に関わる各種規程の作成支援、改訂、周知徹底を行います。
許認可関連業務
事業に必要な各種許認可の申請や更新、関連法令の調査などを行います。
一方、経営企画部は、企業の戦略策定や事業計画の推進に関わる部門であり、法務機能の中でもより戦略的、かつガバナンスに関わる側面を担うことが多いです。
コンプライアンス体制の整備
法令遵守の徹底に向けた社内体制の構築、倫理規程の策定、役員・従業員へのコンプライアンス教育の企画・実施など、企業全体のコンプライアンス意識向上を図ります。
コーポレートガバナンスの強化
企業統治の透明性と効率性を高めるための仕組みづくり(取締役会の運営、監査役会の支援など)を支援します。
リスクマネジメント
事業活動に伴う潜在的なリスクを特定し、その評価、分析、そしてリスク低減策の策定を行います。特に、法的リスクは重要な要素となります。
新規事業の法的検討支援
新しいビジネスモデルやサービスの立ち上げに際し、関連法規の調査や法的リスク評価、法的課題解決に向けた助言を行います。
社内での役割分担と明確な責任体制がポイント
このように兼務体制で法務機能を運用する場合、最も重要なのは業務分担の明確化と、それに伴う責任体制の確立です。
誰がどの業務を担当し、どの範囲まで責任を持つのかを明確にしておくことで、業務の重複や漏れを防ぎ、トラブル発生時の対応もスムーズになります。
例えば、「契約書の一次レビューは総務部が担当し、特定の重要契約やリスクの高い契約については経営企画部が最終的な法的判断を行う」といった具体的なルールを設けることが考えられます。
また、「特定の法務問題が発生した際には、まず総務部が初期対応を行い、必要に応じて経営企画部や外部弁護士と連携する」といったフローを定めておくことも有効です。
こうした体制を構築するためには、各部門間の密な連携とコミュニケーションが不可欠です。
定期的な情報共有会議の実施や、共通のナレッジベースの構築などが有効な手段となります。
また、兼務担当者に対して、必要最低限の法務知識習得を促すための研修機会を提供することも、体制強化に繋がります。
中小企業が法務専任部署を持たない現実とその背景
中小企業庁の関連調査や、複数の専門機関による調査結果によれば、多くの中小企業が法務部門を独立して設置していないのが現状です。
例えば、ある調査では法務部門を設置している中小企業は全体の約1割に留まるとされており、別の調査では資本金5億円未満の企業において法務部門を置いていない企業の割合が約7割に達するなど、規模の小さい企業ほどその傾向が顕著です。
参照ページ
中小企業における法務の役割とは?法務部門を設置しないリスクも解説|企業法務弁護士ナビ
その理由としては、以下のような点が挙げられます。
契約の数が少ないため: 大企業と比較して、中小企業は取引先の数や取引の種類が限定的であることが多く、それに伴い締結する契約書の数も少ない傾向にあります。
そのため、日常的に法務専門の担当者を置くほどの業務量がないと判断されることがあります。
社内に法務の専門家がいない: 法務の専門知識を持つ人材は、一般的に数が限られており、中小企業にとっては採用のハードルが高いのが現状です。
専門性の高い人材を確保できないため、既存の社員が兼務する形にならざるを得ません。
顧問弁護士を活用しているため: 多くの企業が、日常的な法務相談や複雑な契約書の審査、トラブル対応のために顧問弁護士と契約しています。
社内に専門家がいなくても、外部のプロフェッショナルがサポートしてくれる体制があれば、日々の業務は滞りなく進められると考える企業が多いです。
コスト面の制約がある
法務部門を設置し、専門人材を雇用するには相応の人件費や運営コストがかかります。
特に中小企業にとっては、このコストが大きな負担となるため、設置に踏み切れない大きな理由となります。
実際に、ある地方の製造業の中堅企業では、経理部門の中に法務業務を兼ねる担当者が1名配置された例があります。
その担当者は、日々の小口契約の確認や社内規程の修正などを行い、M&Aや大規模な訴訟など、より専門的な知識を要する案件については、長年契約している顧問弁護士と密に連携しながら進めていました。
これは、限られたリソースを最大限に有効活用し、コストを抑えつつ必要な法務機能を確保する、合理的な判断例と言えるでしょう。
このような柔軟な体制は、中小企業の経営環境に適応した、現実的な解決策となり得ます。
社内法務リソースが足りない場合の対応策|アウトソーシングとALSPの活用
社内に法務の専門家がいない、あるいは法務業務量が特定の時期に集中するなどして、社内リソースだけでは対応しきれない場合、外部の法務リソースをうまく活用することが法務機能確保の鍵となります。
従来、外部の法務リソースといえば、顧問弁護士が主な手段でした。
弁護士は、法律の専門家として、契約書の作成・審査、紛争解決、法的なアドバイスなど、幅広いサービスを提供します。
多くの企業が顧問弁護士と契約し、日常的な相談から緊急時の対応までを委ねています。
顧問弁護士は、企業のビジネスモデルや文化を理解してくれるため、より的確なアドバイスが期待できるというメリットがあります。
しかし近年では、ALSP(Alternative Legal Service Providers:代替的リーガルサービスプロバイダー)と呼ばれる新たな選択肢も広がりを見せています。
ALSPは、従来の法律事務所とは異なる形態で、特定の法務業務を効率的かつコスト競争力のある形で提供するサービスプロバイダーです。
ALSPが提供するサービスには、以下のようなものがあります。
契約審査
大量の契約書の一次レビューや、定型的な契約書の作成・修正など、比較的ルーティンな契約業務を効率的に処理します。
AIを活用したサービスと連携している場合もあります。
知的財産調査
特許、商標、著作権などの知的財産の調査、管理、出願支援などを行います。
M&Aデューデリジェンス
M&A案件における膨大な量の契約書や法的書類のレビューを効率的に実施し、法的リスクを洗い出します。
リーガルリサーチ
特定の法的問題に関する判例や法令の調査を行います。
法務事務の代行
法務部における書類作成、管理、ファイリングなどの事務作業をアウトソースできます。
ALSPの活用メリットは、専門性の高い業務を必要な時に必要なだけ利用できる点、そしてコストを抑えられる可能性がある点にあります。
特に、法務部門を持たない企業にとっては、専門知識が不足している業務を高品質で外部に依頼できる有効な手段となります。
例えば、M&Aの際に一時的に大量の契約審査が必要になった場合など、社内リソースでは対応しきれない場面で威力を発揮します。
法務クラウドやリーガルテックサービスの活用例
近年、急速に進化しているのがリーガルテックと呼ばれる分野です。
AI(人工知能)やクラウド技術を駆使したサービスが次々と登場し、法務業務の効率化と品質向上に大きく貢献しています。
法務部を持たない企業でも、これらのツールを導入することで、これまで専門知識やマンパワーが必要だった業務を、比較的容易に、かつ低コストで実現できるようになりました。
具体的な活用例としては、以下のようなサービスが挙げられます。
AI契約審査ツール
「LegalForce」「AI-CON」「GVA assist」などが代表的です。
これらのツールは、契約書をアップロードするだけで、条項の抜け漏れ、不利な条項、一般的なリスクなどをAIが自動で検出し、修正案やコメントを提示してくれます。
弁護士の知見がAIに学習されており、短時間で高品質なレビューが可能になります。
法務の専門知識が乏しい担当者でも、基本的な契約リスクを把握し、対策を講じることが容易になります。
電子契約サービス
「クラウドサイン」「DocuSign」などが広く普及しています。
契約書の作成から送付、署名、保管までの一連のプロセスをオンライン上で完結できます。
これにより、印刷、製本、郵送、印紙代といったコストを削減できるだけでなく、契約締結までのリードタイムを大幅に短縮できます。
また、契約書の保管もクラウド上で行われるため、紛失リスクを低減し、検索性も向上します。
契約管理システム
締結済みの契約書を一元管理し、更新期限の通知、契約内容の検索、関連文書の紐付けなどを行うシステムです。
契約書の山に埋もれて重要な情報を見落とすといったリスクを防ぎ、契約履行の漏れを防ぐ効果があります。
法務関連ナレッジデータベース
法令情報、判例、法務関連ニュースなどを体系的に整理し、検索可能にしたデータベースサービスです。
常に最新の情報を手軽に入手できるため、法改正への対応や、個別の法的問題に関する調査を効率的に行えます。
これらのリーガルテックサービスは、導入コストが比較的低く、操作も直感的であるため、法務部門を持たない中小企業でも導入しやすいという大きなメリットがあります。
業務効率化と法的品質の向上を両立させ、賢く法務機能を補完する」ための強力なツールとなり得ます。
会社の実情に応じた柔軟な法務体制こそが重要
最終的に、企業が目指すべきは、自社の規模、業種、そして取引内容に最も適した、柔軟かつ実効性のある法務体制の設計です。
これは、「法務部があるかないか」という形式的な問いではなく、「法的リスクを適切に予見し、最小限に抑えるための仕組みが、社内にどれだけ堅固に構築されているか」という本質的な問いかけに他なりません。
例えば、頻繁に海外取引を行うIT企業であれば、国際契約法務に強い弁護士事務所との顧問契約や、英文契約に特化したAI契約審査ツールの導入が効果的かもしれません。
一方、国内で特定の製造業を展開する中小企業であれば、業界特有の法令遵守に詳しい社労士や弁護士との連携、そして総務部による契約管理と簡易な法務チェック体制の構築が現実的かつ十分な対策となり得るでしょう。
重要なのは、一度構築した体制を固定化するのではなく、企業の成長や事業環境の変化に応じて、常に最適な形にアップデートしていく視点を持つことです。
法務機能の強化は、単なるコストではなく、企業の持続的な成長と発展を支えるための戦略的な投資であるという認識を持つことが肝要です。
法務部がない会社が取るべきリスク管理と今後の選択肢
- 契約審査・トラブル対応は誰が担うべきか
- 実務担当者に最低限求められる法務知識とは
- コンプライアンス体制の整備|誰が責任者になるべきか?
- 内部通報制度やハラスメント対応の設計は万全か
- 「うちは法務部がないから…」では済まされない企業リスク
- 不祥事・訴訟時の企業イメージと実損失
- これからの選択肢|法務機能の強化と外部連携のすすめ
- 弁護士・司法書士・社労士との顧問契約の強化
- ALSP(代替的リーガルサービスプロバイダー)の積極的な活用
- 【総括】法務部がなくても機能すれば問題なし。必要なのは「実効性ある体制」
法務部がないからといって、企業が法的リスクから解放されるわけではありません。
むしろ、法務の専門家が社内にいない状況だからこそ、潜在的なリスクに対する意識を高め、効果的なリスク管理体制を構築することがより一層重要になります。
契約審査・トラブル対応は誰が担うべきか
企業活動において、契約書の作成や審査は最も基本的な、しかし最も重要な法務業務の一つです。
契約書は、企業間の権利義務関係を明確にし、将来のトラブルを未然に防ぐための設計図だからです。
例えば、「損害賠償条項」「解除条項」「準拠法」「裁判管轄」といった重要な条項に不注意な点があれば、将来的に大きな損害を被る可能性があります。
特に、海外企業との取引においては、準拠法や紛争解決手段の選択一つで、自社に極めて不利な結果を招くことも少なくありません。
法務部がない会社の場合、これらの契約業務は多くの場合、営業部門、調達部門、または管理部門(総務・経理など)の担当者が兼務することになります。
彼らはそれぞれの業務の専門家ですが、必ずしも法務の専門知識が豊富であるとは限りません。そのため、以下のようなリスクが生じやすくなります。
リスクの見落とし
法的専門知識が不足しているため、契約書に含まれる潜在的なリスクや不利な条項を見落とす可能性があります。
不適切な条項の挿入
知識不足から、意図せず不適切な条項を盛り込んでしまったり、必要な条項が欠落したりするリスクがあります。
交渉力の低下
法的な裏付けがないまま交渉を進めることで、相手方に有利な条件を飲まされてしまう可能性があります。
トラブル発生時の対応遅れ
契約書の解釈やトラブル対応において、法的判断が遅れたり、誤った対応を取ったりするリスクがあります。
これらのリスクを最小限に抑えるためには、社内の実務担当者が最低限の法務知識を持つこと、そして外部の専門家と連携する体制を構築することが不可欠です。
実務担当者に最低限求められる法務知識とは
法務部がない会社であっても、実務担当者、特に契約に日常的に関わる営業担当者や管理部門のスタッフには、最低限の法務知識が求められます。
これは、彼らが契約交渉の最前線に立ち、あるいは契約管理を行う上で、法的リスクを早期に察知し、適切な判断を下すための基盤となるからです。
具体的には、以下のような知識が挙げられます。
主要な契約類型とその特徴
「秘密保持契約(NDA)」「業務委託契約」「売買契約」「共同研究開発契約」「代理店契約」「ライセンス契約」など、自社が頻繁に締結する契約の基本的な構造、目的、そして一般的な条項について理解しておくこと。
契約の有効要件と効力
契約が法的に有効であるために必要な要件(合意、目的の適法性など)や、契約の効力発生時期、解除条件などを理解すること。
典型的なリスク要因
損害賠償責任の範囲、契約解除の条件、債務不履行時の対応、知的財産権の帰属、個人情報保護に関する条項、反社会的勢力排除条項など、企業にとって特に重要となるリスク関連条項の意義と注意点。
紛争解決条項
準拠法(どの国の法律が適用されるか)、合意管轄(どの裁判所で争うか)、仲裁条項(裁判外紛争解決手段の選択)などが持つ意味と、自社にとっての有利・不利。
コンプライアンスの基礎
独占禁止法、下請法、景品表示法、個人情報保護法、労働基準法など、自社の事業に関連する主要な法令の概要と遵守事項。
最近では、中小企業向けに特化した実務法務セミナーやeラーニング、あるいはビジネス書として出版されている「契約書レビューの基礎」といった書籍などが充実しています。
これらの学習機会を積極的に活用し、社内での研修プログラムを定期的に実施することで、実務担当者の法務リテラシー向上を図ることが重要です。
また、契約書のテンプレートを整備し、その解説資料を社内で共有することも有効です。
コンプライアンス体制の整備|誰が責任者になるべきか?
法務部の有無にかかわらず、コンプライアンス体制の整備は現代企業にとって不可欠な要素です。
法令遵守はもちろんのこと、企業の倫理規範、社会規範、そして社内規程の遵守も含まれます。
個人情報保護法、労働法、独占禁止法、下請法、贈収賄規制など、多岐にわたる法令に違反した場合、企業イメージへの致命的な打撃はもちろんのこと、巨額の罰金、事業停止命令、顧客からの信用失墜、従業員の士気低下など、計り知れない実損失を招く可能性があります。
法務部がない会社でコンプライアンス体制を整備する場合、その責任者の明確化が非常に重要です。
責任者は、コンプライアンスに関する最終的な意思決定を行い、その実行を監督する役割を担います。
代表取締役
企業のコンプライアンスに関する最終的な責任は、原則として代表取締役が負います。社長が直接陣頭指揮を執ることで、コンプライアンスに対する全社的な意識を高める効果も期待できます。
総務部長または管理部門長
現場との橋渡し役として、総務部長や管理部門長が適任となるケースも多いです。
総務部長や管理部門長は、企業の日常業務や従業員の実情をよく理解しており、コンプライアンス施策を具体的な行動に落とし込む上で重要な役割を果たします。
社内規程の作成・管理、従業員への周知、教育プログラムの企画・実施などを担当します。
コンプライアンス担当者
小規模ながらも、専任のコンプライアンス担当者を置くことで、より専門的かつ継続的なコンプライアンス活動を展開できます。
コンプライアンス体制の整備においては、以下の要素が不可欠です。
コンプライアンス基本方針の策定と周知
企業として何を守るのか、どのような姿勢で事業を行うのかを明確にし、全従業員に周知します。
社内規程の整備
就業規則、情報セキュリティ規程、個人情報保護規程、インサイダー取引防止規程など、各種社内規程を整備し、定期的に見直します。
従業員教育
新入社員研修や定期研修などを通じて、コンプライアンス意識の向上を図ります。具体的な事例を交えた研修は、より効果的です。
内部監査機能の導入
コンプライアンスが遵守されているかを定期的にチェックする仕組みを導入します。
法務部がない場合、チェックリスト運用や、部署横断的な監査チームの設置などが有効です。
違反時の対応フローの明確化
コンプライアンス違反が発覚した場合の報告経路、調査方法、処分、再発防止策などを事前に定めておくことが重要です。
内部通報制度やハラスメント対応の設計は万全か
近年、企業の社会的責任が強く問われる中で、内部通報制度(公益通報制度)やハラスメント対応体制の整備は、単なる努力義務を超え、企業の存続を左右する重要な要素となっています。
特に、2022年に施行された改正公益通報者保護法により、従業員数300人を超える企業では、内部通報制度の整備が義務化されました。
これには、通報窓口の設置、調査体制の構築、通報者への不利益取扱いの禁止などが含まれます。
法務部がない企業であっても、これらの制度は万全に設計され、運用される必要があります。
内部通報窓口の設置
社内窓口(人事部、総務部など)だけでなく、通報者が安心して利用できるよう、外部の弁護士事務所や専門機関に委託した外部窓口制度の導入が強く推奨されます。
外部窓口は、通報者の匿名性を確保しやすく、通報内容に対する客観的な調査が期待できるため、特に中小企業において有効な手段です。
通報後の調査体制
通報内容に応じて、適切な調査チームを編成し、事実確認を行う体制を確立します。
弁護士などの専門家の協力を得ることも検討すべきです。
通報者保護
通報者が不利益な取り扱いを受けないよう、明確な規定を設け、周知徹底します。
是正措置と再発防止
調査結果に基づいて、適切な是正措置を講じ、同様の事案が再発しないための予防策を策定・実施します。
ハラスメント防止規程の策定
パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメントなど、様々なハラスメントの種類を明確にし、その禁止を明記した規程を策定します。
相談窓口の設置
社内(人事部、総務部など)や外部の相談窓口を設け、従業員が安心して相談できる環境を整備します。
相談対応者への研修
相談に応じる担当者は、ハラスメントに関する専門知識を持ち、傾聴スキルや公正な対応ができるよう、定期的な研修が不可欠です。
迅速かつ公正な調査
ハラスメントの申告があった場合、迅速に事実関係を調査し、プライバシー保護に配慮しながら公正な判断を下します。
加害者への処分と被害者への配慮
調査結果に基づき、加害者には適切な処分を科し、被害者に対しては必要なケアや配慮を行います。
これらの制度は、単に法的義務を果たすだけでなく、従業員のエンゲージメント向上、健全な企業文化の醸成、そして企業のレピュテーション維持に直結するものです。
法務部がない場合でも、人事部門や総務部門が主導し、必要に応じて外部の専門家のサポートを得ながら、これらの制度を実効性のあるものにすることが重要です。
「うちは法務部がないから…」では済まされない企業リスク
「うちは法務部がないから、専門的な対応は難しい」という言い訳は、もはや現代社会では通用しません。
企業の社会的責任(CSR)が強く問われる中、消費者庁、労働基準監督署、公正取引委員会などの行政機関は、企業の組織体制の有無ではなく、実際の対応内容や予防策の実効性を厳しく評価します。
法務部門が存在しないことを理由に、法的トラブルへの対応が遅れたり、不十分であったりした場合、その企業は社会的な信頼を失い、事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
不祥事・訴訟時の企業イメージと実損失
一度不祥事が発覚したり、訴訟に発展したりした場合、企業が被る損害は計り知れません。
金銭的な損失だけでなく、企業イメージの低下やレピュテーションリスクは、長期的に企業の成長を阻害する要因となります。
法務部の有無自体が問題なのではなく、法的リスクに備える姿勢の有無が、企業の明暗を分けるということを考慮することが必要です。
リスクを軽視し、適切な予防策を講じていなかった企業は、結果として甚大な被害を被る可能性があります。
逆に、法務部がなくても、リスクに対する高い意識を持ち、適切な外部連携やリーガルテックの活用によって実効性のある対策を講じていた企業は、同様のリスクを回避できたかもしれません。
これからの選択肢|法務機能の強化と外部連携のすすめ
現代のビジネス環境は、法改正のスピードが加速し、企業に求められる法的対応の範囲も拡大の一途をたどっています。
例えば、2024年以降も、個人情報保護法の改正(Cookie規制の強化など)、消費者契約法の改正(不当条項の範囲拡大など)、労働関連法の改正など、様々な法制度が変更されています。
こうした変化に常にキャッチアップし、自社の事業活動に与える影響を評価し、適切な対応を講じるためには、常に最新の法務情報にアクセスできる体制が不可欠です。
法務部がない企業が、これからの時代に対応していくためには、以下の選択肢を積極的に検討し、組み合わせることが賢明です。
弁護士・司法書士・社労士との顧問契約の強化
顧問弁護士
日常的な法律相談、契約書審査、紛争解決、新規事業の法的検討など、幅広い法務業務に対応できます。
企業のビジネスモデルや業界特性を深く理解してもらうことで、より実践的かつ戦略的なアドバイスが期待できます。
特定の分野(国際法務、M&A法務、知的財産法務など)に強みを持つ弁護士を選ぶことも重要です。
司法書士
会社設立、役員変更、増資などの商業登記や、不動産登記、供託業務など、登記関連の業務において専門家です。
企業法務の基礎的な部分をサポートしてくれます。
社会保険労務士(社労士)
労働法務の専門家として、就業規則の作成・改訂、労働紛争の予防・対応、ハラスメント対策、社会保険・労働保険の手続きなどをサポートします。
特に労務問題は、従業員との関係性に直結し、企業の信頼性にも大きな影響を与えるため、社労士との連携は非常に重要です。
例えば、社労士と連携したハラスメント防止策や、適切な残業管理体制の構築は、企業リスクを大幅に低減する事例が多く見られます。
ALSP(代替的リーガルサービスプロバイダー)の積極的な活用
前述の通り、ALSPは、特定の法務業務を効率的かつコスト競争力のある形で提供します。
契約審査の大量処理、リーガルリサーチ、デューデリジェンス支援など、社内リソースでは対応しきれない専門業務をアウトソースすることで、法務品質を確保しつつ、コストを最適化できます。
リーガルテックサービスの継続的な導入と活用
AI契約審査ツール、電子契約サービス、契約管理システムなどは、法務部を持たない企業にとって、限られたリソースで法務業務を効率化し、ミスを減らすための強力なツールです。
これらのツールは日々進化しているため、自社のニーズに合わせて最新のサービスを積極的に導入し、その活用方法を従業員に浸透させることが重要です。
社内担当者の法務リテラシー向上
外部の専門家やツールを活用する一方で、社内担当者の法務リテラシー向上も継続的に行う必要があります。
基本的な法務知識は、トラブルを未然に防ぎ、外部の専門家との円滑なコミュニケーションを可能にするための基盤となります。
定期的な研修、法務関連情報の共有、質疑応答の機会の提供などを通じて、全社的な法務意識を高めていくことが重要です。
これらの選択肢を単独で利用するのではなく、自社の状況に合わせて柔軟に組み合わせる「ハイブリッド型」の法務体制を構築することが、これからの企業には求められます。
【総括】法務部がなくても機能すれば問題なし。必要なのは「実効性ある体制」
本記事を通して、「法務部がない会社」が必ずしも問題であるとは限らないことを申し述べました。
重要なことは、「法務部」という名称や形態にこだわることではなく、企業としての法務機能が「実効性」を伴って機能しているかどうか、という点に集約されます。
改めて、今回の解説の要点をまとめます。
- 法務「部」という名称にこだわる必要はない
- 社内での兼務体制や外部連携でも十分に対応可能
- リーガルテックやALSPの活用でコストを抑えつつ法務品質を確保
- コンプライアンス体制、契約審査体制を整備することが最優先
- 法的リスクを見据えた「実効性ある法務体制」こそが企業の信頼を守る鍵
法務機能の構築は、一度行えば終わりというものではありません。企業の成長ステージや事業環境の変化に合わせて、常に最適な体制を模索し、柔軟にアップデートしていくことが求められます。