※ 本記事には、プロモーションが含まれています。
転職活動において、履歴書や職務経歴書は求職者の第一印象を大きく左右する非常に重要な書類です。
採用担当者は、これらの書類を通じて応募者のスキル、経験、適性、人柄などを総合的に評価し、次の選考ステップに進めるかどうかを判断します。
つまり、たった数枚の紙がその後のキャリアを大きく左右することもあるのです。
この記事では、「転職 履歴書 盛り方」というキーワードを中心に、求職者が自分自身を魅力的に、かつ誠実にアピールするための書類作成テクニックを解説します。
単なる自己主張ではなく、事実に基づいた“魅せ方”を工夫することで、採用担当者の心に響く履歴書・職務経歴書を作成することが可能です。

- 「盛り」と「詐称」の境界線とは?
- 転職回数が多い場合の対処法は?
- 職務経歴書と履歴書、それぞれの違いとは?
- 盛ってもOKな項目・NGな項目とは?
- 書類審査通過率を高めるための工夫とは?
また、盛り方の工夫は一歩間違えると「信用を失うリスク」にもつながります。
そのため、この記事では「どこまでが許容範囲か」「どうすれば自然にアピールできるのか」といった実践的な視点から具体例を交えて解説していきます。
これから転職活動を本格的に始める方はもちろん、すでに応募書類を作成したことがある方も、本記事を参考に自分の書類を見直すことで、より完成度の高いアピールが可能になります。
ぜひ最後までご覧いただき、理想の転職先への第一歩を踏み出してください。
なお、履歴書における志望動機の位置づけ等については、別記事で解説していますので、併せてご覧ください。
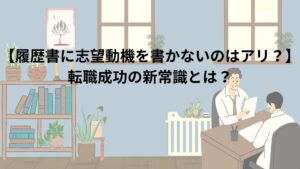
転職活動における履歴書の盛り方と注意事項
- 履歴書に記載すべき事項とは
- 履歴書に「盛れる」事項は何か
- 履歴書にどこまで盛ることができるのか
- 転職回数が多い場合に、職歴の一部を書かないことはアリか
- 履歴書で絶対NGなことは何か
履歴書の記載すべき事項とは
履歴書は、求職者のプロフィールを簡潔に伝えるための書類であり、以下の基本的な情報を必ず記載する必要があります。
基本情報(氏名、住所、連絡先など)
氏名、ふりがな、生年月日、現住所、電話番号、メールアドレスなどが該当します。
最近では、メールアドレスの形式や署名なども丁寧に記載することで印象がアップします。
学歴・職歴
時系列で簡潔に記載します。
学歴は高校卒業以降を記載するのが一般的です。
職歴では、会社名、部署、職務内容などを明記し、特に成果がある場合には簡単に補足を加えると効果的です。
免許・資格
業務に直結するものや、アピール可能な資格を記載しましょう。
資格取得年月を明記し、内容によりレベルやスコア(例:TOEIC○点)も補足するとなお良いです。
志望動機
その企業に応募した理由を、自分の経験やスキルに絡めて論理的に記述します。
企業研究を反映させた内容にすることで、熱意が伝わりやすくなります。
本人希望欄(勤務地、給与、その他)
希望する勤務地、勤務時間、給与、その他要望などを記載できます。
特に希望がない場合は「貴社の規定に従います」などと記載しておくのが無難です。
これらの項目はすべて、採用担当者が候補者の適性を判断する上で重要な情報となるため、正確かつ簡潔に記載することが求められます。
また、書式やフォーマットについても企業ごとに指定がある場合があるため、事前に確認した上で作成することが大切です。
さらに、書類全体の見栄えやバランスも印象に影響します。
手書きの場合は丁寧な文字を心がけ、パソコン作成の場合でも読みやすいフォントと整ったレイアウトを意識しましょう。
履歴書に「盛れる」事項は何か
履歴書における「盛り」は、事実に基づきながら自分を最大限魅力的に見せる表現力の工夫が求められます。
ただし、誇張しすぎて事実と異なる内容にならないよう注意が必要です。
以下に、代表的な“盛り方”のポイントをより詳細に解説します。
資格名の表現を工夫する
単に資格名を記載するだけでなく、その資格が業務にどう役立つかまで含めて記載すると効果的です。
例:「TOEIC700点取得済」→「TOEIC700点(ビジネス英語対応レベル。英文メールや電話応対に対応可能)」
例:「日商簿記2級取得」→「日商簿記2級(経理実務経験と連携し、月次決算対応可能)」
学校名や学歴を印象よく見せる
学校名そのものは変更できませんが、学部や専攻、学内での取り組みなどを加えることでポジティブな印象を与えることができます。
例:「地方国立大学」→「国立大学(経済学部、統計学ゼミにて実証研究に従事)」
例:「短期大学卒」→「短期大学(ビジネス実務学科卒、プレゼン大会で学内最優秀賞)」
職歴の要約で強調表現を加える
職歴欄では単に業務内容を書くのではなく、成果や実績を具体的に数値で表すことで印象が格段にアップします。
例:「営業担当」→「年間目標達成率120%を記録した営業担当(新規開拓営業を主軸とし、地域売上No.1を獲得)」
例:「事務職」→「チーム内の業務効率化を提案し、作業時間を20%削減した事務担当」
これらの盛り方を意識することで、読み手に「この人は戦力になりそう」「具体的な実績がある」と思わせることができます。
ただし、裏付けのない誇張は面接時に見抜かれるリスクがあるため、自信を持って話せる内容に限定しましょう。
履歴書にどこまで盛ることができるのか
履歴書の“盛り”には、一定の範囲とルールがあります。
誤解されがちですが、盛ること自体が悪いわけではなく、あくまで「印象をよくするための工夫」として、事実を脚色しすぎない範囲で使うことがポイントです。
事実に基づいた表現なら問題なし
自身の実績や経歴を、強調してわかりやすく伝える表現は許容されます。
たとえば「部署の一員として参加」した業務でも、「プロジェクトに携わり、課題解決に貢献」と言い換えることは可能です。
“盛り”は印象の演出に留める
「成果を強調」「役割の範囲を明確にする」など、読み手に自分の良さが伝わるように言葉を選ぶのがコツです。
一方で、事実と異なる役職や業務範囲を記載するのはNGです。
たとえば、実際にはチームメンバーとして営業をしていた場合、「チームリーダーとして戦略を立案」と書くのは虚偽にあたります。
成果や数字は裏付けできる範囲で提示する
「前年比120%達成」や「月間新規顧客獲得数30件」など、数字を使った成果は説得力を増しますが、必ず証明可能な範囲にとどめましょう。
面接で詳しく問われた際に説明できなければ、かえって信頼を損なう結果になります。
履歴書における盛り方は、「嘘にならない範囲で自分の強みを最大限引き出す技術」です。
特に、言い回しや表現を工夫することで、同じ内容でも読み手に与える印象は大きく変わります。
求職者としての信頼を損なわず、かつ効果的にアピールできる“盛り”を意識して記載しましょう。
転職回数が多い場合に、職歴の一部を書かないことはアリか
空白期間が長くならない範囲で調整は可能
転職回数が多くなると、応募先企業によっては「継続性がない」「定着性に欠ける」といったネガティブな印象を持たれることがあります。
そのため、履歴書に記載する職歴の選別はある程度行っても構いません。
特に短期間(1年未満)の契約や派遣、アルバイトなどは、必ずしもすべてを記載する必要はありません。
ただし、職歴の間に不自然な空白期間が発生すると、かえって疑念を持たれるため、ブランクが長くならないように調整することが重要です。
ただし職歴詐称と受け取られないように注意
一部の職歴を省略することは可能ですが、「なかったこと」にするという意識ではなく、「重要度や関連性の低い職歴は簡略化する」という方針で臨むことが大切です。
具体的には、履歴書本体では省略しても、職務経歴書や面接の際に聞かれたらきちんと説明できる準備をしておきましょう。
正直さを保ちつつ、アピールすべき経験を優先して伝える姿勢が信頼につながります。
派遣や短期契約での就業歴については、「補足事項」欄や職務経歴書の末尾に簡単な記述を加えることで、説明責任を果たすことが可能です。
たとえば「2022年4月〜2022年6月:短期派遣にて事務補助」などと記載することで、空白の回避と説明のバランスを両立できます。
このように、転職回数が多い方ほど「書かないこと」のリスクと、「どう書くか」の工夫が重要になります。
省略の判断基準は、“採用企業にとって価値のある情報かどうか”という視点で行うとよいでしょう。
履歴書で絶対NGなことは何か
履歴書は第一印象を左右する重要な書類であるため、いくつかの基本的なマナーやルールを守らないと、いくら内容が良くても不採用につながってしまうリスクがあります。
以下に、絶対に避けるべきNG項目を詳しく紹介します。
虚偽の記載(学歴詐称、資格の未取得など)
採用されたいがために、取得していない資格を記載したり、学歴を実際より高く記載する行為は絶対にNGです。
仮に内定後に判明した場合、内定取り消しや懲戒解雇の原因となります。
手書きが雑、誤字脱字がある
手書きの場合、字の丁寧さや誤字脱字の有無はその人の仕事ぶりにも通じると見られます。
雑な文字や明らかな漢字の間違いがあると、誠実さを疑われる原因になります。
パソコン作成でも同様で、誤字脱字は読み手の印象を大きく損ねます。
見直しは必須です。
写真が適切でない(スナップ写真、背景が不自然など)
プライベート感のある写真や明らかに適していない服装の写真はマイナスです。
スーツを着用し、背景が白または薄いグレーの証明写真を使いましょう。
また、サイズが合っていなかったり、ピンぼけしているものもNGとされます。
空白が多すぎる、志望動機が浅い
志望動機の欄が空欄だったり、内容が短すぎる場合は、「志望度が低い」「本気度が伝わらない」と判断されかねません。
また、「御社の成長性に魅力を感じた」などの抽象的な表現だけではなく、企業研究を基にした具体的な記載が求められます。
これらのNGポイントは、見落とされがちな部分ですが、書類選考の段階で致命的な印象を与えてしまうことがあります。
細部まで丁寧に仕上げる意識を持つことが、成功する転職活動の第一歩です。
転職活動における職務経歴書の盛り方と注意事項
- 職務経歴書の記載すべき事項とは
- 職務経歴書と履歴書の記載事項は重複してもよいか
- 職務経歴書に「盛れる」事項は何か
- 職務経歴書でタブーとされる内容があるか
- 履歴書と職務経歴書は、いずれも提出する必要があるのか
- 総括|転職活動における履歴書/職務経歴書の盛り方と注意事項
職務経歴書の記載すべき事項とは
職務経歴書は、履歴書と並んで転職活動において重要な役割を担う書類であり、より詳細に自身の業務経験や成果を伝えるためのツールです。
採用担当者にとっては、候補者が実務にどう貢献できるかを判断する基準になるため、内容の正確性と分かりやすさが求められます。
以下に、職務経歴書に記載すべき主要な事項について詳しく説明します。
所属企業名・在籍期間
在籍していた企業の正式名称と、勤務していた期間を明記します。
企業の業種や規模が一般的に知られていない場合は、簡単な説明を添えると理解を助けます。
例:「株式会社ABC(従業員数約200名、BtoB向けのITサービス企業)」
業務内容
担当していた部署や職種、具体的な業務内容を詳細に記述します。
単なる職種名だけではなく、「どのような役割を果たしたか」「どのような手法で業務を行っていたか」まで書くと説得力が増します。
例:「法人営業として、新規開拓および既存顧客へのフォロー業務を担当。月10〜15社への提案活動を実施」
実績や成果
業務上の成果をできる限り数値で示すことで、客観的な評価につながります。
売上の伸び率、改善された指標、プロジェクトの達成状況など、定量的に表現できる項目は積極的に取り入れましょう。
例:「既存顧客へのアップセルにより、前年比150%の売上向上を達成」
使用スキルや経験
使用していたソフトウェア、業務上活用した言語やフレームワーク、または業界知識など、スキルや経験を具体的に記述します。
実務でどのように活用していたかを補足すると、さらに評価が高まります。
例:「Excel(ピボットテーブル、VLOOKUP関数を活用した月次レポート作成)、Salesforce(案件管理、商談進捗管理)」
自己PRや志望動機(補足)
書類の末尾などに、これまでの経験を通して身につけたスキルや仕事への姿勢を自己PRとしてまとめると、人物像が伝わりやすくなります。
志望動機は、応募企業に対する理解とマッチング度を示す内容にすると効果的です。
例:「業務を通じて培った『傾聴力』と『課題発見力』を活かし、貴社の営業チームに貢献したいと考えております」
職務経歴書は、応募者の“ビジネス履歴書”とも言える重要な資料です。
単に経歴を並べるのではなく、「自分の何が企業にとって価値があるのか」を意識して記載することで、より高い評価を得られる可能性が高まります。
職務経歴書と履歴書の記載事項は重複してもよいか
基本的には問題なし
履歴書と職務経歴書はそれぞれ異なる役割を持つため、記載する情報の中身が重なる部分があっても基本的に問題はありません。
履歴書はあくまで「概要の提示」が目的であり、職務経歴書は「詳細な業務内容と成果のアピール」に特化した書類です。
たとえば、履歴書には「○○株式会社 入社(営業職)」と簡潔に記載し、職務経歴書では「新規開拓営業として月平均10件のアポイントを獲得、年間売上目標達成率120%を達成」などのように、具体的かつ詳細に業務内容を記述します。
ただしコピペではなく、視点を変えて記述するのがベター
同じ情報を記載する場合でも、表現の切り口や文体を変えることで、採用担当者にとっての理解しやすさや印象の良さが向上します。
特に職務経歴書では成果や実績を数値化し、どのようなスキルを活用していたのかを補足することが重要です。
また、履歴書は定型的な様式が多いため、自由記述が可能な職務経歴書での補完や差別化が求められます。
両方の書類が重複しつつも異なる角度から自分を伝えることで、説得力が増し、採用担当者に好印象を与えることができます。
職務経歴書に「盛れる」事項は何か
職務経歴書では、自分の経歴や実績をアピールするために“盛り”を取り入れることが可能ですが、履歴書以上に「裏付け可能な事実に基づく表現」が重視されます。
以下は、職務経歴書で効果的に盛ることができる代表的な項目です。
実績の具体的な数値化
成果や成果指標を数字で示すことにより、説得力を高めることができます。
ただ「頑張った」と記すよりも、「何を達成したか」を明確にしたほうが印象に残ります。
例:「営業活動」→「新規顧客開拓数 月平均10社、年間契約件数40件」
さらに補足して「アポイント獲得率30%向上」「既存顧客売上前年比160%達成」などのように表現を工夫すると、アピール力が増します。
担当プロジェクトの社会的意義や成果を強調
自分の関わったプロジェクトがどのような目的で実施され、どのような成果や影響をもたらしたのかを具体的に記述しましょう。
例:「業務効率化プロジェクトに参画」→「業務フローの改善で作業時間を30%削減し、部署全体の残業時間が平均10時間短縮」
また、「社内評価制度見直しプロジェクトにより、社員満足度が大幅に向上」など、定性的成果を具体的に伝えるのも有効です。
役割やポジションの工夫された表現
自身の立ち位置をより明確に伝えることで、「単なるメンバー」ではなく「価値を生み出せる人材」である印象を与えることができます。
例:「開発チームの一員として従事」→「メイン機能開発を担当し、仕様策定から実装・テストまでを一貫して実施」
このように、職務経歴書では事実を正確に伝えつつ、読み手にインパクトを与える構成と表現を心がけることで、より強い自己アピールが可能になります。
職務経歴書でタブーとされる内容があるか
職務経歴書では、自分の経歴や実績を正しくかつ魅力的に伝えることが求められますが、その一方で記載すべきではない内容、つまり“タブー”もいくつか存在します。
これらを避けることで、書類全体の信頼性や印象を損なわずに済みます。
あいまいな表現(例:多くの経験)
「多くの業務に携わった」「さまざまなプロジェクトを担当」などの抽象的な表現は、何をしてきたのかが伝わりにくく、評価の対象になりにくい傾向があります。
読み手に伝わるよう、可能な限り具体的な業務内容や成果を記載しましょう。
例:「さまざまな業務に対応」→「経理・労務・庶務業務を並行して担当し、月間の経費処理件数は100件以上」
退職理由の詳細な記載(必要がない限り省略)
職務経歴書では基本的に退職理由の記載は求められていません。
特にネガティブな理由(例:上司との対立、会社の体制への不満など)は逆効果になりかねません。
面接時に聞かれた場合に備えて口頭で説明できる準備はしておきつつ、書面では「一身上の都合により退職」「契約満了のため退職」など、簡潔な記述にとどめるのが賢明です。
ネガティブな要素(人間関係、待遇など)
前職での人間関係のトラブルや、不満に感じていた給与・労働条件について触れることは避けましょう。
仮に事実であっても「他責的」「協調性に欠ける」という印象を与える可能性があります。
また、職務経歴書はポジティブな実績や能力をアピールする場であるため、否定的な内容は記載しないことが基本です。
企業にとってプラスとなる情報に焦点を当てて構成しましょう。
このように、書類作成においては「何を書くか」だけでなく「何を書かないか」も同様に重要です。
タブーを避けることは、応募者としての信頼性を高める第一歩であり、選考通過率の向上にもつながります。
履歴書と職務経歴書は、いずれも提出する必要があるのか
基本的には両方提出が望ましい
履歴書と職務経歴書は、それぞれ異なる情報を伝える役割を担っています。
履歴書は基本情報や学歴、職歴、資格、志望動機などを簡潔に伝えるのに対し、職務経歴書は実務経験やスキル、成果をより詳細に記述するものです。
したがって、採用担当者が求職者を多角的に評価するには、両方の書類が必要です。
一部のIT系職種などでは職務経歴書のみ求められることもあり
特に即戦力が求められるエンジニア職やフリーランス向け案件などでは、履歴書よりも職務経歴書やポートフォリオの提出が重視される場合があります。
こうした場合、履歴書は省略可能とされることもありますが、念のためフォーマットを用意しておくと安心です。
企業ごとの指定に従うことが最優先
応募先企業が求める書類の種類やフォーマットに従うことが絶対条件です。
求人票や企業の採用ページには、提出書類に関する明確な指示があることが多いため、必ず確認しましょう。
もし不明な点があれば、問い合わせて確認することも選考に対する誠実な姿勢として好印象につながります。
両方の書類を揃えておくことは、転職活動において自分の魅力を幅広く伝えるための基本です。
形式にとらわれず、それぞれの役割を理解しながら、応募先に応じた柔軟な対応を心がけましょう。
総括|転職活動における履歴書/職務経歴書の盛り方と注意事項
この記事のポイントをまとめておきます。
- 「盛り」は事実の強調・魅せ方の工夫にとどめる
- 適切な数値化や表現で説得力のある書類に仕上げる
- 嘘にならないよう事実をベースに組み立てる
- 自分の強みを読み手に伝える意識を持つ
- 書類は「会ってみたい」と思わせることがゴール

