※ 本記事には、プロモーションが含まれています。
◆法務部門とは、企業における各種の法的事項(契約、機関決定、紛争解決等)に関する業務を取り扱う組 織です。組織名称が「法務部」か否かは、各社の判断によります。
◆法務部門が取り扱う業務の種類・範囲は、各社に在籍する法務の人員構成・規模等によって異なります。中小の企業の中には、ひとりの社員で法務全般の業務を取り扱っている会社も少なくありません。
◆他の企業の法務部員の業務状況を知り、「自分は、そのような業務を行ったことがない」と不安を覚える方もおられるかもしれません。しかし、そのような心配は無用です。
◆法務部員が各自の能力を高めるためには、「どのような業務をしているか」よりも「どのような仕事の方法を採用しているか」の方が重要です。この記事を他の記事と併せ読むことを通じ、「他の人よりも一歩進んだ仕事をする」ことを意識して仕事をすれば、きっと良い結果を生み出すことができるでしょう。
企業における法務部門の位置づけ
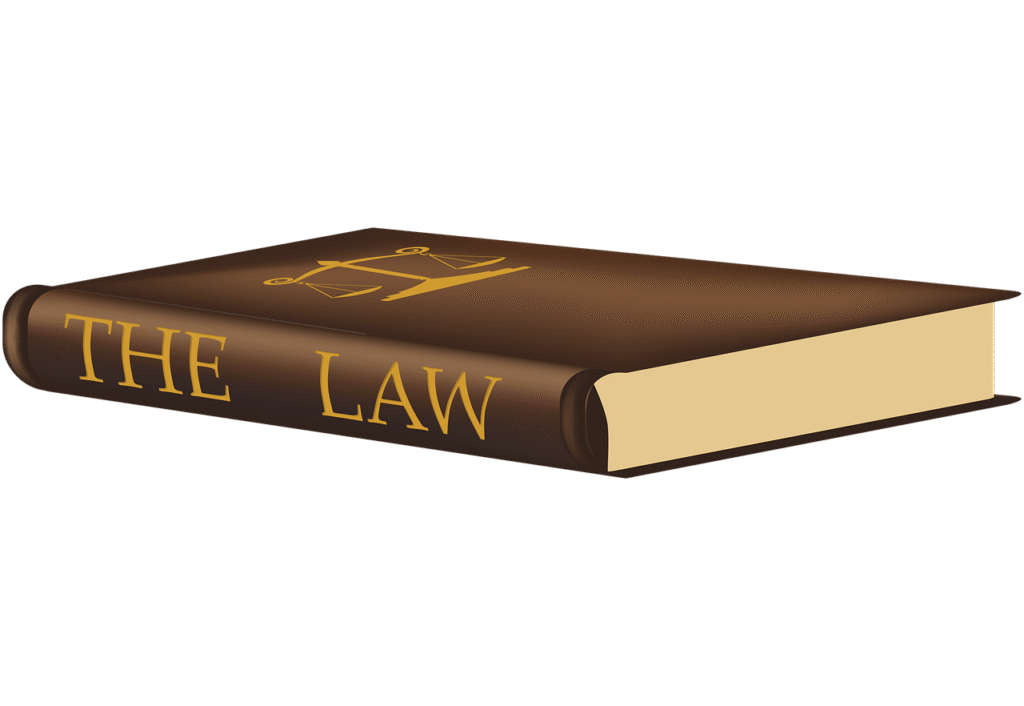
(1)法務部門とは
企業における各種の法的事項(例えば、契約手続、株主総会・取締役会等の機関決定、紛争解決等)に関する業務を取り扱う組織が法務部門です。
組織の名称については、代表的なものは「法務部」ですが、「部」よりも小規模な組織である場合には、「法務室」というように「室」を用いる企業もあります。また、特定の組織、例えば、総務部内の1つの担当ないし課に法務の業務を担わせることも少なくなく、その場合には「総務部法務担当」とか「総務部法務課」という名称になることがあります。
さらに、法務以外の業務の占める比重が高い場合には、法務の語を用いることはせず、例えば、総務部内の特定の担当ないし課がいわば兼務する状態の中で法務機能を担うこともあります(総務部総務担当等)。

法務部門は、企業における
各種の法的事項に関する業
務を取り扱う組織です。
(2)人員構成
法務の人員構成をどのようなものとするか、については、各社の事情・政策判断によるといえます。すなわち、上場企業の中でも管理職を含め、5名程度の人員で法務対応を行う会社もあれば、総勢100名程度の陣容を要する大規模な法務部を設ける会社もあります。
ここで注意を要するのは、法務部門の人員が比較的少数の企業の場合、法務と関連する業務を他の組織で担うことが少なくなく、社内の関連組織の連携体制により法務機能を発揮することがあることです。
このため、大規模な法務部門と比較して、法務機能が低下するということを意味することを直ちに意味するものでありません。
次に、社員の中には、日本または米国の弁護士資格を保有する者が配置されていることもあります。特に近年は、日本で司法修習を終了した後、すぐに企業でインハウスの弁護士として執務を開始するケースも多く見られるようになりました。
また、在職中、各社の制度に従い、米国等のロースクールに留学し、米国の弁護士資格を取得し、一定の期間中、米国の法律事務所で実務経験を積み、その後、帰国して再び法務部門で業務をする社員も増える傾向にあります。
一方、中小企業の場合には、上場企業をはじめ大企業のように多くの法務人材を措置することは実際上困難だといえます(小規模な会社の場合、法務に限らず、管理部門ないし共通系組織よりも、営業や技術開発の方により多くの人的リソースを割く必要があるのが実情です)。
このため、こうした企業の中には、法務担当者は1人しかおらず、1人でその企業における全ての法務対応を行っている会社もあります(法務担当者がひとりぼっちであることから、中には自ら「ボッち法務」と称している方もおられます)。しかも、こうした企業の場合、その1人が法務専任とは限らず、他の総務系の業務を兼務していることも少なくないということを聞いたことがあります。



質・量ともにどれだけの法
務人材を確保し、配置する
かは、企業各社の事情によ
ります。
法務部門の業務範囲
それでは、法務部門が取り扱う業務には、どのようなものがあるでしょうか。これも各社の置かれた状況、人員構成等により違い出てきますが、私が経験してきた業務を順不同に列挙してみると、以下のようになります。
| 業務 | 概要 |
| ① 契約管理 | 自社が企業活動において、相手方企業との間で売買契約、業務委託契約又は使用許諾契約等、各種の契約を締結します。その際、法務部門は、各々の契約に含まれる自社の法的リスクの有無、その管理方法を検討したうえで、契約締結に至る必要があります。契約締結自体を法務部門が行うのか、ビジネス部門が行うのか、各社により区々ではありますが、仮にビジネス部門が締結窓口となる場合であっても、法務部門が当該ビジネス部門に対して密接に連携し、強力な支援を行うことが求められ、法務部門がビジネス部門とともに相手方企業との契約交渉に同席し、意見を戦わせる場面も少なくありません。 |
| ② 社内各組織からの法務相談対応 | 社内各組織から自社の業務に関する法務相談が持ち込まれることがあり、その相談に対応します。内容によっては、社外の法律専門家(弁護士)に意見照会することにより回答を作成することもあります。 |
| ③ 株主総会・取締役 会・経営会議等の事務局または支援 | 自社の株主総会や取締役会について、関係法令を遵守した内容・方法で進める必要があります。法務部門が株主総会等の窓口役を務めるわけではない場合であっても(総務部が担うことが多い)、法務部は法的観点からサポートを行うことが求められています。また、企業によっては、自社の経営会議の常設メンバーとして法務部の責任者を参加させる場合もあります。法務部門は、企業活動において極めて重要な役割を負っていることを示すものと言えます。 |
| ④ 新サービス開発支援 | 法務部門の業務は、契約の締結やトラブル対応、機関決定にとどまるものではありません。自社が新たなサービスを開発し、ユーザに提供しようとする場合において、それがユーザをはじめとする社会に受け入れられるものとなっているか、自社のリスクが適切に管理されているか、等、場合よっては法的な枠組みを超えた観点から政策的な判断をするケースもあります。こうした業務に対応するには、法務部員がビジネス部門・技術部門等の関連組織と緊密に連携し、関連組織と同様のスピード感を持って法務対応に従事する必要があります。法務部員にとって「ビジネスは生き物」であることを実感する貴重な機会であるともいえます。 |
| ⑤ 訴訟等のトラブル対応 | 自社がユーザや相手方企業との間で何らかのトラブルが発生した場合、さらには訴訟等のステージに移行した場合には、法務部の役割は通常以上に大きなものとなります。訴訟対応にあたっては、丁寧な事案分析と証拠の収集を要しますし、自社の訴訟代理人弁護士との連携も必須になります。 |
| ⑥ 法令改正対応 | 自社の事業に影響のある法令が改正されたり、社会情勢等に応じて新たな法令が制定された場合に、社内各組織が改正法を適切に順守できるよう、社内で改正内容を周知したり、社員に対する研修を実施等することを通じ、社内に必要事項が浸透するよう、必要な措置を講じることが求められます。 |
| ⑦ ロビイング | 自社の事業に関し、新たな社会問題等が発生し、既存の法令では十分な対処ができない場合において、自社が必要な措置を講じることが可能にする新たな法制度等を実現するため、国会議員に陳情等を行うこともあり得ます。どのような法制度とすることが適切なのか、法務部員の能力が試される領域です。 |
① 契約業務
皆さんも日常経験しておられるように、企業活動においては、実に多くの契約行為が存在します。自社が他の企業から物品等を購入する場合には売買契約が、業務の遂行を他の企業に委託する場合には業務委託契約を締結することになります。この場合、契約書の作成、契約条件の交渉等は社内のどの組織が行うことになるでしょうか。
私の経験では、契約書の作成、契約条件の交渉を行う、社内の主管となる組織は、その契約を必要とする組織です(営業部門等)。法務部門は、主管組織が起案した契約書ドラフトに不足している事項を追加したり、条項相互に齟齬が生じていないかをチェックする他、(案件の内容、社内における重要度との比較になりますが)案件によっては法務部門が主管組織とともに、主管組織をサポートする趣旨で相手方器量との契約交渉等に同席し、参加することがあります。


② 社内各組織からの法務相談対応
法務部門の業務の中で、契約管理業務と並んで多くの比重を占めるのが、社内各組織からの法務相談に対応する業務だといえます。
相談内容は、契約案件だったり、トラブル案件だったり、様々で。業種による違いも大きいはずです。私が駆け出しの頃は、内線電話で相談が入ったり、居室に社員がやってきて相談に応じる等をしていました。現在は、電子メールや社内システムを通じた相談受付体制が(特に大企業の場合)確立される傾向にあり、そうして社内各組織から持ち込まれた相談案件を上司が部下に割り振り、対応を指示する方法より業務が進められることが多くなっています。
上記は、主なものを列挙したにすぎません。実は、企業の法務部門の所掌業務は、業種やその会社の置かれている状況、法務部門の人員状況等により異なります。
私自身を振り返って、新卒で入社した大手証券会社においては、金融商品取引法(当時の証券取引法)、会社法、独占禁止法、証券税制等が業務の中心であり、純粋な契約事務の比重は少なく、さらに、景品表示法については、まったく取り扱わない状況でした。
その後、転職先では、契約事務の占める割合が非常に高くなり、相手方企業との契約交渉を行う機会が多くなりました。加えて、大ヒットした新事業・新サービスの誕生の様子を間近で見る幸運にも恵まれましたし、M&A案件にも数多く対応することができ、社外の法律専門家の指導助言を仰ぐことを通じ、一人の法務スタッフとしての成長を実感する時間でもありました。
あらためて法務部門の業務範囲を考えた場合、「これは法務部門は無関係だ」として範囲を画することのできるものはありません。時代の進展、会社が置かれている状況等により、従来は法務部門が手掛ける内容ではなかったものが今では法務部門による積極的な関与を必要とする業務に変化しているということを感じ取ることができるはずです。
③ 株主総会・取締役会・経営会議等の事務局又は支援
自社の株主総会や取締役会等の適切な運営に対応・支援することも法務部門の重要な役割です。法務部門自体が株主総会や取締役会の運営窓口を務める企業もあれば、窓口役は他の組織(例えば、総務部)が務め、法務部門は関連部としてもっぱら法的観点からこれらの運営をサポートするという構成をとることもあります。
法務部門に在籍する社員は、ここでの業務を通じて、会社法の知識と実務経験を積んでいく良い機会になります。いわば、「生きた会社法」を実感できる場と言えます。このため、中には、「会社法を極めたい」という思いを抱き、(法務部門が主管組織とはならず、サポート組織である場合)、法務部門からこの業務の専担組織への異動を希望する人も出てくることがあります。
④ 新サービス開発支援
従来、社内の各組織においては、法務部門が他の組織の業務との関連で登場するのは、契約締結段階とか、トラブルの解決局面のような、いわば後半での出番となることが多いという印象を持たれていたと思います。
しかし、私自身の経験ではあるのですが、社内のビジネス部門がユーザ向けの新たなサービスを開発するにあたり、そのサービスの企画検討段階から法務がレギュラーメンバーとしてチームに参画し、ビジネス部門をはじめとする関連各組織、さらには社外のビジネスパートナー、社外の弁護士らとともに丹念に検討を行い、その結果、サービスを世に送り出したことがあります。
そこでは、新たなサービスの設計、関係するビジネスパートナーと自社との役割分担、必要となる契約等の構成、ユーザとの利用規約の策定等、法務担当者にとって腕を振るいがいのある事項が多くあります。
私は、この機会を通じ、社会に支持されるサービスが誕生するまでの過程を目の当りにすることができました。その経験は、他の類似の案件に生かすことができました。さらに、私がより重要な事柄であると認識するに至ったのは、「ビジネスは生き物である」ということです。
⑤ 訴訟等トラブル対応(訴訟等に至らない案件に対する支援を含む)
企業において、ビジネスパートナー又はユーザとの間で何らかのトラブルが発生した場合、当初は各案件の主管組織においてその収束に向けて対応するものの、思うように進まない場合には、法務部門の支援を求められる場面に移ることになります。
このような場合、法務部門は、いわば「最後の砦」として頼られることになりト、法務部門が自らの能力を存分も発揮できる場面の1つです。
解決にあたっては、事案の分析、法的論点の抽出・検討にはじまり、トラブルの当いれ、訴訟代理人の選任、訴状・準備書面等の準備等を行います。訴訟等の当日の期日の対応を含め、法務経験の浅い社員の基礎体力作りにも資する事項でもあります。
⑥ 法令改正対応
自社の事業に関係の深い法令の改正がなされた場合、社内にその内容が適切に浸透させる必要があります。その方法としては、関連組織に対する説明会の開催やその重要度如何によっては経営会議等、幹部が出席する会議体での説明を行い、各組織内で重要性を認識してもらい、準備対応を行うということもあり得ます。
⑦ ロビイング
自社のサービス等について第三者による悪用等がなされ、自社が社会から批判を受ける等の事態に至った場合において、既存の法律では解決が困難であり、新たな法律の制定を必要とする場合があります。
法律の制定には国会による審議を経て、衆議院・参議院の両議院で可決することを必要とします。このため、国会議員に対し、既存の法律では対応することのできない事象が発生しており、新たな法律を必要としている旨を国会議員に理解していただくロビイングを行うことも考えられます。



法務部門の業務は、業種や
会社が置かれている状況に
より、実に幅があります。
<まとめ>
ここまでの内容をお読みになり、現在法務部門に在籍し、日々、業務に取り組んでいる皆さんの中には、「自分は、このような業務を担当したことがない」「自分はしっかりと法務としてのキャリアをつむことができていないのではないか」といった不安を覚える人もおられるかもしれません。
しかし、ご心配いりません。なぜなら、法務部門の業務の内容は、基本的に会社の状況や人員構成等により定まるのであり、そこで業務に従事する社員がコントロールできる性質のものではないからです。
よって、今後、あなたの会社において、これまでには出会ったことのない、興味を惹かれる、新たな業務に出会ったのであれば、上司とご相談していただき、チャレンジしてみてください。自社の法務部門の新しい可能性を開拓することができれば、さらに法務の仕事が楽しくなるはずです。

