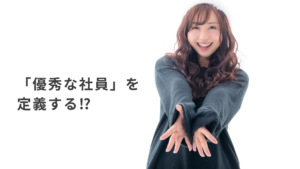はじめに
企業においては、常に優秀な人材を求めています。
社員間でも優秀さに関する話題が出ることがあります
例えば、皆さんの職場の中でも管理職同士で「〇〇さんは優秀だね」という会話がなされており、それを何気なく耳にすることがあるのではないでしょうか。
上司から「優秀」であると認められた社員には、社内での評価において良い評価がなされ、その結果、社内の昇格ルールに従って、順調に昇格し、昇進していくことになります。
その一方で、「優秀」であるとは認めてもらえない社員の場合には、優秀な社員と比較すると、必ずしも良い評価を受けることができず、昇格・昇進が遅れがちになります。
それでは、上司が認めたり、求めたりする「優秀さ」とは、いったいどのような内容のものであるか、ご存知でしょうか。
実は、この意味を正確に理解しておかない限り、あなたが現在の勤務先・職場で今よりも良い評価を受けたり、上の職位に就くことは困難であることをまず理解しておく必要があります。
そして、この意味の理解がない状態で、あなたが転職しようとしても転職先からの内定得ることは難しく、また仮に転職が実現したとしても、転職先にて出世の階段を勢いよく駆け上ることは実際上困難であるといわざるを得ないでしょう。
この記事で分かること
- 「優秀な社員」とは、どのような社員のことなの?
- どうすれば「優秀な社員」になることができるのか知りたい
- 優秀ではないと判断された社員が、「優秀な社員」に転じることはできるの?
この記事では、優秀な社員になるべく日々努力をしているものの、未だその成果を実感することができていない法務部門の社員の皆さんを対象にして、抱える不安を解消するうえで有益な情報を提供することを目的としています。
優秀な社員とは?
法務部門における優秀な社員に係る説明に入る前に、まず一般論としての優秀な社員がどのような存在なのか、その定義を見ておくことにしましょう。
会社に利益をもたらしてくれる人
「優秀な社員」とは、会社から見て、業界や業種を問わず、「会社に利益をもたらしてくれる人」であるといえます。
これは、営業職のような数字を残すことで評価を受ける職種を想像してもらえれば、理解がしやすいのではないでしょうか。
例えば、予め、期初で設定した目標を大きく上回る営業成績を残すことができたならば、それは「会社に利益をもたらしてくれた人」であるとの評価を受けやすいと言えるでしょう。
会社の未来を担える人
次に、「会社の未来を担える人」であることも、優秀な社員の定義を構成する要素であるといえます。
こうした人材は、自分で将来の予測を立てて、自身のスキルアップや会社の将来を考え、それに向かって努力することができます。
自らが主体的に、積極的に思考し、行動することができる能力は、実はビジネスにおいて非常に重要な能力であるといえます。
皆さんの周囲を見回してみてください。
中には、ひたすら上司や先輩からの指示を待っている人がいるのではないでしょうか。
そういう人は、自分がミスすることを極端に嫌い、失敗したとしても「指示をした上司や先輩が悪い」という逃げ道を要しておきたいという気持ちが無意識のうちに働くのです。
こうした姿勢の社員は、会社に利益をもたらす人とも、会社の未来を担える人にも該当しないでしょう。
もっとも、ここで注意していただきたいことがあります。
それは、優秀な人材の細かい要素には、会社による差異が生じうるということです。
会社ごとに優秀な人材を定義づける際は、新規の事業で必要なスキルを持っている人が欲しい、時間をかけて根気よく学べる人が欲しいなど、現場の意見を取り入れて考えると良いでしょう。
「優秀な社員」の特徴~一般論
優秀な人材の定義は、会社ごとに異なるとお伝えしました。
しかし、優秀な人材にはいくつか共通する特徴が挙げられます。本章では、どの会社でも共通する、優秀な人材の8つの特徴を紹介します。
①自分の役割を理解している
優秀な社員は、会社に利益をもたらすにはどうすればいいのか、会社側から何を期待されているのかを自ら思考し、よく理解しているという特徴があります。
自分が会社から求められている役割が何であり、何をすべきかを判断し、自分以外にもできる仕事は他の人に任せて、自分が本当にすべきことに集中するわけです。
こうした能動的な社員は、利益を生み出す仕組みや本質を理解しているため、会社が果たすべき目的を達成するために臨機応変に対応することができるのです。
また、このような優秀な社員は、自分自身のことも深く理解しています。
自分の持ち味、とりわけ何が得意なのかを理解したうえで、それを活かして会社に貢献していきます。
ときには、自分よりも長けている人に仕事を任せながら、会社全体の業務が円滑に進むよう柔軟に調整します。
こうした2つの能力は、その社員が日頃から自分を含め周囲の人々や社内外の動きを絶えず観察しており、変化を読み取る能力を磨いていることにより養われるのです。
漫然と毎日を過ごす社員、自分の眼の前にある業務のみを見ている社員と比較すると、日々差がつくことは、皆さんも容易に理解することができるのではないでしょうか。
②自己研鑽を怠らず学んだことを仕事に活かす
優秀な社員は、現状に満足せず努力を怠りません。
どんな分野でも常に新しい技術やシステムが生まれていること、従来のやり方ではいずれ売り上げに貢献できなくなる可能性があることを知っているからです。
常に自身をアップデートしていく必要があることに留意しており、業界の最新動向や関連情報を把握する努力をしています。
また、学んだスキルや情報を自分の中だけで収めるのではなく、会社内で共有するのも優秀な社員の特徴です。
自分だけが分かっているよりも、社内で共有・活用した方が会社全体の利益につながると捉えているためです。
皆さんの周囲には、情報等を自分のみで抱えている人がいるのではないでしょうか。
「自分だけが知っている」としても、会社の利益には直ちにつながりません。
組織全体に広めていくことを怠ることにより、会社の利益を失いかねないことに気づくことができないのです。
次項とも関係しますが、こうした社員の場合には、会社が組織である以上、自分1人で仕事をするわけではないことをあらためて確認する必要があるでしょう。
③職場の人と良好な関係構築をする
会社では、ほとんどの場合、チームを組んで複数名で業務を行います。いくら優秀な人材でも、1人ですべての仕事をこなすことはできないためです。
独りよがりで意思疎通ができない人は周囲からの理解や協力を得にくく、成果を上げるのが難しくなります。
大きな成果を上げるためには、関係者たちと円滑なコミュニケーションを取り、良好な関係を構築する力が必要不可欠です。
仕事上の問題や疑問を質問したり、進捗状況を把握したりと、職場の人と密にコミュニケーションを取れることが理想と言えます。
一方で、本人の人格も重要です。
例えば、他の人に対して高圧的な態度を取ったり、パワハラをしたりする人は、どんなに能力があっても他の社員の価値をおさえつけてしまうリスクがあるためです。
本当に優秀な人材は、自分の能力が高いだけではなく、他の社員と良い関係を築きながら個々の能力を引き出せるスキルがあるのです。
④人材育成やマネジメントができる
人材育成やマネジメントができるのも優秀な人材の特徴です。
一握りの優秀な人材だけでは、いずれ会社の成長が止まってしまう可能性があるため、次世代を担う人材の育成やマネジメントが不可欠です。
例えば、まずは仕事をやって見せて、部下に新しい仕事を任せつつ、しっかりとサポートを行っていけば、部下も無理なくレベルアップできるでしょう。
部下が育って自走できるようになると、自分自身はさらに高度で自分にしかできない仕事に集中できるため、チームや組織の生産性を高めることにも繋がります。
⑤会社の将来を考えて行動できる
優秀な人材は、広い視野で会社の将来を考えて行動できます。
事業を存続し、会社を成長させ続けるためには、最新技術の登場や社会インフラの変化など、自分が携わっている業界以外の動向も観察しながら動く必要があります。
例えば、世の中のキャッシュレス化が進むことで現金をあまり利用しなくなったり、最新医療で寿命が延びたりするなど、社会は常に変化し続けています。
このような変化にキャッチアップしつつ、自分の会社にどう活かせるかを考えられる人は、会社に大きく貢献してくれるでしょう。
⑥時代の変化に柔軟に適応できる
優秀な人材は、時代の変化に適応できる柔軟性を備えています。
不確定要素の多い近代は「VUCA時代」と呼ばれています。
働き方や消費者ニーズなど、ありとあらゆるモノ・コトが多様化・アップデートを続けており、年々複雑さを増しています。
変化のスピードが早いことも相まって、従来の製品・サービスの価値や、仕事の進め方があっという間に通用しなくなる場合もあるでしょう。
複雑な時代だからこそ、未来の予測が難しいことを認識したうえで、さまざまな変化に敏感に反応し、柔軟に対応できるマインドやスキルが重要といえます。
⑦ITスキルや知識を使いこなせる
ITスキルや知識を持ち、それを使いこなせるのも優秀な人材の特徴です。
DX(デジタルトランスフォーメーション)、リスキング、AIやビッグデータなどのキーワードが注目される昨今において、これらを理解し業務に取り入れられるかどうかが、企業成長の分かれ道といえます。
例えば、SNSなどを積極的に活用することで、より効果的なマーケティングが実現できたり、IT技術を導入することで業務の効率化が図れたりもするでしょう。
新たなツールやテクノロジーは組織の生産性や効率を高め、ときには従来の仕事のやり方を一変させるほどの影響力があります。
今、さまざまな企業でIT技術を積極的に使いこなし、企業を成長に導ける人材が求められているのです。
⑧英語や語学スキルがある
日本国内の市場が頭打ちしたり、ビジネスのグローバル化が進んだりするにつれて、英語をはじめとした語学スキルの重要性が高まっています。
企業の規模や業種にもよりますが、企業が生き残り成長を続けていくためには、いずれかのタイミングで販路の拡大や海外進出を検討する必要があるためです。
また、少子高齢化に歯止めがかからない日本において、海外から優秀な人材を迎えることも、日本企業が向き合うべき議題のひとつです。
リモートワークが浸透した現在において、海外人材を雇用するハードルは下がってきているといえます。
いずれの場合でも、現地の人たちとコミュニケーションを取れる語学スキルに加えて、日本との違いや異文化に対する理解なども求められます。
参照ページ
そもそも「優秀な人材」とは?優秀な人材の定義・特徴・採用のポイント
多くの人々が誤解している
上記の説明をご覧になった皆さんは、どのような感想をお持ちになったでしょうか。
「自分は、ここに書かれた優秀な社員の特徴にまったく当てはまらない・・・」と思い、気持ちが沈んではいないでしょうか。
また、気持ちが沈むにまでは至っていないとしても、この記事の内容を読みながら、次第に眉間に皺を寄せるようになったのではないでしょうか。
でも、ご心配には及びません。
上述の内容は、確かに優秀な社員の定義であり、その特徴を示す事項であることは確かです。
しかし、組織に属する人間の1人である会社員、法務部員にとって日常の業務の中でより重視する必要のある事項があります。
それを以下で説明していくことにします。
「何でもデキる社員」は存在しない
上述した優秀な社員の「定義」や「特徴」は、実際に企業で仕事をしている人間の眼から見ると、やや現実性に欠けるように感じるのです。
確かに、そうした定義や特徴を備えた人物は優秀だといえるでしょう。
そのこと自体に異論を挟もうとしているわけではありません。
しかし、自分の職場ないし会社に「果たしてそのような人物がいるのだろうか」という疑問を感じるのです。
そのような、最高レベル⁉の優秀な社員がいない会社であったとしても、その組織の中における優秀な社員とそうでない社員が存在するはずです。
つまり、ここで申し上げたいことは、「何でもデキる社員などいない」ということです。
この記事にて上述したような特徴を備えた人材は、果たしてどれだけ存在するでしょうか。
少なくとも私は自分の長い社会人生活を通じて、そうした人材に出会ったことがありません。
それは、私が知らないだけだという可能性は、もちろんあります。
しかし、そうした、とてつもなく優れた人が世の中に多数存在するようには思えないのです。
スポーツの世界でも同様ではないでしょうか。
確かにMLBにおける大谷翔平選手は、報道等において「規格外」であると評価されますが、それは、何でもデキる人材が世の中で稀有なものであることの証左です。
例えば、プロ野球選手であっても、打撃・守備・走塁のすべてで傑出した選手は、イチローさんのことがすぐに思い浮かびますが、それに続く選手となるといかがでしょうか。
そのイチローさんもヒットメーカーではありましたが、長距離打者ではありませんでした。
多くのプロ選手は、打撃・守備(投手を含みます)・走塁のいずれか秀でることによって自らの特徴を見出し、その世界で生き残りをかけているのです。
会社という組織も全く同様です。
上述の特徴全てを満たすことに頭を悩ます必要はないことをここで再度お伝えしたいと考えています。
真に優秀な社員の特徴とは
それでは、こうした要素を一旦横に置いておいたとして、「優秀な社員」となるためにはどうすればよいのでしょうか。
そこが皆さんの最大の関心事であるはずです。
それは、次のとおりです。
「社員が自らの能力を最大限に発揮して、自分の上司を立派に見せることができる社員」
どうすれば「優秀者な社員」になれるか
会社は、組織で仕事をしています。
この当たり前のことを忘れている人が多いのではないでしょうか。
社員個人で仕事をしているのではなく、組織で仕事をしているわけです。
ここで組織という場合の単位は、会社であったり、本部・事業部・〇〇部・課・担当等がこれに該当します。
組織単位の大小はあるとして、各組織の長は、自分が受け持つ組織の仕事・結果に対して責任を負っています。
上の役職に行けば行くほど、その責任は重くなります。
そうした状況にある上役は、自分からは配下の社員に対して弱音をはくなど、弱い部分を見せることはありません。
あくまでも毅然と、「そんなことで動揺などするなずない」かのごとく、振る舞うはずです。
しかし、実際上は、日々、孤独な苦しい戦いを乗り切るべく腐心しているのです。
もし、あなたがそうした上役の状況を察した場合、どうするべきか、考えたことがありますか?
逡巡しているかもしれません。
でも、もし、あなたが自分の備えている能力を駆使して、上司の仕事を助けることができないでしょうか。
上司といえど、何からなにまで優れた実力を持っているとは限りません。
人前で口頭で説明することに長けている人ではあるものの、文章をはじめプレゼン資料を作成することを不得手にしている場合もあるでしょう。
また、企業法務の世界に目を移したとして、民法・会社法・金融商品取引法には詳しい人であるものの、独占禁止法等の経済法には明るくないということもあり得ることです。
そうした場合に、あなたが進んで上司を補佐し、上司の持つ弱みを補うことにより、代表取締役をはじめとする経営幹部が上司の功績をたたえる評価をしてくれたことにつながったとしたら、どうでしょう?
「自分が評価されたわけではないから関係ない?」
そんなことはありません。
あなたの強力なサポートを受け、経営幹部の前で恥をかくことなく乗り切っただけでなく、高評価を受けることにつながったことを上司は決して忘れることはありません。
他の社員の手前、あなたのみを評価する口ぶりはしないはずですが、会社が定めるしかるべき評価の際には、しっかりとあなたの功績を記憶すると同時に記録するものなのです。
これが優秀な社員の仕事なのです。
この記事を読んでくださっている皆さんも「これならできるかも!?」と思われたのではないでしょうか。
世間に出回っている解説書に記載された抽象的な「優秀さ」は、それはそれとして置いておき、組織として取り組んでいる仕事、上司が力を入れなければならない事項について、あなたが自分の能力を最大限に駆使して上司を助けること、このことを意識してください。
そうすれば、あなたの眼の前に道が拓けてくることでしょう。
なぜ上司を立派に見せないといけないのか?
ここまでこの記事を読んでくださった読者の中には、1つの疑問が生じた人もおられるのではないでしょうか。
その疑問とは「どうして自分は上司を立派にみせないといけないのか」「上司を立派に見せることのできる社員が優秀だという理由が分からない」というものではないでしょうか。
社員は会社という組織の中で仕事をしています。
組織である以上、上司と部下、いわゆる上下の関係が存在します。
そして、上司は部下に対する評価を行います。
部下が昇格・昇進するためには、上司の評価・支持が必要不可欠なのです。
あなたが現在の上司を好きか嫌いかということは全く関係ありません。
ただ、あなたが現在の会社で良い評価を受け、出世をしていくには、上司のあなたに対する評価が優れていること、そして、会社におけるリーダーとして期待できることを理由として、今よりも上位の職位に推薦してもらうことが必要なのです。
上司も組織の一員として、経営幹部より難しい課題の解決を求められていることが少なくありません。
そんなとき、部下の誰が上司の窮状を察知し、いくばくかの業務分担を申し出て、上司の稼働・負担を軽減できたとしたら、その上司は何と感じるでしょうか。
「この部下は、頼りになる」ということもありますが、上司の目線からは次のような印象を受けるものです。
「この社員は、自分の仕事だけでなく、周囲の動きにも注意をしており、視野が広い」
狭い領域にしか目が向かない人材では、その仕事の品質もその程度であると考えるのです。
視野の広い人材であるとの印象を上司に与えることができたならば、あなたは上司から信頼を集めることができるようになるのです。
逆に「あの上司は嫌いだから、アイツがどうなろうと関係ない」というような投げやりな姿勢であれば、上司はあなたをより上位の職位につけることはしないでしょう。
まとめ
会社という組織における「優秀な社員」とはどのような存在であるのかは、多くの人に関心のあることですよね。
インターネット上の情報や解説記事によると、かなりハイレベルなというか、途方もない人物像が描かれています。
しかし、実際のビジネスにおける「優秀な社員」と評価される人材とは乖離があることもまた事実なのです。
会社における「優秀な社員」とは、自らの能力を最大限に発揮して、上司を立派に見せることのできる社員です。
部下としての社員は、上司の支持なしに昇格・昇進することはできないのです。